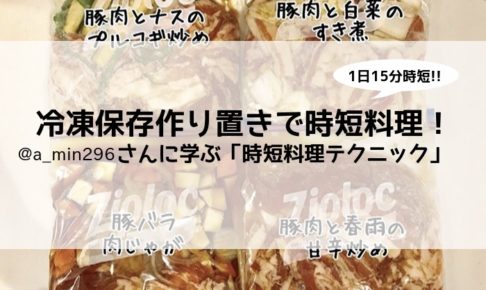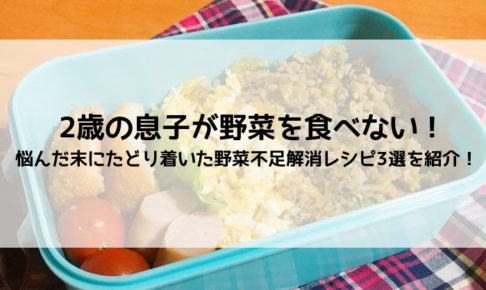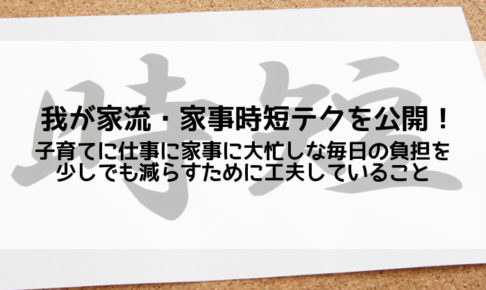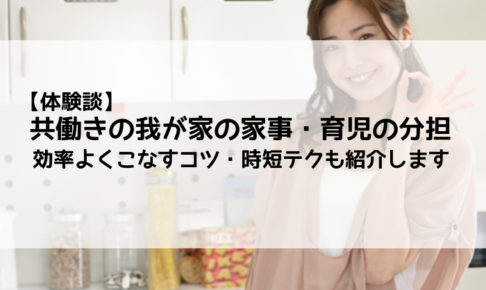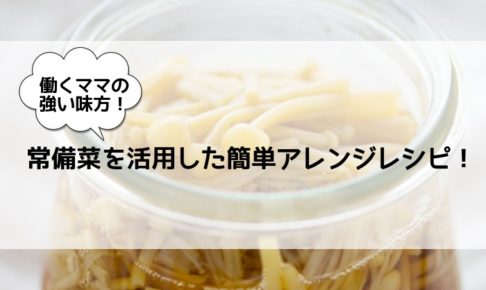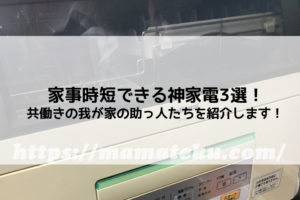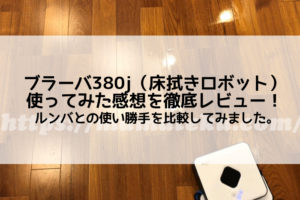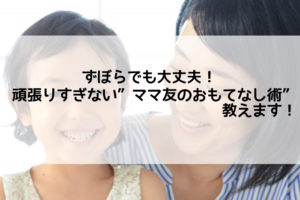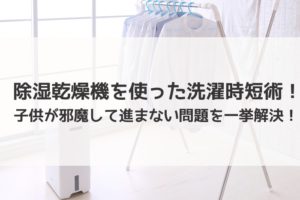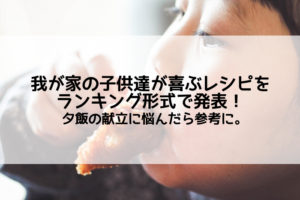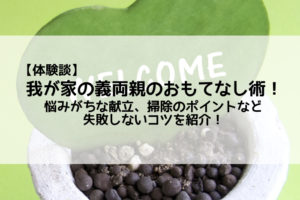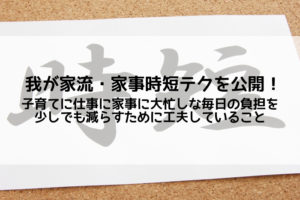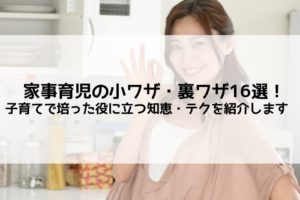tomomicchu
最新記事 by tomomicchu (全て見る)
- 働くママの強い味方!常備菜を活用した簡単アレンジレシピをご紹介! - 2018年5月5日
ママテク(@mamateku)ライターのtomomicchuです。
子育てと家事の両立、とっても大変ですよね。
私も3人の子供の相手をしながら、毎日戦争のようなごたごたした日々を過ごしています。
特に我が家は、主人の帰宅が遅いので、基本的には私一人ですべてをしなくてはならない状態です。
家事で一番困ったのが、ごはん作りです。
特に、育児休暇明けの食事の準備は、本当に大変でした。
そこで今回は、働くママにもおすすめな、私がよく作っている常備菜や、その常備菜を使った簡単アレンジレシピをご紹介します。
週末に常備菜を作っておくだけで、あとはちょっとしたアレンジで1品作ることができるものばかりです。
手軽に簡単に作れるメニューなので、気になったものがあれば是非試してみてくださいね。
パッと読むための目次
常備菜の定番、なめたけを作ろう!
常備菜と言えば、簡単に作れて、日持ちがするものです。
その中でもおすすめなのが、なめたけです。

なめたけはビン詰めで売られているものを使っている人は多いものですが、実は自宅で簡単に作ることができます。
しかも、子供ってなぜかぬるぬる・ねばねばしたものが好きで、味もはっきりとしているので、我が家ではごはんが進みやすくなりました。
なめたけの作り方(基本)
なめたけを作るときに必要な材料は、ほとんどのおうちにあるものばかりなので、思い立ったらすぐに作ることができます。
【スポンサードサーチ】
- えのき(200gぐらい)
- しょうゆ(大さじ3)
- みりん(大さじ3)
- 酢(小さじ1)
作り方は簡単です。
小鍋に3分の1~4分の1にカットしたえのきを入れて、そこにしょうゆ・みりんを入れます。
そのまま最初は中火で温めていきます。
最初は水分がほとんどない状態ですが、火が通っていくと、えのきの水分がでてきてたれでひたひたの状態になります。
粘り気が出てきたら、酢を入れてそのまま水分が少なくなるまで煮詰めます。
火をつけてから、完成までは約3分ぐらいなので、とっても簡単に作ることができます。
完成したなめたけは、煮沸したビンに入れて、冷蔵庫で保管しておけば1週間ぐらいは持ちます。
なめたけの作り方(めんつゆ・電子レンジ編)
さらに簡単に作りたいという人は、めんつゆと電子レンジを使う方法もあります。
- えのき(200gぐらい)
- めんつゆ(大さじ2)
- 水(大さじ2)
- 酢(小さじ1)
作り方は、耐熱容器にカットしたえのきと、めんつゆ、水を入れて、そのまま電子レンジでチンします。
我が家の電子レンジの場合、500Wで4分ぐらいでOKです。
ご家庭にある電子レンジによって、加熱時間は調節してみてください。
しっかり火が通ったら、仕上げにお酢を入れて、全体をよく混ぜて冷まします。
めんつゆで作る時には、めんつゆの濃縮などもあるので、たれの味見をしてから加熱しましょう。
少し濃い目の味にしておくと、アレンジしやすいなめたけが出来上がります。
基本のなめたけは、使うきのこはえのきですが、えのきだけでなく、なめこをプラスしたり、まいたけなどの食感の異なるきのこをミックスしても、また違った味わいを楽しむことができます。
基本のなめたけに飽きてきたら、きのこの種類を変えてみるのも、また違った味わいを楽しむことができるポイントです。
きのこの種類や量を変えた時には、加熱時間や調味料の量を調整してみてください。
きのこは水分が多い食材なので、調味料は少し濃い目に調節しておいたほうが仕上がりの味はしっかりと決まるでしょう。
なめたけの簡単アレンジレシピ
なめたけは、炊きたてのごはんにかけたり、大根おろしに乗せて食べるとシンプルでとてもおいしいですよね。
しかし、なめたけは実はアレンジ自在の便利食材です。
自家製のなめたけを作ったら、アレンジレシピに挑戦して、簡単におかずを一品増やしちゃいましょう。
ほうれん草のなめたけ和え
食卓にあと一品足したいというときに便利なのが、ほうれん草のなめたけ和えです。
作り方はとっても簡単です。

洗ったほうれん草をお好みの固さにゆでて、しっかりと水気を絞ったら、3~4センチ程度の長さにカットします。
そこに、なめたけをたれを少し多めに入れて混ぜます。
味付けなどは、なめたけとなめたけのたれでOKなので、誰でも失敗なく簡単に作ることができます。
ほうれん草のえぐみも、なめたけの味でカバーできるので、とても食べやすく仕上がります。
なめたけとツナの炊き込みご飯
なめたけは、ごはんにかけるだけではなく、炊き込みご飯にしても美味しいです。
- お米3合
- なめたけ(100g~120gぐらい)
- ツナ(1缶)
- 顆粒だし(小さじ1)
- しょうゆ(小さじ1~2)
作り方は、研いだお米に材料を全部入れて、水を入れたら軽く混ぜて、炊飯器のスイッチを入れます。
炊き上がったら、よく下から全体を混ぜて完成です。
しっかり味がついているので、おにぎりやお弁当にもぴったりです。
白身魚のなめたけホイル焼き
しっかりおかずになるのが、なめたけの魅力です。
働くママや、子育て中のママはどうしても魚料理が面倒に感じてしまいがちです。
魚料理は、子供に合わせようとすると、煮たり焼いたり、手間がかかるものです。

しかし、魚の栄養を考えると、子供にこそしっかりと食べてもらいたいものですよね。
なめたけがあれば、簡単においしい魚料理を作ることができますよ!
- 白身魚(タラなどあっさりしたものがおすすめ)2枚
- 料理酒(大さじ1)
- なめたけ(大さじ2)
白身魚は、気になる骨やうろこなどを取り除いて、料理酒をかけて10分程度つけておきます。
10分程度おいておくと、魚から水分が出てくるので、しっかりとキッチンペーパーで拭き取りましょう。
大きめにカットしたアルミホイルの上に、下処理をした白身魚をおいたら、その上になめたけをかけます。
ふんわりとアルミホイルの口を閉じて、そのまま、オーブンで焼きます。
オーブンがある場合には、200℃に熱したオーブンで12分程度でOKです。
オーブンがない場合には、オーブントースターでも代用可能です。
オープントースターの場合にも、熱めの温度設定にして、15分程度焼きます。
ときどきアルミホイルの中をチェックして、火が通っているか確認しましょう。
焼きあがったら、万能ねぎなどをかけると、彩りも明るくなって良いですよ。
味もしっかりとついているので、子供でも食べやすく、ごはんとの相性もばっちりです。
栄養たっぷりの常備菜、スタミナ納豆!
常備菜に使えるのは、野菜やキノコだけではありません。
納豆も、アレンジ次第でたくさんのお料理に活用することができます。

栄養もたっぷりで、美容にも良い納豆は、積極的に取りたい食材の一つでもあります。
子供でも食べやすいものばかりなので、ぜひ作ってみてください。
スタミナ納豆の作り方
スタミナ納豆の作り方を覚えておくと、いろいろなお料理にアレンジすることができます。
- 納豆(3パック)
- ひき肉(100gぐらい)
- ねぎ(1本)
- しょうゆ(適量)
- にんにく(一片)
- しょうが(一片)
作り方は、熱したフライパンに油(分量外)をいれて、みじん切りにしたにんにく・しょうがを炒めて、香りがたってきたら、粗みじんにしたねぎとひき肉を入れて、パラパラになるまで炒めます。
ひき肉の種類は何でもOKです。
しっかりとした味にしたいときには、豚や牛豚のあいびき、さっぱりとした味にしたいときには鶏ひき肉がおすすめです。
油も、ごま油にすると、また風味が変わって違った味わいが楽しめます。
材料が炒め終わったら、あらかじめたれをいれて混ぜておいた納豆と混ぜ合わせます。
しっかりと全体を混ぜて、味をみて薄かったらしょうゆを足しましょう。
これで、スタミナ納豆は完成です。
スタミナ納豆の簡単アレンジレシピ
スタミナ納豆は、そのままごはんにかけて食べても美味しくいただけますが、アレンジ次第でおかずとしても活用することができます。
納豆チャーハン
スタミナ納豆を簡単にアレンジする方法として、納豆チャーハンがおすすめです。
子供と過ごすランチタイムや、ごはんの支度に時間がかけられないときに、大活躍するメニューです。
作り方は、熱したフライパンでごま油を温めて、そこにご飯を入れて炒めます。
ごはんに油が回ったら、あらかじめ作っておいたスタミナ納豆を適量投入します。
納豆が入ったら、時間をかけずにさっと炒めて、全体が混ざったら完成です。
サラダ菜などの、葉物野菜にまきながら食べても美味しいので、ヘルシーに食事を楽しみたい人には、葉物野菜と一緒に食べるのがおすすめです。
納豆オムレツ
子供にも人気で、大人にはお酒のおつまみにもなるのが、納豆オムレツです。

普通の納豆で納豆オムレツを作る人も多いのですが、スタミナ納豆で作ると、ひき肉やネギなどの野菜も入っているので、ボリュームもしっかりあって、立派なおかずになります。
作り方も、とっても簡単です。
溶きほぐしたたまごを焼いて、半熟になったらスタミナ納豆を入れて、そのまま形成して完成です。
好みによって、チーズをプラスしても美味しいですよ。
子供にも人気で、卵に味を付けなくてもスタミナ納豆の調味によってしっかり味がついているので、失敗がないのも魅力です。
ふっくらとしたオムレツは、子供たちにも人気のメニューです。
納豆巾着
和風でしっかりとしたおかずを作りたいときには、納豆巾着がおすすめです。
あらかじめ油抜きして半分にカットしておいた油揚げに、スタミナ納豆を入れて、口をつまようじなどで止めます。

お稲荷さんを作るような要領で、スタミナ納豆を入れていくと、仕上がりもきれいになります。
油揚げはしっかりと油抜きをして、カットした時に口を開いておくと、作るときにスムーズにスタミナ納豆を投入することができます。
スタミナ納豆を入れて、しっかり口を閉じたら、フライパンで油揚げにこんがり焼き色がつくまで焼きます。
両面をしっかりと焼くことで、サクサクとした食感を楽しむことができます。
フライパンを使わなくても、オーブントースターで焼いてもOKです。
オーブントースターで焼く場合には、つまようじが焼けてしまうこともあるので、十分に注意しましょう。
中に入っているスタミナ納豆は加熱済みなので、油揚げがこんがりと焼ければ完成です。
スタミナ納豆を作り置きしておくだけで、10分もかからず作れるおかずです。
常備菜の美味しさをキープするポイント
常備菜は、時間があるときにまとめて作っておくことで、毎日の食事の準備が楽になったり、アレンジの幅が広がるものです。
常備菜を用意する時には、おいしくキープするためのポイントがいくつかあります。
しっかりとポイントをおさえておくことで、おいしいままの常備菜を用意することができますよ。
保存容器は適したものを準備する
常備菜の保管には、保存容器がポイントになります。
容器のスタイルとしては、しっかりと口がしまるもので、できればプラスチック製ではなくて、ガラスや陶器で出来ているものの方が、保存容器として適しています。

殺菌処理など、煮沸消毒も必要となるので、ガラスや陶器などの素材で出来ているものがおすすめです。
常備菜の容器は、衛生的にしておくことが重要です。
普通の食器とは異なり、常備菜は長めに食料を保管しておくので、保存状態が重要です。
煮沸消毒をして、しっかりと水分を乾かしたきれいな容器に、作った食材を入れて保管しておきましょう。
煮沸消毒の方法は、大きめの鍋に多めのお湯を沸かします。
グラグラと煮立ったら、そこに保存容器を入れて3分間煮詰めます。
煮詰めている間は、容器の向きを変えたり、直接鍋に当たらないように注意しながら煮詰めましょう。
容器を動かすときや、取り出すときにはきれいな菜箸やトングを使いましょう。
菜箸やトングが汚れていると、煮沸消毒の意味がなくなってしまうので、要注意です。
同じ種類のものをいくつか購入しておくと、冷蔵庫の中も、すっきりと整理整頓できるので便利です。
また、蓋をしっかりと閉めておかないと、そこからほこりなどが入ってしまったり、臭い移りの原因にもなるので、しっかりと密封できる容器を選びましょう。
常備菜を始めた頃に、食器にサランラップで封をして保管していましたが、汁漏れや臭い移りが気になって、密封容器にたどり着きました。
ビンなどのしっかりと蓋が出来るものがない時には、密封できるタッパーや、ジップロックなどの保存袋で空気を抜いて保管するのも、応急処置としては利用できます。
味はしっかりとつける
常備菜をおいしく作るポイントは、味をしっかりとつけることです。
味付けは薄味にしたいと思っている人も多いと思うのですが、常備菜は時間が経つことで味がどんどん馴染んでいってしまいます。
作ってから食べるまでの時間がかかる常備菜の場合には、しっかりとした味付けが必要なんです。
しっかりとした味付けといっても、塩や砂糖を増やして味を濃くするのではなく、だしをしっかりととったり、煮込み時間を長くして味をしみこませるなども、おいしくするためのポイントです。
普段薄口しょうゆを使っている人は、常備菜には普通のしょうゆを使ったり、だしもいつもよりも濃い目にとって使うと良いでしょう。
フタをしめる前に、しっかりと冷ます
常備菜の保管で重要なのが、最初にしっかりと熱を取ってから保管するということです。
忙しいと、ついつい熱いうちに容器のふたを閉めて、冷蔵庫に入れてしまいたくなります。
しかし、常備菜をおいしくキープするためには、しっかりと冷ましてから保管をすることが重要です。
熱いうちに容器をしめてしまうと、湯気が水蒸気となり、蓋や容器についてしまいます。
この水分が、味を変えてしまったり、細菌の繁殖の原因になったりもします。
少し面倒ですが、常備菜を作ったら、しっかりと熱を取ってから蓋をしめて保管しましょう。
使うときが重要
常備菜を最後までおいしくキープするためには、使うときが重要です。
例えば、ちょっとだけ使いたいときや、自分のお皿に少しだけ取り分けたいときなど、今まで自分が使っていたお箸などで、ついついとってしまいたくなります。
しかし、常備菜にとっては、この行為が最もNGな行為です。
常備菜は、長期間保存ができるように、保存容器を煮沸消毒をしたり、しっかりと冷まして細菌の繁殖を抑えるようにしたり、手間暇をかけて作っても、使いかけの箸やスプーンを使っただけで、今までの努力と手間が無駄になってしまいます。
使うときには、新しいきれいなお箸やスプーンを用意して、取り分けように使用したり、使いたい分だけお皿によそって出すようにしましょう。
食べないのに、冷蔵庫から常温へ放置して、また冷蔵庫にしまうのも温度差によって傷んでしまいます。
唾液や食べかけの食材などが混入すると、そこから細菌が繁殖したり、カビなどの原因にもなります。
上手に管理をすることで、最後までおいしい状態をキープすることができますよ。
まとめ
働くママにとって、常備菜は食事の準備の時短アイテムとして、とても便利なものです。
常備菜のレパートリーを増やすことで、そこからのアレンジメニューも増えていくので、お料理の幅も増えていきます。
常備菜は、作ったときだけでなく、使う時の工夫も必要です。
衛生的な状態をキープすることで、最後までおいしく食べることができます。
常備菜を上手に活用して、ごはん作りを簡単にしましょう。
アレンジメニューによって、同じ常備菜でも飽きずに食べることができます。
時間のあるときに、何品か作っておいて、忙しい日を乗り越えていきましょう。