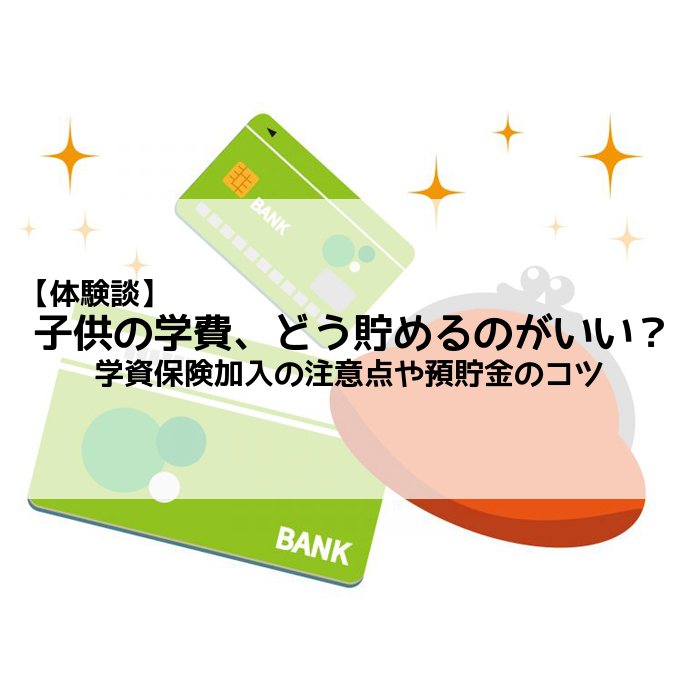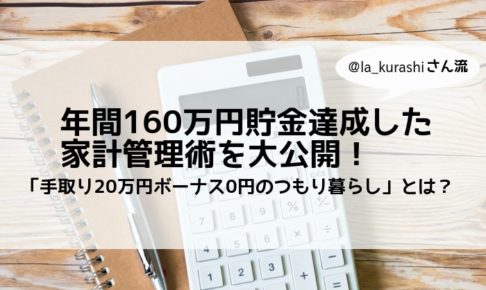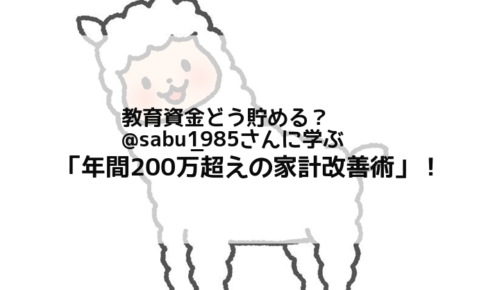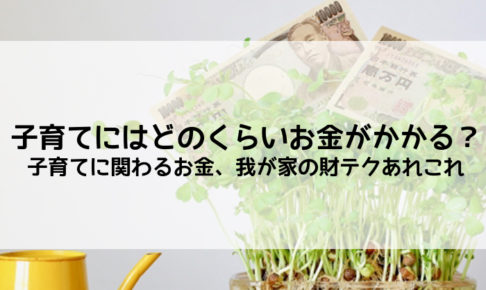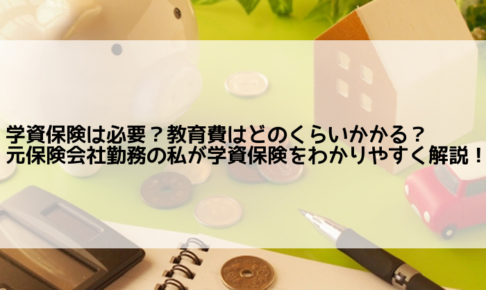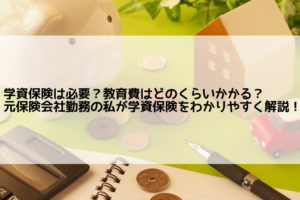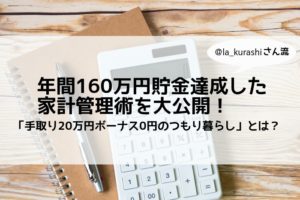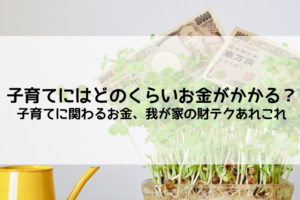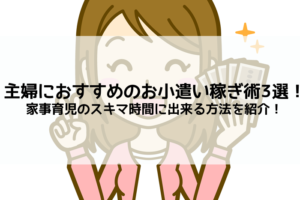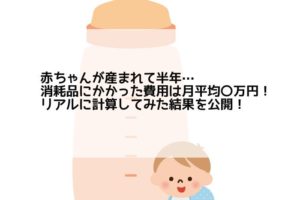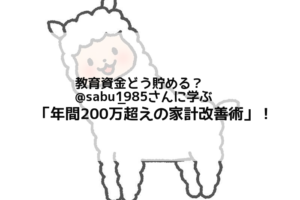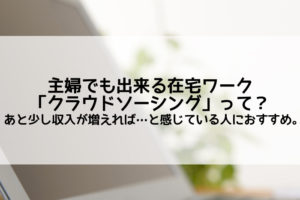Write.mama
最新記事 by Write.mama (全て見る)
- 【体験談】子供のおもちゃの片づけ方は小さいうちからが大事!子供をお片付け上手に育てるコツを教えます! - 2018年1月5日
- 【体験談】子供の学費、どう貯めるのがいい?我が家の実体験を元に学資保険加入の注意点や預貯金のコツをアドバイス! - 2018年1月2日
- 【体験談】お祝い返し、カタログギフトで大失敗した話…!子供へのお祝い返しを選ぶことで学んだこと。 - 2017年10月21日
ママテク(@mamateku)ライターのWrite.mamaです。
子供の学費にかかる費用って、子供が小さい頃はまだあまりピンとこないかもしれませんが、結構重要なこと。
今のうちから真剣に考えておかないと、子供が大きくなった時に学資などもが準備できなくなってしまいます。
うちの子はもう18歳になり、まさに進学時にこのお金の問題に直面したばかり。
今回はそんな我が家の実体験を元にどのタイミングで学資保険などの貯蓄を始めるべきなのか、毎月の積立はどのくらい?そういったことを書いていきたいと思います。
パッと読むための目次
子供に関わる出費で真っ先に考えたいのはやっぱり学資!
子供が生まれたら、おむつやお洋服、その他いろいろな出費が重なり、すぐに学資について考える方は少ないかもしれませんが、この時世だからこそ考えておかなければいけないと思います。
我が家の場合、何の相談もなく旦那さんが学資保険に加入してきました……しかも、月額が結構お高めで、何と満期が18歳。
『一体どうするの!?』と当時はもちろんケンカになりましたが、今となってはそれもいい思い出です。
そして、18歳を満期にしてくれていたことには感謝しています。
ですが、正直、それでもまったく足りない!というのが現実でした。

そう、生まれてすぐに学資保険に入りましたが、満期で入って来るお金だけでは進学準備には足りませんでした……。
専門学校、大学に入るには本当にお金が必要なのだと痛感しています。
だからこそ、今から積みたてを始める方には将来直面する問題をしっかり把握し、準備をしておいて欲しいと思います。
【スポンサードサーチ】
今の金利や月額を考えてみよう
もちろん、学資保険をかけるとなると、毎月の積みたてが必要になります。
そこを家計から賄うわけですが、それができる状況かどうかが重要ですよね。
ない袖は振れないという状況では、そもそも学資保険をかけることが難しくなってしまいます。
ちなみに我が家は郵便局の学資保険だったのですが、HPをチェックしてみると最近の状況が見えてきました。
ゆうちょの学資保険の場合は、今は3段階に分かれて紹介されているようです。
ここでも書かれていますが、満期をいつに設定するかがとっても重要です!
実は、我が家の学資保険の満期は2月でした。すでに秋頃には進学先は決まっており、満期で配当金が入ってくる前に入学金を納めなければならず、預貯金から出すことになりました。
もちろん加入してきた旦那さんも、まさか秋には入学が決まるなんて思っていなかったと思います。
18年も前の話ですし、仕方がありません。
何とか出してあげられたのは、子供名義で「もしも貯金」をしていたからです。

あくまでも学資は満期があり、それまで配当金を受け取ることができません。途中、何かあったときのための口座がこの時は役立ちました。
学資保険と合わせて、子供名義の「もしも貯金」はオススメです!
ちなみに、HPに載っている学資で我が家のものと1番近いのは「小・中・高+大学入学時」の学資準備コースになります。
18年前に加入したものなので、途中の配当金は15歳のときに1回だけでした。
そのときの配当金も、高校の入学金で全部使い切ったので、入っておいて本当によかったと思っています。
確か25万ほどの配当金で、20万を入学金、残りは制服の購入費に充てました。
この時も、配当金が入ったのはやはり2月だったので預貯金から先に入学金は支払いました……。
ぜひ、お子さんが私学に入る可能性も考えて満期を設定してください。
私立は公立よりずっと早く入学が決まり、その分入学金の納入日も早いのです。

HPにもありましたが、17歳で満期というコースもあるようです!これはとってもいいと思いますよ。
月額の保険料は、窓口で相談を
HPでは月額の保険料を算出するシミュレーターもありましたが、やっぱり窓口で相談するのが1番だと思います。

学資は、加入したら途中で解約してしまうと損をしますし、子供のこれからを考えると途中解約はしたくないですよね。
だからこそ、毎月しっかり払い込める金額のものが理想です。
あとは10年後に同じ金額を支払えるのかしっかり考えることも大切です。
我が家は旦那さんの収入が減ってしまい、私の収入から子供の学資を何度か入金するということもありました。
あくまでも旦那さんのお給料から生活費、保険などをすべて負担していましたが、それが難しくなってしまったのです。
旦那さん自身も張り切って高い保険料の学資に入ってきたことを後悔していました。
3か月滞納したのち、「今月入れないとまずい」と告白してきて、慌てて私が振り込みに行く、ということを何度か繰り返しました。
もうすぐ満期を迎える身としてはいい思い出ではありますが、はっきり言ってそういうことが度々発生すると夫婦仲に亀裂が入るのは確かです。
そうならないために、無理なく払い込める金額の学資を選ぶように心がけてみて下さい!
絶対、我が家のように旦那さんがひとりで勝手に決めて来た、とかではなく、しっかり夫婦で話し合った上で加入を決める。
月額の支払い金額を将来を見据えて無理のない範囲で決めるという順序をしっかり踏みましょう。
その方が、後々絶対揉めません。
ゆうちょ以外にも学資はある
我が家はゆうちょ以外の学資にお世話になっていませんが、その他の保険会社でも学資保険を設定しているところがたくさんあります。
友人のところではソニー損保の学資に入っているという人もいます。
通販保険の大手ですが、ネットからの申し込みなどに抵抗がない方はHPを見てみるといいと思います。
たくさんの保険会社で学資を設定しているので、資料請求して比較してみてもいいと思います。
私たちのときは、選びようがなかったこともあるためゆうちょの学資ですが、今のように比較対象があるのなら比べたかったです。
いまから学資保険への加入を検討している方はぜひいくつか比較検討した方がいいと思います。

また0歳から学資をかけない方もいて、小学校入学から入ったという方もいます。
ただ、その場合は払い込む年度が少なくなるので、月額の保険料に差が出てくると思います。
支払いの負担を考えるなら早めの方がいいですし、受け取りの配当金の大きさを考えても遅いよりも断然早い方がいいと思います。
お子さんが小さく、保育園料などもかかって大変とは思いますが「いくらなら出せる」という金額を算出してみて、そこから合う学資を探すという方法もあると思います。
ソニー損保以外だと、JAの学資も有名みたいですね。私の周りだと、ゆうちょまたはJAが多かったです。
実家が農家という方はゆうちょもJAも両方加入しているという強者もいました。
さすがに2つかけていれば安心感は大きいですが、それができるのがすごいですね。
学資保険ではなく定額貯金にした、というお家もある
実は、学資保険には加入せず、定額貯金で残した、というお家も私の友人の中ではありました。
やっぱり収入に不安があり、毎月定額を納入できるか不安があった、ということが理由のようです。
金額としては5000円~1万円が多かったです。
だいたい3年など短期間に満期を迎えるように設定しておき、その時にまた掛け金を見直し無理なくお金を残しておくという方法です。
これでもしっかり残せるなら問題ないと思います。
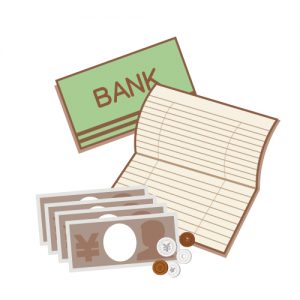
我が家の場合、定額ではありませんが子供の名義でキャッシュカードを作らない貯金用の口座を作り、毎月少しずつではありますが入金しておきました。
ときには3000円。ときには1万円という風に、その月に合わせて入金できる金額は流動的でしたが、無理なく積み立てられました。
もし早い段階で学資保険に加入するのは難しいという場合、こういう選択肢があることも覚えておくといいと思います。
その場合は、あまり自宅の近くにある銀行だと、簡単に下ろしに行けるので貯まりにくいということもあるようです。
それを防ぐということであれば、少し離れた場所にある銀行にあえて口座を作り、キャッシュカードは作らないといいかもしれません。
子供の学資を残す手段は何も学資保険だけではありません。

兄弟が生まれた場合、どうする?
実は、1人目には学資をかけたけど、2人目は何もない……というご家庭が多いようです。

友人のところも、来春2人目が高校受験を迎えますが、学資がない状態での入試になります。

一応、第一志望は地元の公立高校のようですが、もしもの備えは大事なので併願の可能性もあります。
なるべくなら、兄弟にも同じ条件の学資へ加入しておくことが大切だと思いますが、家庭の事情で難しいこともあると思います。
その場合は、1人目の子供にかけた学資をどう使うか、使い方を考えてみるといいようです。
なるべく全額使わない。または、満期より前にもらえる配当金を定期預金にしておき、2人目の子供の学資に充てるなど工夫すると困りません。
どのくらいあればいいのか、という点については、やはり学校ごとに違うので一概には言えないのですが、公立であればそれほど心配いりませんが、将来私立を考えている場合は早いうちからなるべくたくさん残すことを考えた方がいいですね。
実際、どのくらいのお金が入ってくるの?それでも足りないときは?
我が家の場合、途中の配当金は25万だったという話は先に書きましたが、2月に迎える満期で受け取れる金額は240万くらいのはずです。
郵貯のHPの金額と比べてもらえばわかりますが、少ない金額と言えると思います。
一生懸命高いと思って払っていた学資ですが……最終的にはこれからの進学先でかかる費用と比較すると、半分にも満たない金額になることがわかりました。
すでに入学金は支払っているため、それを省いたとしても足りません。
現実的な問題として、子供が高校を卒業して専門的な知識を学ぶことになった場合、とんでもない金額のお金が出て行くことは確かです。
そもそも、学費以外にもしひとり暮らしが必要ならある程度の生活費の援助も必要になると思います。
自宅から通うにしても、交通費が必要です。
制服ではなくなるので、私服もある程度必要でしょう。そうなると、出て行くお金の多さがよくわかります。

もちろん、本人がアルバイトをして足りない分を賄い、補うことも必要ですし、我が家の場合は学生支援機構から学費を借り入れることが決まっています。
こちらの審査はかなり早い段階からあり、年に2回設定されているので1回目の審査がダメでも2回目があります。
もし、準備していた学資で足りないとわかった場合は、高3になった時点ですぐに審査書類を出しましょう。
学校から配布があり、説明会を開いてくれる場合もあります。
ちなみに、銀行から学資を借りる方法もあります。学生支援機構の審査が通らない場合、銀行に相談するのがベストです。
各銀行に学資ローンのパンフレットがあるので、こちらも早いうちに目を通しておくといざというときに困りません。
銀行系の学資ローンに関しては、我が家は高1の段階で1度窓口に相談に伺いました。
とっても親切に教えてくれるので、こちらも考えましたが学生支援機構の方の審査に通ったため、銀行の学資ローンは借りずに済みました。
早いうちから心配ばかりしても仕方がないのですが、やはり備えあれば憂いなしです。
子供の学びに対する意欲を損なうことがないように、しっかり準備してあげてくださいね。
まとめ:子供の学資を用意する方法はいくつもある。それぞれの家庭に合う方法で!
子供の将来のために、ある程度のお金を残しておいてあげたいと思うのは親としての優しさだと思います。
ですが、それぞれに家庭の事情もあり、合った方法も様々。それぞれ家庭の事情に合わせ、どうやって学資を残せばいいのかを夫婦で検討してみて下さい。
ゆうちょの学資、JAの学資、ネット保険、銀行系の学資ローン。通常の預貯金、定額貯金。
あくまでも、親の名前ではなく子供の名前で残すものなので、口座を開く際はキャッシュカードは作らず「残す、貯める」ことを意識する。それだけでも充分違いが出ます。
実際、どのくらいかかるか見当がつかないものなので、どのくらい残せばいいのかもわからないという人は、自分のとき、両親はどのくらいのお金を残してくれていたのか聞いてみてもいいと思います。
私個人だと、私には学資がなかったので……そもそも進学は断念。
成人式用に20万の積み立てがありましたが、着物を作らなかったのでそれをそのまま結婚した時にもらいました。
今となってはいい思い出ですが、やっぱり当時は進学できないことが辛く、大学に進学した友達に会えないなどで落ち込んだこともありました。
自分がそういう思いをしたので、できれば自分の子供には同じ思いをさせたくない。そう思っています。
結局準備していた学資では足りなかったわけですが、子供用に残した預貯金で何とか入学金は払えましたし、これから下りてくる学資の満期金額で2年分くらいの学費は何とかなります。
専門分野に進むため、文系の大学へ行くより学費がかかってしまうのですが……そういう進学先の違いでかかる学費に違いがあるので、専門分野に行きそうかも?と思ったら早めに学費としてお金を残しておく方がいいと思います。
今は男女問わず専門分野を学ぶ姿勢があるため、女の子だから文系などと思い込まない方がいいですね。
どっちに転んでもいいようにしっかり準備しておくと、きっと困りません!
学費の心配はいらないと言ってあげられると、子供の学ぶ意欲も続きます。
祖父母から援助を受ける、という手段もありますので、もし両親に相談できればそれもありだと思います。金利がない分、ありがたいですよね。
その代わり、援助を受ける分だけしっかり祖父母に恩返しできるよう、その点について子供と話し合っておくといいと思います。
子供の将来が少しでも明るくなるように、頑張って必要なものを残してあげたいですね!