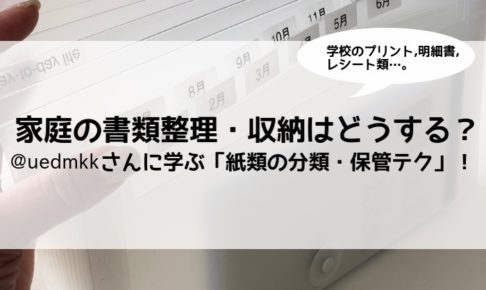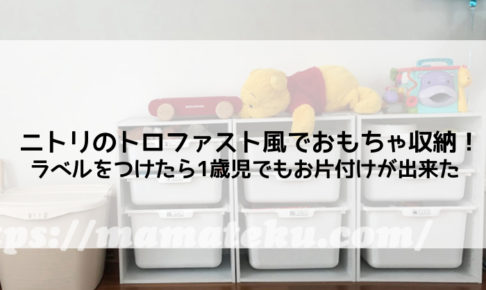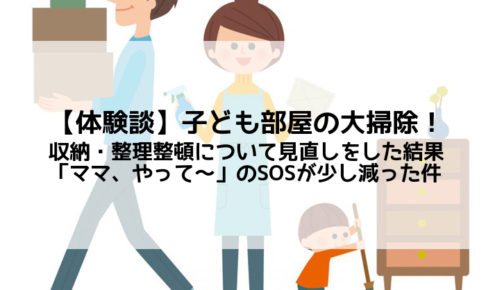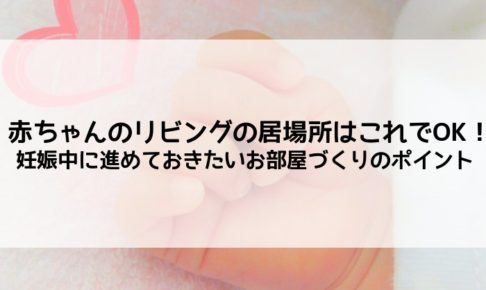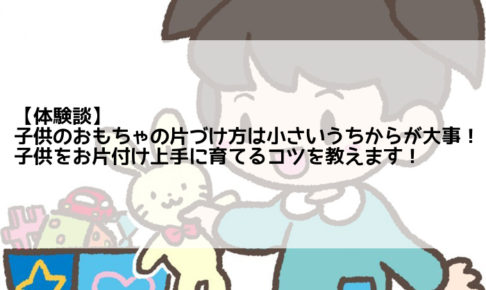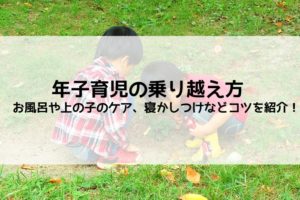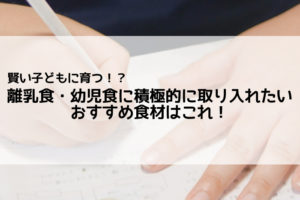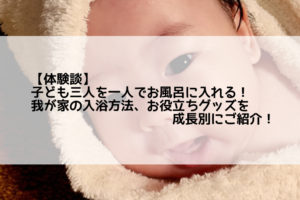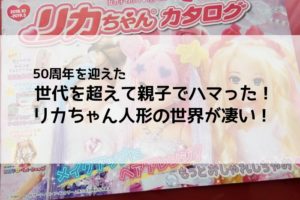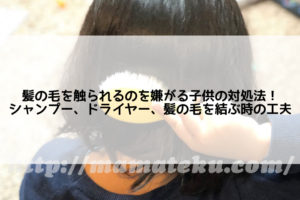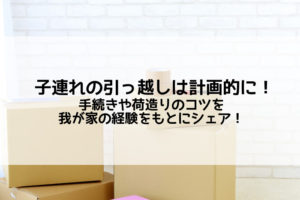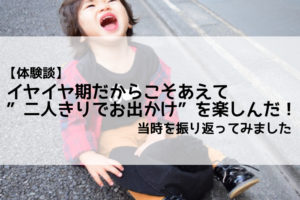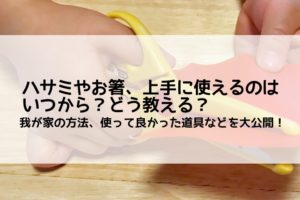Write.mama
最新記事 by Write.mama (全て見る)
- 【体験談】子供のおもちゃの片づけ方は小さいうちからが大事!子供をお片付け上手に育てるコツを教えます! - 2018年1月5日
- 【体験談】子供の学費、どう貯めるのがいい?我が家の実体験を元に学資保険加入の注意点や預貯金のコツをアドバイス! - 2018年1月2日
- 【体験談】お祝い返し、カタログギフトで大失敗した話…!子供へのお祝い返しを選ぶことで学んだこと。 - 2017年10月21日
ママテク(@mamateku)ライターのWrite.mamaです。
子供のおもちゃの片づけ方に悩むパパママは多いと思います。

実は、意外とそうでもないのです。
小さいうちからおもちゃを与え過ぎない。片づけるなら一緒に、最後まで丁寧に教えてあげると子供は片づけ上手になれます!
また、片づける場所をわかりやすく決めてあげることで子供は散らかさなくなります。
今回は私が子供の様子を見ながら考えた片づけ方についてお話したいと思います。
パッと読むための目次
ところで…おもちゃ、ありすぎませんか?

特に一人っ子のお家は、おもちゃが豊富でも実際には子供が遊びきれていないこともあると思います。
うちも一人っ子で、祖父母や周りからたくさんおもちゃをもらったのでとにかく溢れるほどありました。
そこで、まずオモチャの断捨離からスタートすることに。

子供が2歳、3歳ならそろそろ断捨離のタイミングです。
まず、子供がよく遊んでいるおもちゃが何かを把握してみて下さい。
【スポンサードサーチ】
よく見ていると、お気に入りがはっきりして、実はあまり手を伸ばさないおもちゃがあることがわかると思います。
あまり遊ばないオモチャの把握が出来たら次にそのオモチャを、子供の目の届かない場所に隠してみます。
数日経って、「あのおもちゃがない!」という意思表示がなければ、子供にとって思い入れがないことがはっきりします。
そういうおもちゃは処分対象にします。
頂き物だったり色々思うことがあったとしても、片付かない、遊ばないおもちゃは邪魔でしかありません。
心を鬼にして思い切って処分しましょう。
捨てる、または買い取ってくれるところへ持ち込むか、フリマに出すのもいいですね。
知育系のおもちゃだったとしても、子供が遊ばないなら一切知育の役に立っていません。
遊ぶ、遊ばないを選別することで、子供がどんなものに興味があり、どんなおもちゃが遊びやすいのかもわかります。
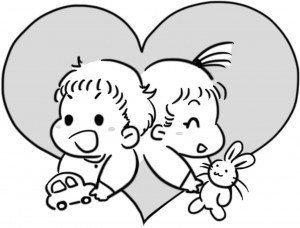
遊ばないおもちゃを買ってしまうという「親のうっかりミス」も防ぐこともできるので、子供が小さいのにおもちゃが溢れるほどある場合は、まずおもちゃの選別からスタートしましょう。
数を減らすと、片づけはぐっと楽になります!
「何でもある」ではなく、手持ちのおもちゃで上手に遊べるかどうかも子供の頭を回転させるためのよい知育です。
おもちゃは与え過ぎないことは大切だと思います。
なるべく、親の目の届く場所に片づける場所を確保する
子供のおもちゃを片づける理想の場所は、私はリビングだと思っています。
それはなぜかというと、来客などがあった場合、絶対に片づけなければならない場所だからです。
パパやママが片づけているところを子供が目にしやすい場所もリビングなので、子供のおもちゃも、小さい間はリビングに収納場所を確保すると片付けを覚えてくれやすくなります。

子供の友達が遊びに来たときもさっと取り出せますし、お友達と一緒にお片付けもできます。
違う部屋においてしまうと、目につかないからいいか……という甘えが出てしまい、意外とパパとママが片づけに積極的ではなくなってしまうなど悪い影響もあります。
子供がお片付けに積極的になれる場所は、パパやママが積極的に片づける場所とイコールなのです。
おもちゃの量が決まってくると、それを片づけられるだけの収納があれば大丈夫です。
カラーボックスでもいいですし、子供が取り出しやすいような専用の棚でもOKです。
できれば棚や引き出しがいくつかあると、何をどう片づければいいのか考える力もつくので、カゴにぽんぽん投げ込めばOKという収納ではない方がいいと思います。

今まで投げ込み式でよかったのに、何で分けなければいけないの?と理由を聞かれたとき「大きくなったから」では子供にとって納得のできる理由ではないと思うので、お片付けが始まったら傍にいて、一緒に片づけてあげるようにしましょう。
その際、いつ、どんなときにおもちゃを片づけたらいいのかも一緒に教えてあげるといいですね。
私の場合、お昼ご飯の前、お昼寝の前、晩ご飯の前とお風呂に入る前で1日4回のお片付けタイムを決めていました。
そんなに!?と思うかもしれませんが、場所がリビングだったのでお片付けをしないとご飯を気分よく食べられないので、まずは片づけを優先。
それからお昼ご飯を作り始めてキレイなリビングでご飯という意識づけをしていました。
それができてくると、子供はお腹が空いたら自然と片づけるようになりました。
そうすることでお腹が空いたアピールができますし「ママ、おなかすいた」と言葉でも伝えやすくなったと思います。
お風呂の前のお片付けも重要でした。
お風呂から上がってしまうと、すぐ寝てしまう子だったのでリビングがぐっちゃぐちゃだと片付けは全部パパとママの仕事になってしまうので、「お風呂に入るよ」と声をかけたら片づけてくれるようになるまで一緒に片づけるようにしましたよ。
おもちゃの収納、どんなものがよかった?
カラーボックスや引き出しタイプなど、子供用の収納はたくさん売られるようになってきました。
何より、片づける場所に子供が興味を持ってくれ、近づいてくれないと意味がないのでシンプルな部屋作りをしている場合は悩ましいかもしれません。
子供っぽさをなくしたい!と部屋作りをしているパパとママが多いですもんね。
私はむしろその逆で、子供がいるアピールをしていました。
それは家にお客さんが来た時に、子供の通り道を避けて座ってくれたり、子連れなら子供のものがある近くに子供を寄せて、大人が触って欲しくないものは手の届かないところに置くなど、こちらから説明しなくても来客が気づいてくれるからです。
なるべくソファやダイニングの近くに子供のおもちゃは片づけず、リビングの奥、またはテレビの横に子供専用のスペースを作っていました。
私は3段のカラーボックス2つと2段のカラーボックス1つを段違いで組み合わせ、下段には引き出し、上には軽いものを置いて取り出しやすくしてありました。
あえてカーテンなどはつけずに「子供が上手に片づけられます!」というアピールをしていました。

子供も片付けができたときに、お客様から褒めてもらえると子ども自身がとても誇らしげだったので、それでよかったと思っています。
褒めてもらえると子供もお片付けを進んでやるようになります。
また収納スペースがそのくらいで足りたのは、最初におもちゃを選別して子供のお気に入りだけを残したからだと思っています。
あまりにもたくさんあると、きっとそれだけでは足りなかったと思いますが、外で遊ぶことも多く、家の中で遊ぶことに重きを置いたわけではないのでそれで充分でした。
家の中におもちゃが多いと、外で遊ばない子になってしまうかもしれないのでおもちゃは少なくてよかったと思っています。
ちなみに、子供がよく遊んだおもちゃの第1位はボタンを押すと動物が飛び出してくるおもちゃでした。
ただそれだけの単純なものだったのですが、友達の子供2人もお世話になったくらい大人気のおもちゃでした。
その次がやりたい放題。そして、シルバニアファミリーです。
カラーボックスを段違いで組んだのは、2段のカラーボックスの1番上にシルバニアファミリーのお家を置き、下段の引き出しにお人形や小物を片づけていたからです。
子供の身長でも取り出しやすく、片づけやすかったと思っています。
DVDはどうする?
子供のお気に入りはおもちゃに限らず、好きなDVDも含まれますよね。

しまじろうなんかは繰り返し観ていたので、これが観たい!とアピールしやすい場所に置いてありました。
それが、カラーボックスの2段目でした。
奥行きがあるので手を伸ばして取ることになりそうですが、あえて空のティッシュケースを奥に入れ、DVDは背表紙が見やすいように手前に置くようにしていました。
特に繰り返し観ているお気に入りは、表紙が見えるように置くなど工夫してみました。
表紙を見せたいときは、100均で売っている写真立て用の小さなイーゼルが便利でした。
そういう場所を1か所作っておくと、子供が自分で見たい表紙を選んで置き換えたりすることもできるので、子供の好みも理解できました。
奥を使わないのはもったいない、ではなく、無駄なものは持たない、与えないという気持ちの表れだったので、空のティッシュケースを置いた場所が無駄だと思ったことはなかったです。
録画しておいた子供向け番組などは、子供がわかりやすいようにラベルを作ってあげたのですが、1枚のDVDに同じ種類の番組しか入れないように編集しておくと、自分も子供も観たいときの振り返りが楽だったのでその手間は惜しまない方がいいのだなぁと感じました。
私自身がパソコン作業が好きということもありますが、録画した物を編集する時間は意外と楽しい作業でした。
なるべく隙間なく詰めるのではなくて、ある程度の余裕を持たせることで見栄えもよくなりますし、子供も取り出しやすく、片づけやすかったと思います。
子供は遠慮なく手を突っ込みます。加減を覚えないとDVDがバタバタ倒れてしまうので、どうやったら上手に取り出せるかな?と出す~片づけまでの様子を見てあげると子供の成長により気づきがあって面白いです。
いつの間にかDVDを倒さなくなるので、加減を覚えたんだなと思うとほっこりしました。
ちなみにテレビ台にも一応DVD収納はあったのですが、ガラスの扉がついていて自由に開け閉めされることで手をケガされるのが怖かったので、ストッパーをつけ、積極的に利用するのは避けていました。
カラーボックスの上段には、軽いものを
今までの話だと、3段のカラーボックスの最上段である3段目が空いていることになります。
そこに何を置いていたのかというとぬいぐるみなどの軽いものです。
ちょっと取り出しに失敗して上から降って来たとしても、子供がひどい怪我をするようなことがないからです。

うちの子の場合、あまり大きなぬいぐるみを好まず、小さなタイプのものが好きだったのでいくつかあってもスペース的には充分でした。
少し大きくなってから、1体だけ大きなぬいぐるみを購入したのですが、それはあえてカラーボックスにはおかず、子供が手に取りやすい椅子の上に座らせてありました。
子供自身が遊び終わるとそこにそのぬいぐるみを戻しに行っていたので、ぬいぐるみにも指定席があってもいいと思います!
特に、サイズが大きなものならカゴなどに収納せず、ソファに座らせておいたりするとインテリアにもなり部屋の雰囲気が和みますよ。
子供のお絵描き道具はFit’sケースに
子供のおもちゃ、遊び道具として外せないのはお絵描き道具もありますよね。
うちでは全部まとめてFit’sケースに収納していました。
浅型のものを1つ用意しておき、お絵描き帳もぬりえもクレヨンも、おもちゃのせんせいも全部この中でした。
うちの子はお絵描きの道具をあまり持ち運ぶことがなく、実はあまりぬりえをしない子だったので、このFit’sケース1個で足りました。
実際に描いた絵はしばらくとっておき、子供にとっておきたいものと処分していいものを選んでもらっていました。
ケースがそれなりに大きかったこともあり、かなりの冊数のお絵描き帳が保管されていましたが小学校に上がるくらいまで余裕で空きがありました。
小学校入学時に机を買ったため、お絵描きの道具を少しずつ減らしたのですが、Fit’sケースは普通の収納として使えるのでお絵描き道具をしまわなくなった後は服を収納する引き出しにしました。
他にも使いまわしが利くもので片づけられるようにしておくと、子供が大きくなった後も無駄にならなくていいと思います。
Fit’sケースはデザインが変わらないので、買い足すこともできて便利でした。
どこでも取り扱いがあるので、デザインを揃えたいのに揃わない!という悩みはなく済みましたよ。
お出かけの時のお片付けには
子供が小さい頃、田舎暮らしだったこともあり車での移動が中心だったのですが、その際、おもちゃを持ち出すときに重宝したのが大きめの帆布のバッグでした。

雑誌の付録でもいいですし、あまり生地が厚くなく柔らかいものなら購入してもそれほど高くはないはずです。
私の場合、雑誌についてきた帆布のバッグを持ち出し用のおもちゃ箱だと思って活用していたのですが、持ち手があることでかなり重宝しました!
実家に帰るときや、公園に遊びに行く時なども持ち運びが便利かどうかが重要だったのでとってもオススメです。
女の子ということもあり、プラスチックのおもちゃよりもぬいぐるみや絵本が多かったので、持って行きたい物を入れてもらっていました。
最初から「このバッグに入るだけね」と決めておくと、自分で持ち出したいおもちゃをしっかり厳選するようになったので、全部持って行きたい!とかそんな風にごねられることはなかったです。
分量を決めることができるという点でも、子供に許容範囲を教えられてよかったのかもしれないと思っています。
大きくなった今は、荷造りがとっても上手なので小さい頃のこういう経験が活きているのかな?と親バカですが(笑)思います。
お片付けは、子供に厳選させる、許容範囲を教えるいい機会!
子供が可愛くて、ついついおもちゃが増えてしまうお家もあると思うのですが、いつまでも「何でも」が通じるわけではないですよね。
子供と一緒にお片付けしやすい環境を作っていくのであれば、子供が本当に遊びたいものをしっかり選べる環境を作ることを常に意識するといいと思います。
そうすると、遊びのジャンルが決まって来て、持っていたおもちゃの続き(例えば、シルバニアならその系列の物、ブロックなら同じシリーズの他の形が作れるブロックなど)を欲しがるようになっていきます。
子供が集めたいものが決まって来ると、親の買い物もしやすくなりますよね。
そうなるには、片づけた後の使いやすさ、選びやすさが重要かもしれません。
あちこちに色々な物が散らばっていると、子供は部屋の中を右往左往します。
そのうち、集中力が切れてしまいお片付けまで意識が回らなくなってしまうこともあるようです。
そして、どこに何を片づけていいのかわからないという悪循環が発生します。
それを親が未然に防いであげることで、子供はお片付け上手になれます!
まず、最初にお片付けしやすい環境の整備を、お子さんと一緒に工夫してみて下さいね。
パパやママだけで環境を作ってしまうと、子供はやっぱりお部屋の中で迷子になります。子供と一緒に作ることが大切です。
お片付けの場所を決めるときはお子さんが近くにいるときに相談しながら進めてみましょう!