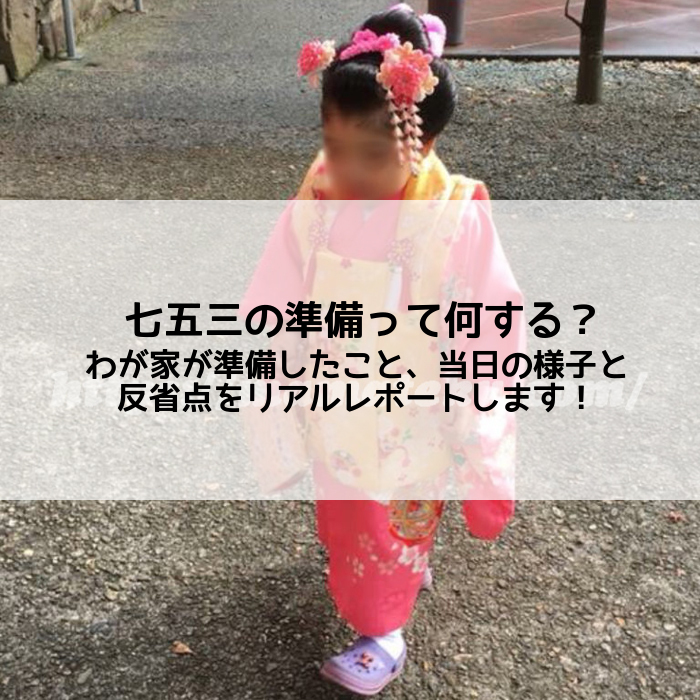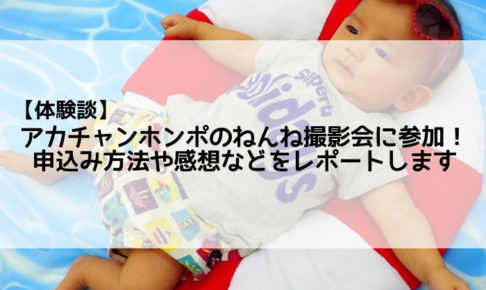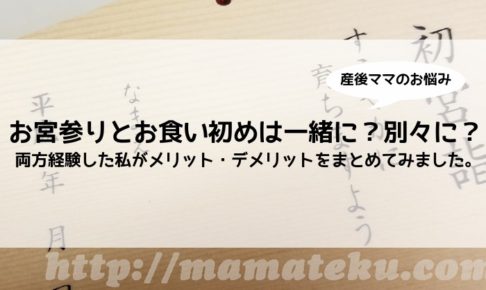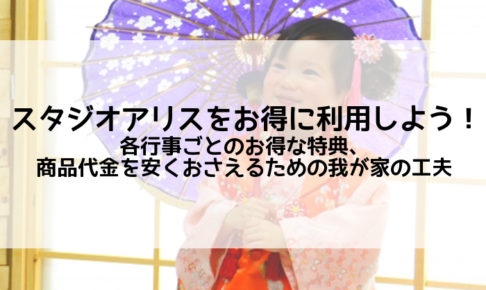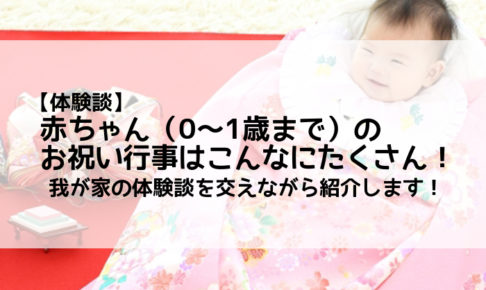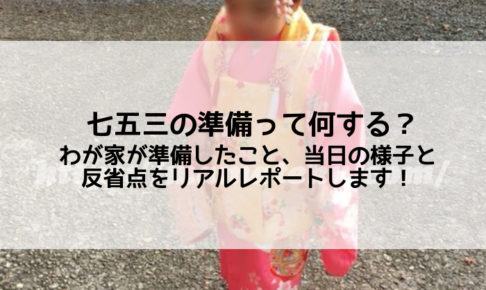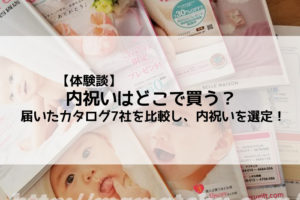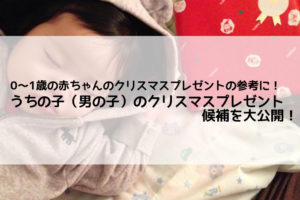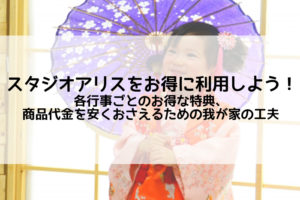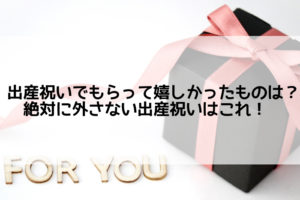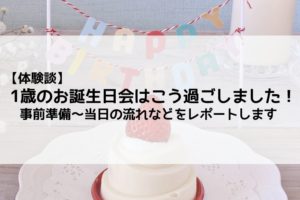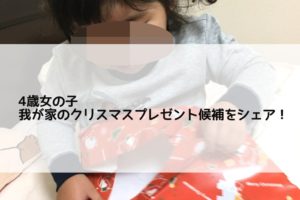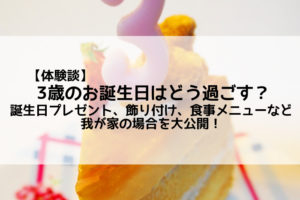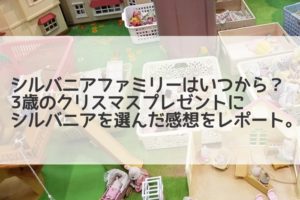ののかママ
最新記事 by ののかママ (全て見る)
- 保育園入園が決まったけど寂しい…。保育園に預けることへの葛藤、私はこう乗り越えました! - 2018年12月31日
- ひらがなの勉強はいつから?我が家の場合と実践している練習法をシェアします! - 2018年12月29日
- 我が家流・イクメンパパの育て方!育児に消極的だった夫を変えた4つのポイントをシェア! - 2018年12月26日
ママテク(@mamateku)ライターのののかママです。
子どもが生まれてから子どもに係る行事はたくさんありますよね。
その都度どんな行事なのか、何をしようか、親として子どもの為にしてあげられることを一生懸命考えてきた私。
そして、そんな行事の中でも私の気合いが一番入っていたのは昨年行った七五三です。
自分の幼いころの写真を見てみても、七五三の着物を着た少し照れたような表情の自分や、いつもは厳しかったけれどとても優しそうな眼差しの父母に、晴れ着を着た私の横で目じりを緩めている祖父母の顔…
七五三は家族にとって幸せな行事の一つなのだなぁと実感していました。
それなので、娘の初めての七五三はどうしても母親としての「健やかに育て」という気持ちをたっぷりとこめて、愛情あふれる一日にしたかったのです。
今回はこれから初めての七五三を迎えるご家庭の為に、我が家の七五三の準備と七五三当日の様子、反省点などをご紹介したいと思います。
パッと読むための目次
七五三ってどんな行事?
それではそもそも七五三はどんな行事なのでしょうか?改めて調べてみました。
七五三の由来は、子どもが無事に3歳になった事をお祝いする行事だそうです。

「3歳になった」と完了形なのは、昔は乳幼児の死亡率がとても高く、3歳まで育つということ自体がとても喜ばしいことであったことが所以だそうです。
- 3歳の男女が髪の毛を伸ばし始める「髪置き」
- 5歳男児が初めて袴をつける「袴着」
- 7歳女児が初めて帯を使い始める「帯解き」
というお祝いがベースになっているといわれています。
江戸時代中期になると、霜月祭の日(11月15日)に神社に着飾ってお参りすると言う形態に代り、最初は武家や裕福な商人に広まり、その後明治以降には庶民にも広がって行ったのだそう。
【スポンサードサーチ】
現代では、子どもが「3歳になった」「5歳になった」「7歳になった」という感謝の気持ちを神様に伝えるとともに、これからの成長を祈る行事として定着しており、晴れ着を着て神社に参拝に行くことが一般的な七五三の行事であると認識されています。
七五三、数え年にするか満年齢にするか
さぁ七五三…と思った際に、我が家で悩んだのが数え年に行うか、満年齢で行うか、ということでした。
周りのママ友に聞いてみてもその意見は千差万別で、数え年でやったというご家庭もあれば満年齢でやったと言うご家庭もあり、中には上の子がいる場合は一緒にやってしまいたかったから上の子は満年齢だけど下の子は数え歳…なんていうご家庭もあって、それぞれの家庭で決めているという意見が私の周りでは圧倒的に多かったです。
我が家の場合も、私と夫それぞれの両親に相談し、さらに私が毎朝ウォーキングで通る神社で宮司さんに相談して、「どちらでも良いと思う」というご意見を頂けたので我が家の場合は満年齢で行うことにしました。
今思えば、満年齢であっても娘がじっとしていられなかったり、スタジオでの写真撮影を怖がって表情が固かったり、ということがあったので、結果的には満年齢で良かったかなと思っています。
きっとこれが1年前だったらもっとじっとしていてくれなかったと思いますし、写真撮影で泣くと言うことも想像できたからです。
また、1年待って良かった…という理由はもう一つあって、それは娘の髪の毛です。

どうしても日本髪を結わせたかったので、友人の美容師さんに相談したところ、肩に着くくらいの髪の長さがあるとベストということで、1年間髪の毛を伸ばすための猶予があることはとてもありがたかったです。
七五三の準備って何するの?
初めての七五三、ということで私が準備したことは下記のとおりです。
①娘の髪の毛を伸ばす
どうしても日本髪での七五三にしたかったため、早い段階で美容師の友人に相談し、娘の髪の毛を切らずに1年間過ごしました。
おでこもあげたかったので前髪も目に入らないギリギリのところでキープしました。
②写真館の予約を入れる
七五三に向けて、私が真っ先にしたのが「写真館の予約をいれる」ということでした。
我が家の場合は、前撮りなどはせずに、写真撮影を七五三のお参りを同日に行うという予定を立てました。
何故同じ日にしたかったかと言うと、着付けとヘアセットは写真館で行って貰えばそのままお参りが出来て、3歳の落ち着きのない子供に何度も着付けやヘアセットをさせると言う手間が省けると思ったからです。

そのため、写真館の予約が取れるかということが一番のハードルで、激戦の日の11月15日は予約が取れず、結果的にそのあとの週の土曜日に七五三を行うことが決まりました。
七五三の日程が決まると、双方の両親に連絡をしてその日を開けて貰い、両家のおじいちゃんおばあちゃんも一緒にお祝いをして貰うことになりました。
③手作りのかんざし作り
七五三の日程が決まると、逆算式に準備をすることを少しずつ洗い出して手を付けて行きました。
私は普段仕事をしているため、準備にさける時間は限られています。
私の子育てのポリシーで、普段は厳しく怒っていても、こういう行事では「お母さんはあなたのことが大好き」という気持ちを思う存分こめたいと思っているため、今回の七五三でもその気持ちを込められる場所をじっくりと考えました。
そして思いついたのが、「どうしても日本髪にしたい」という気持ちがあったため、その日本髪を飾るかんざしを手作りする、ということ。
インターネットでかんざしの作り方を調べ、その中からつまみ細でのかんざしを手作りする事にしました。

とはいっても、今までつまみ細工なんてしたことが無かったですし、存在すら頭にありませんでした。
しかし、いかにも「お母さんの手作り」と言うような出来にはしたくなかったので、思い立ったその日から練習を開始。
かんざしを作ろうと思い立ったその日は5月。
育児の合間や会社での休憩時間、出張で一人の夜を過ごす時間に黙々と練習を重ね、何度も試作品を作成して、11月の七五三の時までに形になるものを作り上げることが出来ました。
結構大変な作業でしたが、娘も喜んでくれて、何よりもそれが嬉しかったです。
④産着の仕立て直し
今回の3歳の七五三で娘が着た着物は、実はお宮参りの際に私の両親からプレゼントされたものでした。
両親がうちの娘にはピンクが似合う…と色んなお店やインターネットで似合いそうな色を探して、沢山の産着の中から選んでくれた思い入れのある着物です。
そのため、お宮参りのころから、3歳の七五三でもこの着物を着せると決めていたのです。
しかし、産着をそのまま七五三で着せることは出来ないので、仕立て直しをする必要がありました。
仕立て直しについては、専門の業者さんも有るようでしたが、つまみ細工の練習で散財(!?)していたこともあって、費用は抑えたかった、「どうせ被布を着せてしまえば細かいところを見ることはないだろう…」と思い、仕立て直しも自分で行うことにしました。
仕立て直しの仕方はインターネットを参考にしました。
https://kimono.support/shichigosan-preparation/
まち針を打つ作業こそ難しかったものの、それ以外はそこまで難しい作業ではなかったように思います。
これから七五三に向けて着物を仕立て直そうと思っている場合は、早い段階で出来るかどうか一度やってみて駄目なら専門の業者に頼むことも選択肢としては有りだと思います。
とはいえ、この仕立て直しには1点反省点があります。
それは、仕立て直しを行ったタイミングです。
私は、この仕立て直しを夏の終わり頃に行ったのですが、そこから11月の下旬までの間の娘の成長を甘く見ていました。
夏の終わり頃にはちょうどいいくらいの丈だった着物が、七五三の時に着せてみると少し短くなっていて、出来ればもう少しギリギリに行うか多少の成長を早めに予測していれば良かったなぁと思いました。
私は今回生まれて初めて仕立て直しを行ったのですが、写真館で話を聞くと、結構な確率で仕立て直しをしていない産着をそのまま持って来てしまうご家庭が多いとの事です。
仕立て直しをしていない着物を持って来られても、着物の仕様が完全に違うので着付けをすることが出来ないと言うことなのでお気を付け下さい。
また、女の子の着物は被布を着るので産着でも華やかさは残りますが、背中の柄は見えなくなります。
そして、5歳の男の子の場合は着物の上に袴を着るので柄が寂しくなってしまうとのことです。
我が家の場合は私の両親からのプレゼントということもあって思い入れがありどうしても産着を着せたかったのですが、そこまで思い入れが無ければ産着ではなくレンタルなどでも手間がかからず良いのではないかと思います。
⑤小物類の購入
かんざしは自作することしたものの、その他の小物類は和服店に行ったり、インターネットでよさそうなものを見つけて購入しました。
今回の七五三で私が購入したのは、下記のとおりです。
- 被布
着物の上に着せるコートのようなものです。着物と同系色でそろえる方が多いみたいですが、我が家は着物がピンクなので、ピンクと相性の良い黄色のものを選びました。 - 半襟
下着に縫い付ける衿です。この一部を見せるのが正式だと聞いたので、見える部分に刺繍があるものを選びました。着物と襦袢を仕立て直す際に一緒に付けました。 - 足袋
- 草履
草履はかわいいものが見つかったためかなり早い段階で購入しましたが、早めに購入したのが大失敗でした。
なぜかというと、七五三の2週間くらい前に履かせてみたところ、とてもきつくて歩ける状態ではなかったのです。
そのため、写真を撮るときだけ草履を履かせて神社を歩くときにはいつも履いているゴムサンダルで代用しなくてはなりませんでした。 - かのこ
日本髪に結うときに使う後髪用の飾りです。 - バッグ
草履に合う色合いのものを探して購入しました。
今回の購入品を見て思ったのは、サイズが変わるようなものはぎりぎりに買ったほうがよいということです。
もちろん大き目のものを買ったのですが、子どもの成長こそ先が読めないものであると今回の体験をもとに実感しました。
購入品に関してはこまごまとしていて買い忘れなどが発生しないかひやひやしていましたが、一つ一つを選ぶ作業はとても楽しかったです。
時には娘と相談しながらどれにしようかと決めました。
⑥お参りの後の食事会の場所探し
七五三には双方の両親がそろうということで、お参りの後の食事会を開くことに。
その食事会の場所を探し、お祝い膳を予約しておきました。

ちょうどお日柄の良い日だったために、近隣のレストランは会食などの予約でいっぱい。
やはり早め早めの対策が必要だなと感じました。
⑦私の着物の手配
今回は娘の晴れの日ということもあって、私自身も着物を着ることにしました。
とはいえ、着物は持っていないので、レンタルでの手配となりました。

レンタル予定日を11月とすると、同じように七五三用のレンタルで注文が多く入っているようで、なかなか好みの着物を選ぶことが出来ませんでした。
いくつかのレンタル会社のホームページをくまなくチェックして、娘の被布と同じ黄色の着物をチョイス。

心が折れそうになりながらも結局行きついたのはYou tube。
当日は実母とYou tubeでの着付け講座を見ながら着物の着付けを行いました。
もしも、お子さんの七五三で自分も着物を着たいと思っている場合は、着物の手配も着付けの予約も早い段階で抑えておくことをお勧めします。
私の場合、何とかYou tubeでの着付けはできたものの、自分でやったことで予想以上に時間がかかってしまい、着付けや髪の毛のセットに化粧でてんやわんやで娘の着付けの受付に間に合いませんでした。
娘は夫に連れて行ってもらって私は後から追いかけるという形になり、娘のお支度の様子を最初から見ることが出来ませんでした。
せっかくのお支度だったのでできれば最初から見たかったです。とても残念でした。
⑧着物を預ける
娘の着物は持込みだったため、写真館でチェックさせてほしいといわれ、実際の七五三の1週間前に着物や小物を一式写真館に預けに行きました。
なぜ預けなければいけなかったのかというと、着付けの為に必要な仕立てなどがきちんとなされているかどうか、小物がそろっているかを写真館で確認したいからとのことでした。
写真館のことは信頼していたものの、当日に小物がない…渡した・渡してないというトラブルなどということがないように、事前に預けるものはリストアップしておいて、念のため携帯で写メもとっておきました。
⑨娘の気持ちを高める
お祝いであるということを認識してもらうため、また祈祷など慣れないことがあるので、娘にはかなり早い段階から七五三のお祝いがあるよということを逐一伝えていました。
たまたま祈祷をお願いする神社も近かったので、その神社の近くを通るたびにお祈りしてもらうんだよと言い聞かせ、きれいな着物着ることができるね、お化粧もしてもらえるね、お姫様みたいだね、と毎回伝えていました。
七五三当日の流れ
今回の七五三では、着付け・写真撮影を行った後に祈祷。祈祷が終わったら家に帰り着替えをしてから昼食というスケジュールを組んでいました。
一番の懸念事項はやはり主役の娘。

まだ3歳ということもあって、朝からのみっちりしたスケジュールに娘の集中力が持つか、慣れないことをやらせるので大丈夫か、途中で飽きてしまったり眠くて愚図るのではないかということがとても心配でした。
①着付け
娘の着付けは写真館で行ってもらいましたが、先程も書いた通り、母親である私は自分の着付けに手間取って大失敗…。
美容スタッフの方に、髪型や化粧などのリクエストをしなければいけないのに間に合わず、先に娘を連れて行った夫から逐一確認の電話が来る始末。

娘はこの時、少し緊張した面持ちで鏡の前に座っていたそうです。
ここは母親の出番だったので、もう少し段取りをしっかりしておけばよかったと思いました。
②写真撮影
一人でカメラの前に立ち、カメラマンに言われたポーズをとることに娘の顔ががちがちになっていました。
泣かれてせっかくのお化粧が取れなかっただけよかったのですが、あまりにも娘が緊張しているので、夫の提案でまずは家族写真からとってもらうことにして、私と夫とで気持ちを和ませ表情を柔らかくさせました。

今回頼んだ写真館はチェーン店ではなく昔からある町の写真館。
午前中貸切にしてもらえたので融通を効かせてもらえてよかったです。
この時念のため持って行っていたウサギのぬいぐるみと、お菓子(手や服が汚れないようにグミ)が大活躍でした。
③祈祷
神社の祈祷の受付を終えて祈祷を待っている間、娘はすっかり疲れてしまい、抱っこして、おんぶして、歩きたくない、もう飽きたと大騒ぎ。
祈祷のときには「千歳あめがもらえるよ」と食べ物でつって落ち着いたものの、3歳児との祈祷はもっとしっかりと対策しておくべきだったと少し後悔しました。
④食事会
娘のお祝いなのに、主役は食事会の会場に着くまでにうとうとし始めて、食事の間ほとんど寝ていました。
やはり朝から慣れないことをしたためにとてもくたびれてしまったようです。
もう少し時間に余裕をもって休む時間を挟んだスケジュールのほうがよかったかなと思いました。
まとめ
大事な娘の七五三ということもあってかなり張り切って準備をしていた分、七五三が終わった後は糸が切れてしまった私です。
一生懸命いろいろ考えてはいたのですが、反省点もとても多い七五三だったのでこの経験は7歳の時に生かしたいと思います。
これから初めての七五三を迎えるご家庭もたくさんいらっしゃるかと思いますが、どうか悔いのないように楽しんで準備をしてください。
良い七五三になりますように!