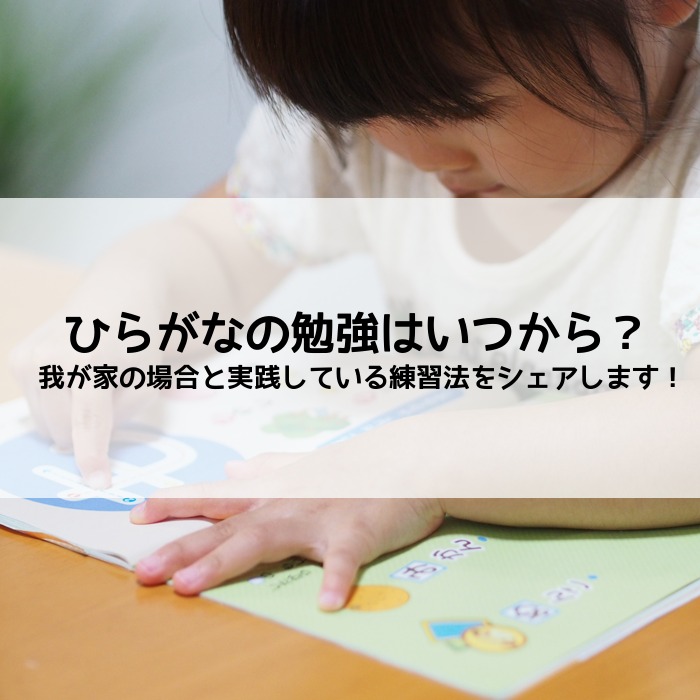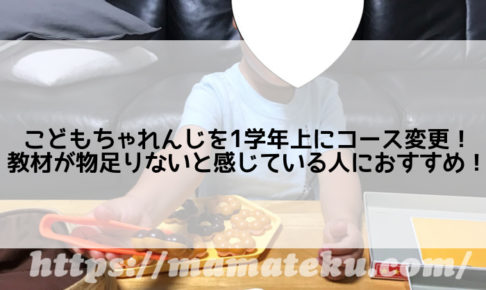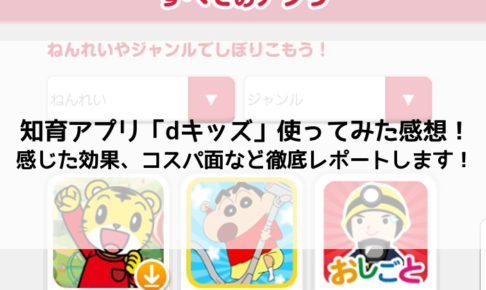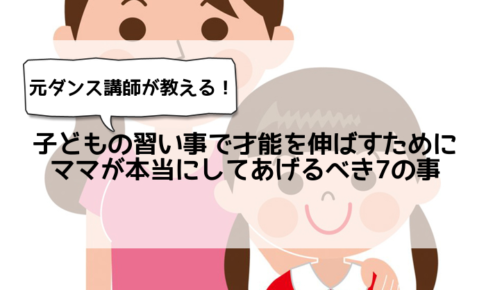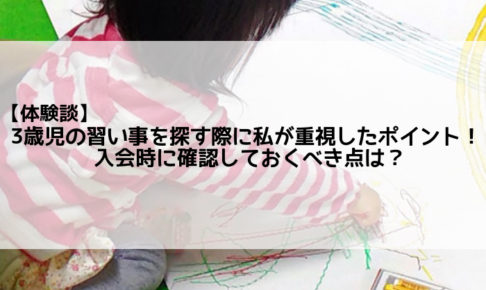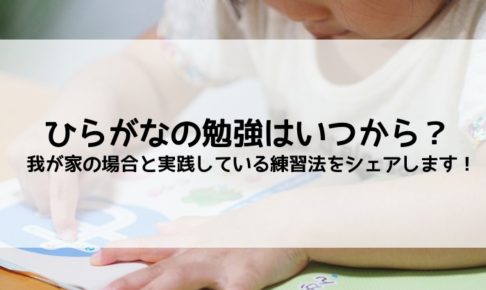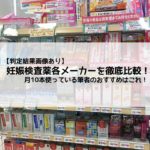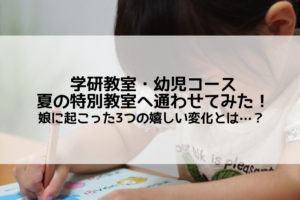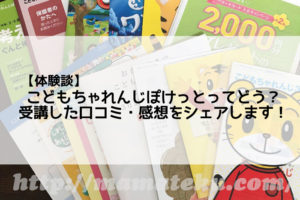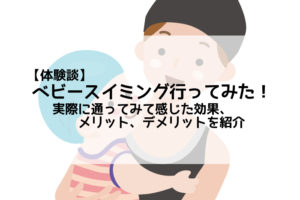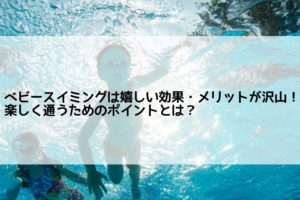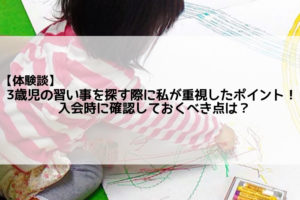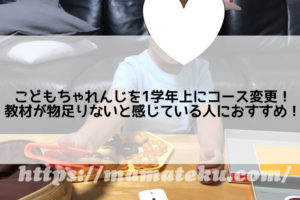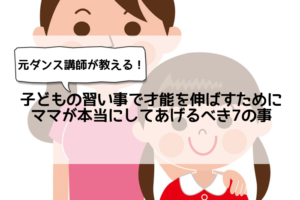ののかママ
最新記事 by ののかママ (全て見る)
- 保育園入園が決まったけど寂しい…。保育園に預けることへの葛藤、私はこう乗り越えました! - 2018年12月31日
- ひらがなの勉強はいつから?我が家の場合と実践している練習法をシェアします! - 2018年12月29日
- 我が家流・イクメンパパの育て方!育児に消極的だった夫を変えた4つのポイントをシェア! - 2018年12月26日
ママテク(@mamateku)ライターのののかママです。
うちの4歳の娘は絵本が大好きです。
眠る前の絵本タイムは私たち親子には欠かせないコミュニケーションタイムですし、本人が暇だと思うときには必ず「絵本を読んで」と持ってきます。
そんな娘ですが、最近は絵本を自分で読んでいることも増えてきました。
とはいえ、まだ4歳。
「読む」と言っても、絵本に書かれていることを覚えていて、絵を見ながら暗唱しているか、絵から物語を空想して自分なりに話を創造しているだけです。
しかし、そんな娘流の本読みもだんだんと物足りなくなってきた様子…。
最近になって、自分で「字を読んでみたい」だとか「おばあちゃんにお手紙を書いてみたい」と言うようになりました。
我が家では私も夫も勉強が好きではなかったため、基本的に子どもには無理強いさせないようにしようと言う方針です。
しかし、興味を持ち始めたことは娘が納得するまで応援はしてあげたいなと思っています。
正直なところ「字の勉強に関してはまだまだ先でいいかな?」とは思っていたのですが、そんなわけで少しだけひらがなの勉強を始めてみました。
今、ひらがなの勉強を始めてみようか…と考えているご家庭もいらっしゃると思います。
【スポンサードサーチ】
今日は現在取り組んでいるひらがなの学習方法をご紹介したいと思います。
パッと読むための目次
ひらがなの勉強に二の足を踏んでいた理由
我が家は私も夫も大卒ですが、勉強は大嫌いで育ちました。
小・中・高・大学と、普通くらいの成績を行ったり来たり…。
苦手科目で落ちこぼれたことも、勉強に挫折感を味わったこともしょっちゅうでした。

私はといえば学校自体も大嫌いで、あと何日行けば休みと毎日指折り数えていたほど。
学校や勉強が楽しいと思ったのは大学に入ってからで、かなり遅咲きです。
正直なところ、子どもの頃もっと勉強しておけば良かった…とかなり悔みました。
そんな私たち夫婦。
通常であれば、自分たちの経験を反面教師に子どもにはしっかりさせるべきなのでしょうが、子どもが出来たとき決めたのは『勉強は本人次第、無理強いしないようにしよう』ということ。
親が出来るのはたくさんの興味をばらまいてあげるだけで、その中で娘が拾うものがあればそれを伸ばしてあげればいい。
勉強が出来なくても、人を思いやることができて、何か一つでも胸を張れるものがあればいいという考え方です。
しかし、本人が勉強したい気持ちがあるならその気持ちは応援してあげたいと思います
現在我が家の娘は4歳になったばかり。
勉強は小学校から、ひらがなは小学校で学ぶものと考えれば、まだまだ早いかな?という気がしていた私です。
というのも、我が家が幼児期の今力を入れたいのは、ひらがなの読み書きよりも、遊ぶことやお友達とたくさん触れ合うこと。
そして色んな興味の種を心の中に植え付けてあげたいなと思っているからです。

もちろん勉強は出来た方が良いとは思うので、この「まだ早い」という考えが正しいかどうかは分かりません。
仮に正しかったとしても、我が家の娘以外の子に当てはまるとは思いません。
子どもたち一人一人がもともと持っている性格や親御さんが子どもに期待すること、それは皆異なるので、我が家流の考えが絶対に正しいとは思わないですし、違う考えを持った人がいたとしても我が家の教育方針は変わりません。
そして、そんなたくさんの考えがあるという前提の中で、我が家が4歳の娘に今のぞむことは、
時には泥だらけになって泥や水の感触を楽しんだり、
自然に触れて季節を感じ取ったり、虫を捕まえて観察したり、
色んな事に興味を持って、全身で遊ぶ力を育むこと。
そして、お友達と楽しく遊んだり喧嘩をしたりするなかで、周りのお友達を大好きになって欲しいと思っています。
正直なところ、ひらがなの読み書きは今やらなくてもいずれ出来るようになると思います。
しかし、遊びやお友達との関係は、幼児の今学ぶことに意味があるように思います。
時間は有限なので、同じ時間を使うならば、ひらがなよりも学んで欲しいものがある。
そのため二の足を踏んでいたひらがなの勉強でしたが、思っていたより早く娘が文字に興味を持ったため、ひらがなの勉強だけは試しに始めてみることにしました。
ひらがなの勉強は何歳から?
それでは、そもそもひらがなを勉強しはじめるには何歳からが良いのでしょうか。
ひらがなを学習し始める年齢について調べてみたところ、早い子では0歳から。
早期教育の教材などを見ても、対象年齢が0歳となっていたりします。
しかし実際に言葉を覚えていく中で、0~2歳で「これがひらがな…」というような認識が出来る子どもはほとんどいないに等しく、全体的に見れば遅くても小学校に入る前には読むことが出来る子が多いようです。
上の子が小学校に通っている娘のお友達のお母さん達にも聞いてみたところ、私の住む地域では「だいたいの子どもたちは小学校就学までにひらがなは書けなくても読める状態」であるとのこと。
それでも小学校の授業ではひらがなを覚えることから始まるため、読めない・かけない子もある程度いるそうです。
インターネットでも調べてみましたが、適齢年齢は「ひらがなに興味を持ったとき」と書かれていることがとても多かったです。

子どもの許容量や集中力などはとても少なく、無理に詰め込みをしてしまってもかえってそれがストレスになってしまう。
興味がないことをストレスを抱えながら勉強するよりは、興味を持った時に興味を引き出してあげる学習方法のほうが、子どもへの負担が少ないということのようです。
つまり、「何歳から」という年齢による線引きではなく、文字を読むことや書くことへの興味があるかどうか、というところで線引きをしたほうが良いようです。
我が家の場合を考えてみると、「興味を持っている」ということではひらがな学習を始めるための準備はそろっているように思います。
しかし、今回私が腰を上げるのが重かった理由にはもう一つ理由がありました。
それは「読む」ことは問題なくても、「書く」ためには〇△□などの記号をしっかりかけるようになってからのほうが良いのではないかな?と思っていたからです。
我が家の娘は絵を描くことも大好きなので、ほぼ毎日何かしらのお絵かきを行っています。
彼女の絵をじっくり観察しているのですが、鉛筆やクレヨンの持ち方はほぼ問題ないように思うものの、〇はゆがんでいるし、直線を書かせようとしていても線はゆらゆらしているし、文字を書かせるにはまだまだ頼りないように思ったのです。
今回、娘が「おばあちゃんにお手紙を書きたい」と言っていたこともあって、まず覚えさせるのは自分の名前かなと思ったのですが、娘の名前は〇をきれいに書けないと難しいのではないかという文字が入っていることもあって、どうやって進めたらよいものかと少し頭を悩ませました。
ひらがなの勉強を始めるにあたって決めた5つのこと
「文字に興味がある」ということと、鉛筆はかろうじてしっかり持てるということもあって、試しにひらがなの勉強を始めてみようと思った我が家。
ですが、小学校に上がるまではまだ時間もあるので、正直なところは焦っていません。
しかし、親が一生懸命になってしまうほどに、だんだんと強引になってしまうような気もするので、下記のことを最初に決めておくことにしました。
①まずは簡単な目標を決める
ひらがなを全部読めなくても、一定数読めればOKと最初に割り切っています。
また、おばあちゃんにお手紙を書くことに関しても、最終的に名前が書けることがとりあえず現時点での目標としています。
②興味を失わせないように気を付ける
せっかく勉強を始めても、飽きてしまったり興味がなくなってしまったら元も子もありません。
今まで同様に絵本を読みきかせ、親が文字を書くところを見せたり、外を歩いていて娘の名前に含まれる文字を見つけたら「あっ、この字は〇ちゃんの名前の〇っていう字だね」と意識的に声をかけています。
③完全ではなくてもゆったり構える
自己流で名前を書いてくることなどもあって、全然読めないこともあるのですが、一々間違いを指摘せず、

④無理強いはしない
今日は疲れてそうだなとかあまりやる気がなさそうだなと思ったときは、別のことに切り替えて一緒に遊びます。
⑤学習は10分が限度。必ず親が付き添う
今回ひらがなの勉強をしようと思ったときに、これはいいチャンスと思ったことは「机の前に座らせる癖をつける」ということです。
今まで、絵を描く時でも床で書いたりリビングのローテーブルで書いていた娘ですが、出来れば勉強や文字を書く時には机に座って行って欲しいと思っていました。
机と言っても我が家のリビングのカウンターなのですが、ひらがなの勉強は必ず椅子に座って正しい姿勢で行わせたいと思っています。
また、娘がひらがなの学習帳をやるときにはひとりでやらせず、隣で私か夫のどちらかが座って見守ることにしました。

娘が飽きてしまった場合は、お絵かきや折り紙をしたり、絵本を読み聞かせて10分は過ぎてしまうのですが、普段は保育園に行っていて、じっくり向き合う時間も限られているからか、一緒に座ることでその時間を「楽しい」と思ってくれているようです。
なぜ、最初にこういった決めごとを作っておいたかというと、娘の中でせっかく芽生えた興味も、つまらないと思わせてしまうとやる気があっという間になくなってしまうのではないかと思ったからです。
これくらいの年齢の子どもは興味を持ちやすく、吸収力も抜群な年齢です。
とはいっても、その反面で一度つまらない・苦痛と思わせてしまうと、その「つまらない」という意識だけが残ってしまい、後々本当に勉強をしなければいけない時期にそのトラウマが残ってしまうような気がして、無理強いはとても危険な気がしています。
そのため、今の段階では勉強というより遊びの延長線上という扱いで、ゆったりと構えていたいと思います。
我が家のひらがな勉強の進め方
それでは、我が家が勉強として進めている具体的な方法をご紹介したいと思います。
①お風呂場のひらがなシートで当てっこゲーム
ひらがなの勉強を始めようと思った時点で、100円ショップでお風呂用のひらがなシートを購入しました。
最近では一緒にお風呂に入りながら、文字当てゲームを行うのが定番で、もともと持っていたお風呂の壁に貼るあんぱんまんのおもちゃと併用してゲームを出し合いっこしています。
- 「今から言う言葉をひらがなシートから見つけてね」とクイズを出す(例:くま)
- あんぱんまんのおもちゃを該当する文字の上に貼らせる(「く」の上と「ま」の上にあんぱんまんを置いていかせる)
単純な遊びなのですが、単純だから楽しいのか、お風呂にゆったり漬かりながら遊んでいます。
②ひらがな学習帳・知育ドリルで勉強
ひらがな学習帳を1冊買って、毎日1~2ページずつ進めています。
直線を書く練習・〇を書く練習がメインのものを選んで、時間を決めて線をしっかり書く練習をメインにしています。
しかし、文字を書かないと線だけでは飽きてしまうので、自分の名前はドリルとは別に毎日練習させています。
③移動中はスマホのアプリでゲーム
我が家は基本的に「大人のものは子どもに触らせない」ことを家庭内ルールとしているのですが、電車での移動中など静かにさせたいときには、最近ひらがな勉強のアプリだけは許すようになりました。
今興味のあるひらがなを勉強できるだけではなく、普段は決して触れることが許されていない大人のスマホを触れるという特別感も加わって、静かにしてほしい場所で静かにしてくれるというメリット付きで、娘と電車に乗るときは重宝しています。
現時点、我が家で取り入れているのは上記の3つだけです。
もう少し年齢が上がって小学校を前にしてみたら、もう少し本格的にいろいろなものを試してみたいと思います。
また、字の勉強というほどのものではないのですが、ひらがなの勉強を始めてから娘が読んでと持ってくる絵本があります。
題名の通り絵がないのですが、絵のない代わりに大小の文字がたくさん羅列してあって、覚えたての文字や自分の名前につかわれている文字を見つけるのが楽しいようです。
もともと好きな絵本ではありましたが、ひらがなを勉強し始めてから読んでとよくせがまれる絵本です。
ひらがな勉強を始めてからの娘の変化
ひらがなの勉強を始めてから、少しずつ娘にも変化が見えてきましたのでご紹介したいと思います。
まず、文字への興味が今まで以上に強くなっています。
絵本を読んでいるときや、街の中の表示など、自分の名前につかわれている文字を見つけると「〇ちゃんの名前の〇!」だとか「りんごのり!」と教えてくれます。
今まで興味を示すことなく流していた文字が、自分の暮らしの周りにたくさんあるという発見を楽しんでいるようです。
そして、おばあちゃんとの文通が始まりました。

まだ絵と、その端に自分の名前風の象形文字のようなものを書いているだけなのですが、日増しにそのクオリティは上がってきているように思います。
おばあちゃんも手紙が来ることを楽しみにしているようで、返信をくれるので、ポストに手紙があるかどうかをチェックすることが娘の日課になりました。
最近では『手紙を書いて、切手を貼って出して、郵便ポストに入れて返信が戻ってくる』という流れがとても楽しいようです。
ただ文字を書くということだけではなく、ひらがなの勉強をすることで、色んなことへの興味に波及していることは私にとっても発見でした。
また、一番大きな変化は、私や夫と毎日10分程度並んで勉強する時間をとても心待ちにしていることです。
忙しい毎日だと、なかなか娘とじっくり向き合う時間が取れないのですが、「ママやパパと一緒に机に向かう」ということ自体が楽しいようで、お勉強したいとせがまれることが増えてきました。
ひらがなの勉強に便乗して、ただ単に机の前に座るという習慣がつけばいいなという軽い気持ちでした。
しかし、一緒に机に座ることを楽しいと思うことで、勉強も楽しいと思っているのなら、それだけでひらがなの勉強を始めてみても無駄ではなかったなと思います。
まとめ
娘がひらがなの勉強を始めてからまだ1か月ちょっとしかたっていないものの、意外と変化が増えてきたように思います。
「まだまだ4歳でひらがなは早いかな…」と思っていましたが、ひらがなの習得よりも、そういった変化や娘の成長自体は決して無駄ではないと思う今日この頃です。
ゆったりと構え長い目で見て、その変化を見守っていきたいと思います。