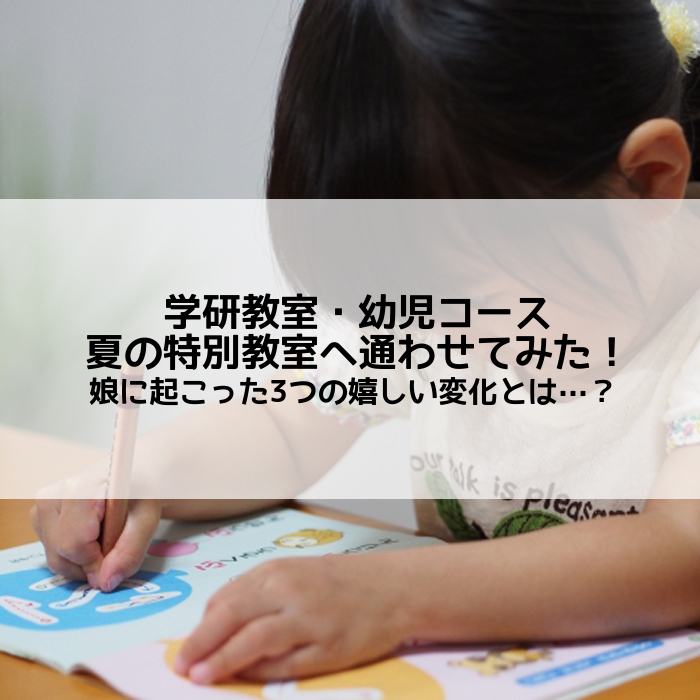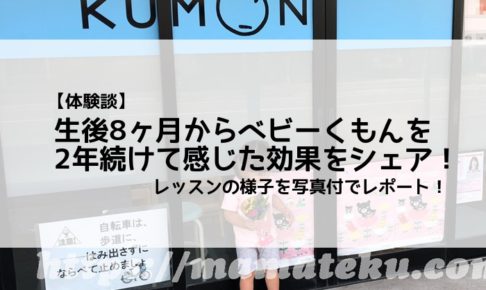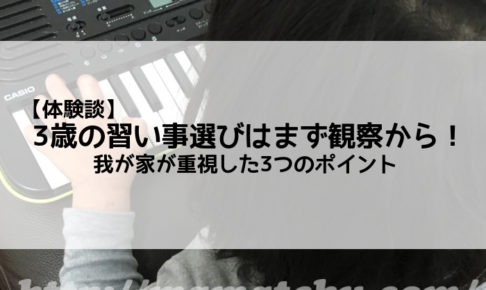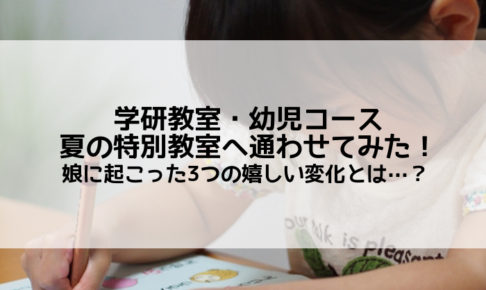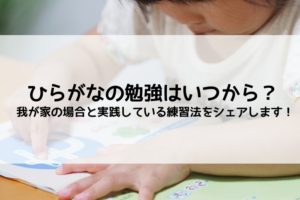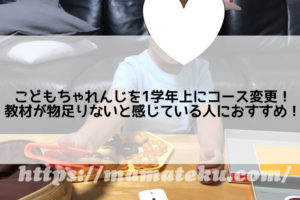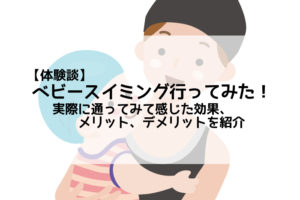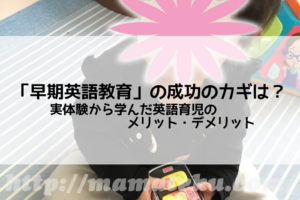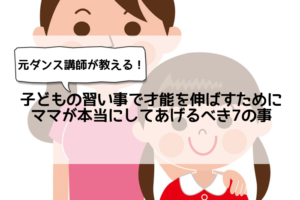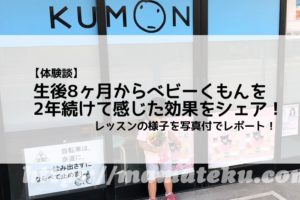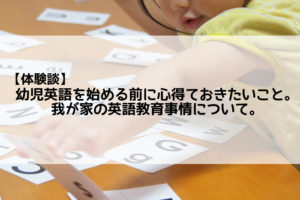あっこちゃん
最新記事 by あっこちゃん (全て見る)
- 子供のお絵かきデビュー!なるべく安全に、汚さないために工夫していることをシェア! - 2019年3月6日
- 手づかみ食べのストレスを軽減できるメニューはこれ!ママも赤ちゃんも楽しくなるレシピを紹介! - 2019年2月17日
- 世代を超えて親子でハマった!50周年を迎えたリカちゃん人形の世界が凄い! - 2019年2月1日
ママテク(@mamateku)ライターのあっこちゃんです。
小学校に上がる前に勉強をさせるべきか、させる場合はいつから何をすべきか悩ましいですよね。
我が家では、年中の長女の夏休みを有意義なものにすべく、この夏、学研教室で開催している「夏の特別教室」に通わせてみました。
夏休みの時間を持て余さないように…という目的で通い始めましたが、実際に行かせてみることで様々な発見があり、今後どんな風に学ばせていきたいか、少しずつ考えが定まってきました。
今回は、年中の長女を「学研の夏の特別教室」に行かせてみた体験談と、その後の入会に関してご紹介していきます。
未就学児の勉強について悩んでいる方に参考にして頂けたら嬉しいです。
パッと読むための目次
学研の夏の特別教室への申し込み~学習スタートまでの流れ
①ネット申込後教室から連絡が来る
夏休みの前、年中の長女を「学研の夏の特別教室」に通わせてみようと思い、まず学研のホームページを覗いてみました。
学研のホームページでは、近くの教室を検索することができます。通えそうな教室を見つけたら次に申し込みです。

学研のホームページの応募フォームから申し込みをすると、指定した教室から電話で連絡が来ました。
電話口で簡単に学習状況をお話しし、訪問日程を決め、約束の日に子供と一緒に教室に足を運びました。
うちの子が選んだ学研教室は、先生が自宅のリビングで開いている教室でした。
②学習診断テストを受ける
最初に教室に足を運ぶと学習診断テストを受けることになります。
このテストは現時点の学力を把握して、どのレベルからスタートするかを判断するためのものです。
【スポンサードサーチ】
勉強と言う勉強をしたことがない娘にいきなりテストを受けさせるのはかわいそうな気もしたのですが、全くできないのであればそれで良いとのこと。
娘はテストの問題文も読めない状態だったのですが、先生に読んでもらいながら受けていました。
娘は、今まで集中して机に向かう経験をしたことがなかったので、黙って答えを紙に書くという作業にかなり苦戦…。勉強をさせる大変さを感じました。
③レベルが決定し学習スタート
テストの結果を受け、学習をスタートさせるレベルを決定しました。
「夏の特別教室」は4回コースと8回コースがあったのですが、まずはお試しという気持ちで我が家は4回コースを選びました。
ちなみに学研教室は「無学年方式」なので、年中だから、年少だからという理由で教材を選びません。
同じ教室に通う年長さんの中には、すでに小学校に上がってから学ぶ内容を先取りしている子もいました。
まだ理解できていないのに先に進んでしまったりせず、個々のペースで学べるのは安心感がありますね。
学研教室では何を学ぶ?学習内容や宿題について
幼児は「かず」・「ちえ」・「もじ」
学研で幼児が学ぶ教材は「さんすう」と「こくご」です。
実際に学研の教材を見てみると、絵を見て線で結んだり、まるで囲ったり、色塗りをしたりと、子供たちが遊び感覚でできる内容だと感じられました。

簡単そうに見えますが、数の意味を理解したり、豊かな語彙力を育めるように考えられているのだそうです。
ただ文字や数字を覚えるのではなく『考える力を育成するために作られた教材』とのことで、やらせながら、今後勉強することに楽しみを見出してくれたらという期待を抱けました。
集中タイムは45分間
学研教室に送り届けると、毎回45分後にお迎えに行くことになります。

テストを受けた時に、おしゃべりをせずにじっと座っていられなかった娘が45分間持つのかどうかとても心配だったのですが、毎回迎えに行くと同じ席に座っているので、親がいない状況でも何とかやっているようでした。
余談ですが、学研教室だけに限らず、幼児の場合は送迎が必要になります。
娘が通う学研教室は、家から自転車で5分ほどのところにあるので、送り届けて家に帰り、迎えに行くとなると家にいる時間は30分ちょっと。
これがなかなか中途半端な時間なので、学研の日はこの30分を買い物の時間に充てるなど、毎回無駄にしないように工夫しています。
教室と自宅の距離によって、自宅に帰るのが微妙な場合もあるかと思います。
学研に通わせるか否かを検討する際に、45分後にお迎えに行くために、子供が学んでいる時間をどう過ごすかを考えておくことをお勧めします。
学研には何を持っていく?
学研教室には毎回持参すべき文具があります。
幼児の場合、4Bえんぴつ、消しゴム、色鉛筆、ハサミ、スティックノリを用意するように言われました。
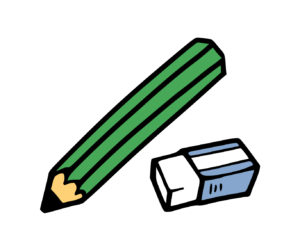
鉛筆がきちんと持てない場合は、三角鉛筆を使用します。
ちなみにこれらの文具、全て100円ショップで売られていたので、筆箱と鉛筆のキャップ、鉛筆削りを含めて1000円以内で準備することができました。
夏の特別教室の期間は、A4がゆったり入るサイズの手提げ袋で通いましたが、入会すると学研教室カバンがプレゼントされます。
宿題は毎日3枚
学研教室では、毎回宿題が出ます。
幼児はかず・ちえ・もじからそれぞれ1枚、計3枚のプリントが1日分の宿題として渡されます。
宿題をする時間と場所をきちんと決めることで、学習習慣が身につくということだったのですが、場所はともかく時間まで決めるというのはなかなか難しかったです…。
ただこのプリント3枚は、1日の量としては多くはなく、むしろもうちょっとやりたいと娘が言い出すくらいの量なので、あまり負担にはなりませんでした。

内容も今のところ楽しいものなので、やりたくないと言い出すことはなかったです。
娘の場合、今はまだ問題文が読めないので、親が読んであげる必要があるのですが、下の子もいるとなかなか長女にかかりっきりになってあげられず、バタバタしながらやることが多くなってしまいました。
学研に通わせるか否かを検討する際には、親が宿題を一緒にやることも込みで考えて判断することをおすすめします。
ちなみに宿題をやる際に、親は子供が分からないところを教える必要はなく、分からないまま持たせて大丈夫とのこと。
逆に親が教えたり、ヒントを与えたところは、問題に〇をつけておくようにと言われています。
○をつけるのは、先生がどこが分からなかったかを把握するためです。
正解していても、○がついているところは何度もやって頂けます。
繰り返し学習が学研の方針なので、一度躓いたところは、何度もやらせてくれます。
褒めて伸ばす
学研教室で、先生に何度も言われたのが「ほめてあげて下さい」という言葉でした。
確かに、普段から娘のできないところに目が行きがちな私にとって、「褒める」ことは意識しないと難しい行為。
褒めて伸ばすが学研の特色の一つなので、宿題を一緒にやるときにも、とにかく褒めることを心掛けました。
学研に通い始めて娘に起こった3つの変化とは?
“学習”への興味が沸いた
娘は、これまで私が数やひらがなのドリルを買ってきても、気が付くとお絵かきして遊んでいるタイプでした。
そんな娘ですが、学研教室に通い始めて数字や文字に触れる時間を持ち、少し分かることが増えたことで、普段の生活の中で気になる数や文字が増えたようでした。
例えば、「今日は何日?」「10日ってどう書くの?」「〇〇ちゃんの「ちゃ」ってどう書くの?」と聞いてきたり、看板の文字を指して、読める字だけ読んでみたりするようになりました。

学研教室の理念の一つに「子供たちに学ぶ喜びを」というものがあります。
「分かる=楽しい」となってくれていたら良いなと感じています。
集中力が養われた
学研教室ではじめにテストを受けた日、すぐにおしゃべりしたり立ち上がったりしようとしていた娘ですが、教室に通い、学研内でのルールを説明されると意外にもあっさり座っていられるようになっていきました。
家で宿題をやっていても、「終わるまでは立ったらいけないんだよ」と自分で言うように。
立ち上がらずに勉強をする練習は、小学校に上がった時に役立ちそうです。
学習習慣がついた
何かきっかけがないと、学習習慣は作りにくいもの。
学研教室に通い、宿題をやることになり、決まった時間までは設定できていませんが、娘は勉強は毎日するものだと思っているようです。
「まだ幼稚園のうちは勉強する時間なんて必要ない」と通わせる前までは思っていましたが、勉強の時間を作るようになって、決まった時間に決まったことをしっかりやれる能力は、大人になってからきっと役に立つだろうと思うようになりました。
私は、学習習慣を持たないままの学生時代を過ごしたこともあり、勉強は得意ではありませんでした。
そのため、娘が毎日すこしずつコツコツできる子にこれからなってくれたら…と願わずにいられません。
夏の特別教室の期間中、毎日「宿題をやらなくては」と思うようになったのは大きな成果でした。
学研の特別教室修了!体験後の勧誘は?
今回4日間の夏の特別教室を受けて、3日目に先生から親が記入するアンケート用紙を渡されました。
アンケート項目の中には、今後入会するか否かについての問いもありました。
そして4日目に教室が始まる時間よりも早めに行き、先生と親子面談をし、学習の成果についてお話しました。
先生からは「特別教室学習報告書」を頂き、これまで娘がやったプリントを見ながら、得意なところともうちょっと力を入れるとよさそうなポイントを教えてもらいました。
最後に今後の話になりましたが、無理に勧誘されるようなことはありませんでした。
私はアンケートに「検討中」と記していたので、入会金が無料になる期間までに考えるように促されましたが、やらないと言ったらあっさりそれで終わる雰囲気でした。
やってみて合わなかったらさらりとお断りできそうなので、今後無料体験をやってみる方は、断れなかったらどうしようと考えなくて大丈夫だと思います。(教室によるとは思いますが)ぜひ気軽に試してみて下さい。

4日間の夏期集中講座を終えると、ノートを頂けました。
幼児には行間が小さめでしたが、今後字の練習などに使えそうです。
学研の体験学習後、入会に迷ったら確認すべきことは?
学習環境を改めて確認する
娘が集中講座を受けた学研教室は、幼児は3名しか通っていませんでした。
あんまり人気がなさそうな気もしますが、少ない方がしっかり見てくれそうなので、よしとしました。
そして何より先生の雰囲気が子供に合うかも大切です。
今回選んだ教室の先生は、私の印象ではきっちりしていて厳しめな印象でした。

私が子供だったら合わないかも…と思ったのですが、誰にでも優しい大人より信用できる気がしたのか、娘は嫌がりませんでした。
他の先生を見ていないので何とも言えませんが、自分で教えるよりははるかにきちんとやって下さるので、よいかなと感じています。
通わせる目的を明確にする
幼児から学習系の教室に通わせる意味があるのか、今一度考えてみました。
高校、大学受験を経験した身からすると、勉強=受験対策=偏差値を上げるためと考えがちです。
娘が自分と同じように、中学までは学区内の公立に通い、高校を受験するのなら、別にそんなに早くから勉強しなくても良いのでは?とも思えました。
そもそも、子供の頃学研に通っていた子が偏差値の高い高校に受かっていたかというところにまで思いを巡らせたり、色々なことを考えてみました。
そこで気がついたのは、私の意識の中に「勉強=受験のため=将来への投資」という感覚が強いということでした。
まだひらがなの読み書きもできない子供に、10数年後の備えをさせるというのは、ぴんときません。
そこで、今、娘自身が学ぶことが楽しいと感じているのならやらせて、嫌がっているならやめようと決めました。

娘に今後通いたいかを聞いて見ると、「教室に通うのは楽しいから、今後も続けたい」とのこと。
宿題が面倒ではないかと聞いたところ、「おもしろいから大丈夫だ」と言いました。
確かに今の教材はまだまだ遊びの延長的なところがあり、煩わしさは感じないのだと思います。
将来のことではなく、今、学ぶことが楽しいと感じていることを大切にしようと思い、ひとまず行きたくないと言うまでは通わせ、宿題をやらなくなったり、行く前にぐずるようになったらすっぱり辞めようと決めて、入会することにしました。
そもそも本当に学研で良い?公文など、他の学習教室と比べてみた
入会させようと決めたものの、学研以外の学習教室を経験したことがないので、「学研という選択がベストなのか」という迷いが生じてしまいました。
そこで、家からの距離、金額、宿題の量の三つの要素で考えてみました。
決め手①家から近い
他の幼児向けの学習教室を探してみたところ、我が家の近くにあるショッピングモール内にもあることがわかりました。
しかし、頻繁に買い物に行くと言えど、ショッピングモールまでは我が家からは少し距離があります。
下の子がいる中での送り迎えの負担を考え、街中にある教室ではなく住宅地の中にある教室の方がよいと判断しました。
うちの近所には、学研教室だけでなく公文の教室もあります。
夏休みにも公文のカバンを持っている子とよくすれ違い、とても流行っている雰囲気です。
そのため、公文と比較して決めることにしました。
決め手②公文より学研が安い
そして、公文と学研の月謝料を調べてみることにしました。
結論としては、公文に比べて学研の方がリーズナブルです。

学研の年中のさんすうこくごコースの月謝は
| 週1回 | 6,480円(税込) |
|---|---|
| 週2回 | 8,640円(税込) |
いずれも、教材費込みの金額です。別途年間2回冷暖房費は1,400円ずつかかります。
公文の場合、幼児小学生は1教科6,480円(税込)。
こちらも教材費込みの金額ですが、算数と国語の2科目やると12,960円(税込)になります。
東京・神奈川の教室は、幼児・小学生の1科目が7,560円(税込)、それ以外の地域は7,020円(税込)になります。
将来云々ではなく今楽しいという感覚だけのために払うのなら、金額の安い学研の方で良いかなと思いました。
決め手③公文は宿題10枚。学研は3枚。
そして、気になる宿題の量についても比べてみました。
公文の宿題は、1教科あたり20~30分でできる量が目安となっているそうで、公文に通っている親戚の子供の場合は、毎日10枚のプリントをやっています。
しかも、それを全部正解になるように親が見て、持っていくのだとか。
1日サボったら、翌日20枚になってしまう…
勉強が好きでなかった私には恐怖ですし、親として10枚を毎日きちんとやらせる自信がありません。
1日3枚の宿題を学研で頑張ってもらう方が我が家にはあっていると感じました。
学研教室、週1回と週2回どちらにコースにすべきか?
学研教室では、週1回と週2回のコースを選べます。
今回、娘は週2回コースで始めることにしました。
理由はコスパが良いから(週1回は6,480円(税込)週2回は8,640円(税込))
さらに週2回コースの場合は、教室に行った日以外の分=全部で5日分宿題が出るので、勉強しない日がなくなるのですが、週1回の場合は宿題が4日分しか出ないので、勉強をお休みする日が2日できてしまいます。
折角ならはじめは、毎日学習にチャレンジした方が良い気もしました。
ちなみに、週1回だけ通い、宿題だけ週2回と同じ量貰うことも可能だそうです(その場合、月謝は週2回分になります)
週何回通うかは途中で変更も可能なので、ひとまずやってみて考えてみようと思っています。
まとめ
習い事をするためのお金や時間は無限にあるわけではないので、今何をやらせるべきかとても悩みますよね。
我が家では、もともと夏休みだけのつもりで行かせた学研教室に入会することになりました。
実際にやってみると良さが分かる場合もあるものだと感じています。
気になる方は是非試してみて下さいね。
子供の学習は、独り立ちしてくれるまで、これからもずっと悩みの種になっていくと思います。
結果はまだまだ出ませんし、そもそも何が正解かも分かりませんが、しっかり考えて選択していけたら良いですね。
学研も選択肢の一つにしてみて下さい。