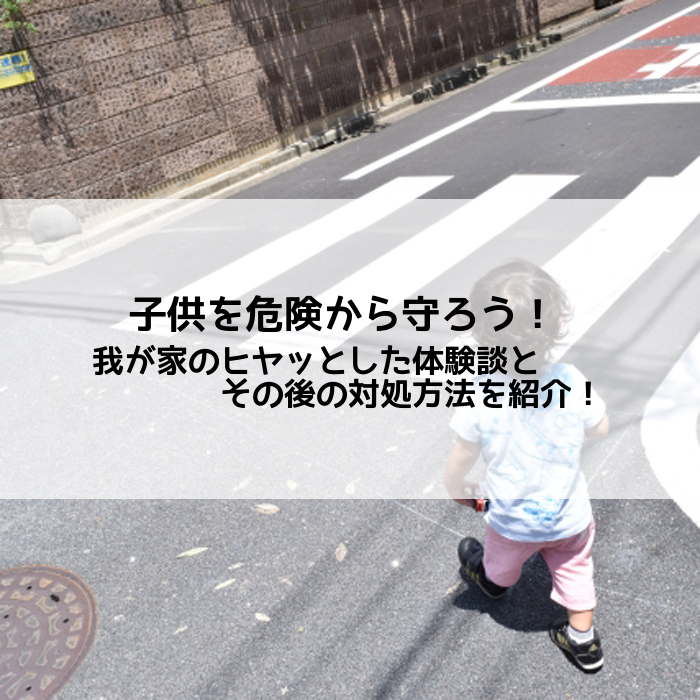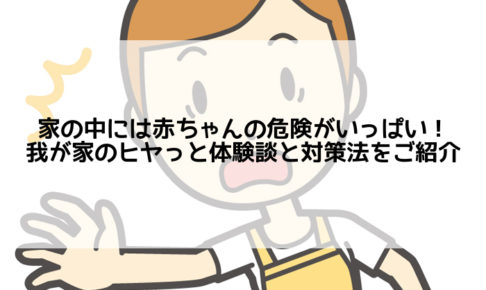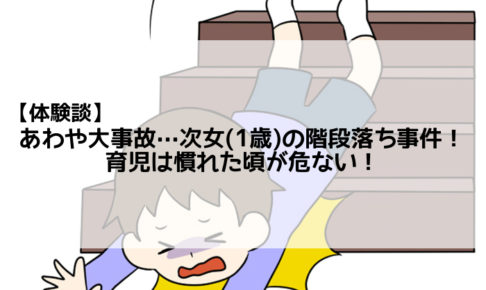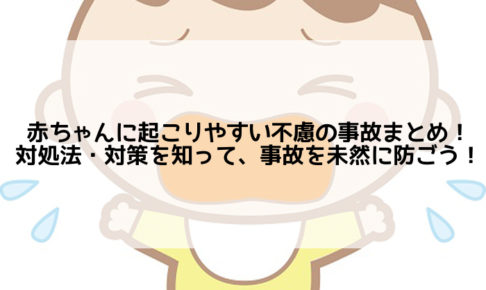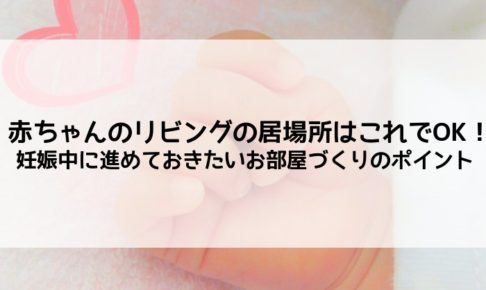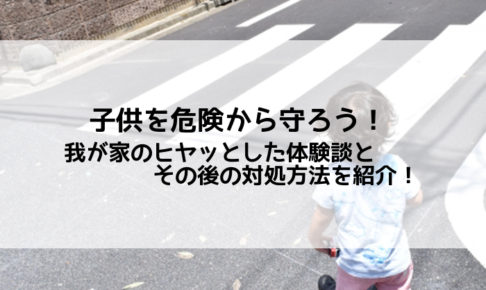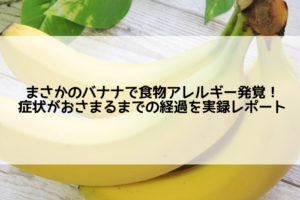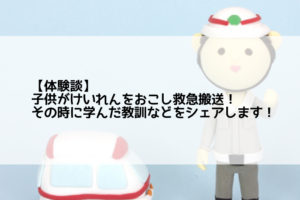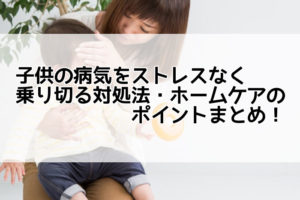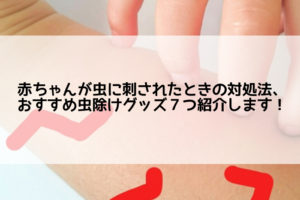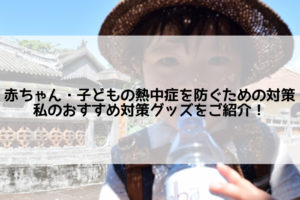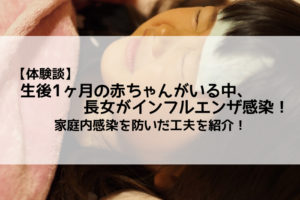ののかママ
最新記事 by ののかママ (全て見る)
- 保育園入園が決まったけど寂しい…。保育園に預けることへの葛藤、私はこう乗り越えました! - 2018年12月31日
- ひらがなの勉強はいつから?我が家の場合と実践している練習法をシェアします! - 2018年12月29日
- 我が家流・イクメンパパの育て方!育児に消極的だった夫を変えた4つのポイントをシェア! - 2018年12月26日
ママテク(@mamateku)ライターのののかママです。
いつもニコニコ笑顔で穏やか、決して怒ることなく、優しく子どもを諭す、そんな素敵なお母さん…を妊娠中は目指していたにもかかわらず、毎日毎日繰り広げられる「何をどうしてそうなった?!」という事態にそんな理想はどこへやら…。
「こら!」「なんでそんなことしてるの!」と、どなりつけることや、「うそでしょ?」「ちょっとまったぁ!」と焦ることもしょっちゅう。
実は、子どもを産む前は道端で子どもを怒鳴るお母さんたちを見て、「なんであんな小さな子相手にあんなにムキになってるんだろう」とか「ああいう、きりきりしたお母さんって嫌だな」なんて思ってたのですよ(反省)
しかし実際に子どもを持ってみると、予測不可能なことが多すぎてそんなこと微塵にも思っていられない。ヒヤッとすること、一瞬思考が停止してしまうこともしばしばです。
過度に子どもの体やその人間性を傷つける怒り方はまた別の話ですが、きっとたいていのお母さんが子どもを本気で怒る理由って、我が子を危険から守りたい母性本能から来ているのだろうなぁと思います。
今回は我が家のヒヤッとした体験やその後の対処方法などをご紹介します。
どうやったら大事な子どもたちを守れるか、一緒に考えていただけると幸いです。
パッと読むための目次
そもそも乳幼児の事故とはどんな時に起こりやすい?
乳幼児の事故、これは不慮の事故と呼ばれているものですが、東京都福祉保健局の調べによると、平成18年度においての子どもたちの死因は不慮の事故が原因であるケースが非常に多く、死因順位には0歳児で第5位、1-4歳児で第1位となっています。

また、当局の調べによると、事故の発生は昼間、親がそばにいる時に起こるケースが一番多いことも分かります。
参考URL:https://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/shussan/nyuyoji/jiko_kyouiku.files/handbook1-2.pdf
日ごろ子どもの行動についてはかなり目を光らせて十分に気を付けているご家庭がほとんどかと思いますが、きっとそれでも起きてしまうのが不慮の事故。
【スポンサードサーチ】
自分の家に起こったことではなくても、テレビ等でその報道を聞き、胸を痛めているお母さんも多いのではないでしょうか。
過去の色々な事例を参考に、ご自宅の安全対策を考えていく必要がありそうです。
ベッドから転落 子どもの成長に親の意識がついていってなかった寝返り期
我が家で初めてヒヤッとした事故、それは転落です。
不器用にも寝返りし始めたある日のこと。私は娘を大人のダブルベッドにコロンと寝転がせて、少し離れた場所で洗濯物を畳んでいました。
それまで寝返りがあんまり上手ではなかったので、寝返りしても通常半回転、うまくいけば1回転。
1回転であればベッドから落ちる心配もないだろう…と、娘をベッドの奥に寝かせて、洗濯を畳み続けていました。

そして洗濯を畳み終えて、ふと目線を娘に向けると、私の目に入ってきたのは娘がベッドから落ちる瞬間でした。
まるでスローモーションのように時がゆっくり流れたのを覚えています。
気づくと娘はコロンコロンコロンと3回、寝返りをしていたのです。ダブルベッドに寝かす寸前まで、半回転又は1回転できるだけが精いっぱいだったのに、あっという間に3回出来るようになり、そして落下。
子どもは1分1秒を待たずにどんどん成長しているんですね。さっきまでできなかったことが数分後には出来るようになっている。
「まだできないから大丈夫だろう」という意識は持たない方が良いとあの時学びました。
落ちた娘は勿論大泣きです。
幸いにもモモンガのような格好で落ちたので、頭を打ってはいなかったことと、泣いているという事は意識はあるんだろうな…と、大泣きする娘を抱きながら安心しつつも、母親学級で学んだ落下時のチェック項目を確認しました。
- 声をかけると反応があるか、意識がしっかりしているか
- 目線はしっかりしているか
- 痙攣していないか
- ケガはしていないか、腫れていないか
- 嘔吐していないか
上記の該当がない場合はしばらく様子を見ても大丈夫だそうです。しかし、
- 様子がおかしい(寝ていて起きない、ずっと眠そう、泣かない、目線がおかしい、意識がない等)
- 打った場所がぶらんとしている、腫れている、触ると泣く、打った場所が凹んでいる
- 痙攣している
- 出血がある
- その他普通とは違う症状
我が家の場合はすぐ泣き休み、すぐにおっぱいを上げても何ともなかったため、しばらく様子を見ることにしました。
おそらく頭を打っていないことと、ベッドの下にはやわらかめのラグを引いていたために、衝撃が少なかったのかと思われます。
また、我が家の大人のベッドですが、結構な高さがあります。そして、普段娘はベビーベッドに寝かせていたため、ベビーガードはつけていませんでした。
その後、夫とベッドガードを設置するべきかを検討はしたのですが、普段寝る場所ではないので設置は見送りました。
その代わり、大人のベッドに寝かせるときは決して離れず、ベッドの上で洗濯を畳んだり、足元に掛布団を敷いたり、万が一落ちても痛くならない対策を取りました。
大好きなうどんが・・・あわや窒息事故
うちの娘はうどんが大好き。簡単なので家でも良く作りますし、外食をすればうどんを頼むこともよくあります。
家で作るうどんは先に短く切ってあり、わりと長く煮ていることもあってやわらかいですが、外のうどんはそうはいきません。コシがあるものもありますし、通常は長いまま出てきますよね。

「お母さんが短く切るから待っててね」そう伝えても、お腹を空かせている所に大好物が出てきているわけですから待てるわけがありません。
ちょっと目を離したすきに、一本丸々食べてしまう娘。そしてそのうどんのコシが強いため、喉に詰まらせる。げふげふと真っ赤な顔で苦しそうにしている娘を見ると、一瞬思考が止まります。
その都度、背中を叩いたり、口から見えているうどんを引っ張り出したりして、詰まっているものを吐き出させてきたわけですが、調べてみると気道が3-6分ふさがれてしまうだけで死に至るリスクがぐんと高まるようです。
3分なんてあっという間。すごく怖いですよね。
今は動画サイトでもその他の応急処置のサイトでも詰まらせ時の対処法が紹介されています。
何かあった際に冷静な対応が出来るよう、日ごろから対処方法を調べておいた方が良いでしょう。
私は過去に応急処置の講習を受けたことがあった為、背部叩打法で事なきを得ました。
何とか助けることができたものの、実際に自分の娘が窒息している時は自分自身の心拍数も上がり、子どもの名前等を叫びつつけ、半ばパニックでした。
あれ以降、我が家は外食をする際に、子どもの目の前や手の届く場所には食べやすく切ったものしか置きません。
今はもう3歳なので、うどん以外はお皿のまま渡していることもありますが、ちゃんと座っているか、1回に口に入れる量は適量か、よく噛んでいるか、水分を取っているか等、食事中には気を遣うようになりました。
子どもからの閉め出し
これは私の夫の話ですが、娘から閉め出されてしまったことがありました。
ある暑い夏の日のこと、ちょうど娘が2歳になる前くらいのことです。
私は用事があり外出をしていて、夫と娘は用事が終わるころに駅まで車で迎えに来てくれることになっていました。しかし、大体何時ごろと伝えてあったものの、時間になって夫に電話をしても一向に出ません。
何かあったのかな…と心配をしつつも、かなり外は暑く、駅から家まで結構かかる距離。電話がなくてもこちらに向かっているかもしれないし…と、私は駅で時間をつぶしながら夫と連絡が取れるのをのんきに待っていたのです。
その時、大変なことが夫や娘の上に起こっているとも知らずに…。
約束の時間から2時間後、やっと夫が電話に出て迎えに来ました。
そして話を聞くと、私を迎えに行くために、娘も夫も用意をして玄関に居た時のこと。夫がママバッグなどを車に乗せていた時に、後ろで「ガチャン」という音がしそうです。

振り返ると、玄関の鍵を娘が閉めてしまっていました。
夫の家の鍵と携帯電話は家の中。焦ってドアを叩く夫に娘もただならぬ気配を感じたのか玄関の中から大泣きです。
『開けて!開けて!』叫び続ける夫の声を聞きつけ、近所の人たちも全員出てきたそうです。
とても暑い日です。いつ娘が熱中症になるかもわかりません。きっと泣き続けて体力も奪われているでしょう。
そして何よりも不運なことに携帯も家の中なので、私に電話する事も出来ず、結局は同じアパートの人に大家さんに電話をしてもらい、車で1時間のところにいた大家さんが慌てて駆けつけてくれて鍵を開けてくれたそう。
その時娘は泣き疲れ、暗い玄関で眠っていたそうです。
この話を後から聞いて夫にはかなり怒りが沸きましたが、しかし、閉め出されたという話は意外とよく聞きますよね。
子どもって鍵を触るのが大好き。洗濯を干している間、脱衣所で服を脱いでいる間、車から離れた途端…きっと鍵を触りたくなるのは子どもの性分なのでしょう。
普段から言い聞かせることが勿論一番大事ですが、万が一鍵を閉められてしまった場合どうすればよいか、閉められないようにするにはどうしたらよいか、常に考えておく必要があります。
ちなみに我が家はあの閉め出し事件以来、鍵と携帯は常に保持が原則です。
近所に住むおじいちゃんおばあちゃんにもスペアキーはもって貰い、車の中に各々の電話番号を書いた紙は入れておくようにしています。
また、洗濯を干すとき等は別の窓も開けておくようにしています。
そして、1番確実な対処法は、ちょっとの間でも子どもも連れていくことです。子どもの手を握っていること、それを上回る安心はないです。
大人の常識は子どもには通じない!鼻や耳に異物が…
10円玉を飲み込んでしまったとか、タバコを食べてしまったとか、そういった誤飲の話を保育園のお母さんなどから聞いていて、乳児の頃は口に入れられる大きさのものは放置しないようにかなり気を付けていました。

しかし、たとえうっかり置きっぱなしにしてしまっても、うちの食いしん坊な娘は美味しいものにしか興味を示さない。
たった1度だけ、パパの食べていた柿の種をこっそり食べてしまい、その辛さに思わず大泣きをしてこっそり食べたことがばれた(笑)…ということはあったものの、誤飲に関してはうちは心配ないな…と安心しきっていました。
ところがある日。これはもうつい最近のこと、娘3歳間近にして起こった出来事です。お休みの日に家族で出かける前に各々が準備をしている最中の出来事です。
先に着替えやもっていくものを揃えた娘はお人形を着替えさせたり、指輪やネックレスを付けてあげたりと、一人で楽しそうにおままごとをしていました。
そんな娘を傍目に化粧を終えて『さぁ行こうか!』と声をかけると、先ほどまで楽しそうだった子がベッドに顔をうずめてしくしく泣いています。
いつものぎゃんぎゃん泣く大泣きとは明らかに雰囲気が違うので、「どうしたの?」と驚いて声をかけると、急にぎゃああと泣き叫び

ふと娘の足元を見ると、お人形につけてあげていたネックレスが壊れ、ビーズが散らばっています。
そのビーズを鼻に当ててみたらいたら、鼻に入ってしまったそうです。

そうです、うちの娘、誤飲はなくても、異物を鼻に入れるという事は行ったのです。
きっと子どもの心理的には、誤飲も異物の体内混入も同じ好奇心からの事故ですよね。
「食べてみたら美味しいかな」「鼻に入れてみたらどうかな」ということなのかなと思います。
鼻をこじ開けてみてみると、確かに鼻の中に赤い物体が入っています。しかもビーズは横向きに入っているので、家の中にあるようなピンセットでとることは正直難しい…痛い痛いと泣き叫ぶ娘を抱え、外出前に耳鼻科に駆け込んだのでした。
耳鼻科の先生に話を聞くと、結構この手の異物を鼻や耳に入れてしまう事故は多いそうです。
言ってわかる年齢、そして鼻をかめるくらい大きな子どもであれば鼻をかむことで異物がとれる場合も有るそうです。
しかし、まだそれよりも小さな子たちに関しては家で無理にとると傷がついてしまう場合も有るので、痛がる様子がなくとも耳鼻科で安全に対処する方が良いとのこと。
耳の場合も傷がつくと困るので基本的に耳鼻科を受ける方が良いそうです。
そして鼻に入ったビーズは「記念にして下さい」とご丁寧に返して頂きました(笑)娘はそれを見るたびに、お鼻に入ると痛いの…と言っています。
身をもって痛みを知ったことで二度としないとは思いますが、子どもは好奇心の塊です。
分かる年齢であれば言い聞かせる、わからない年齢であれば鼻や耳に入れる危険のあるものはおいて置かない方が良いですね。
外出時は危険がいっぱい。駐車場は特に注意を
テレビのニュースで、駐車場で子どもがはねられる事故を目にすることもあります。
駐車場は割と死角が多く、また子どもの身長がその死角に入ってしまうために起こることが多いそうで、その話を聞くたびに『我が家も気を付けよう!』と駐車場は必ず手をつなぐようにしてきました。

しかし、丁度子どもが2歳になったばかりの頃、子どもの身長は85センチくらいの頃です。駐車場での事故にあいました。
正確には私がですけど、子どもの手を引いているときだったので、もしも娘が私がいた車道側を歩いていたら…と思うと冷や汗が出ました。
車を運転している方は分かるかと思いますが、85センチの子どもが車の真後ろに居た場合結構見づらいですよね。
あの日、近所のショッピングモール駐車場で私と娘が歩いていると、セダンタイプの車が駐車場に車を入れようとバックでググッと迫ってきました。
その車はセダンタイプですので車止めに合わせて停めても、車の後ろの部分は歩道側にはみ出てきます。
しかもとても狭い歩道で、まず私に車の後ろ部分が当たり、その反対側を歩いていた娘も転んでしまいました。
幸運にも、運転手さんは私がぶつかったことに気づいてストップしてくれたために大ごとにはならなくて済みましたが、ゆっくり動く車もぶつかれば結構な衝撃でした。
子どもを守るのはほんの少しの習慣からです。
外を歩いていると、狭い歩道での車道側を子どもが歩いている姿を見つけます。
私と娘があったように、車が突っ込んできた時や自転車が走ってきたとき、親が子どもをかばえるように常に意識をしておく事が必要だと思います。

また、子どもが手をつなぎたがらない時もありますよね。日ごろから手をつなぐことの大切さを伝えていくことは絶対に必要ですね。
我が家もイヤイヤ期があり、手をつないでくれなかったのですが、

大事だよ、大好きだよ、ケガしたら悲しいよ、と日常で伝えていくことも大きな事故を予防する手立てになるかもしれません。
日ごろから危険因子の発見を
その他にも、テレビを見れば、窓からの子どもの落下事故、交通事故、車の中での熱中症、浴槽やプールでおぼれる事故等々、決して珍しいニュースではありません。
おそらくニュースになる前の事故もその数同様にたくさんあるのではないかと思います。
日ごろから何をどうするとどんな危険があるのか、その危険が生じた場合にはどうすればよいのか、シミュレーションをしておくことが子どもの安全を守ることにつながると思います。
まとめ
どのお母さんも、子どもの安全を守るため日々奮闘されていると思います。
しかし、どんなに気を付けていても、ほんの一瞬、ちょっと気が緩んだすきに、目を離したすきに、起こるのが不慮の事故。後悔してからじゃ遅いのです。
気を付けて気を付けて気を付けて…それでも完全な安全はないのでしょうけど、せめて精一杯子どもを危険から守っていきたいです。
常に気を張っていなければならなくて、「なんでこんなに毎日怒ってばかりなんだろう」と自信を無くしたり、疲れたな…なんて嘆きたくなったりすることも時折ありますが、いずれ子ども自らが自分を守れる日がやってきます。その時まで、一緒に頑張りましょう。