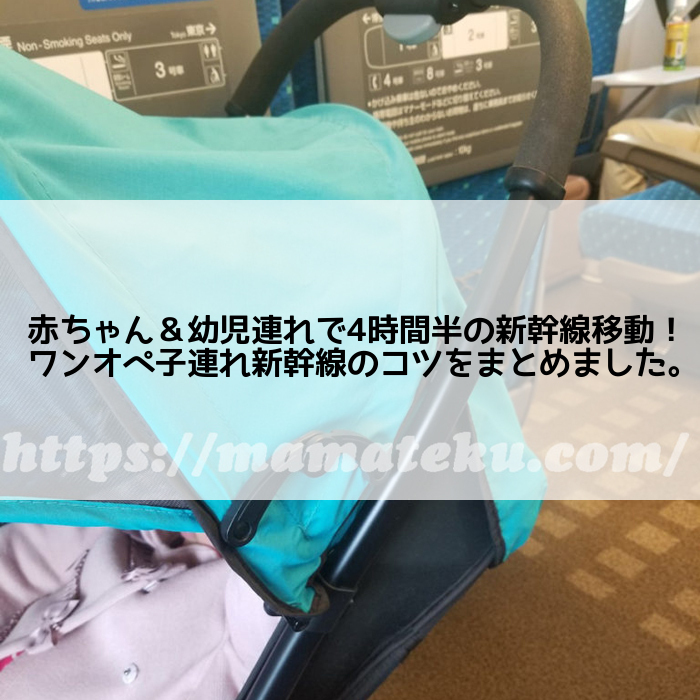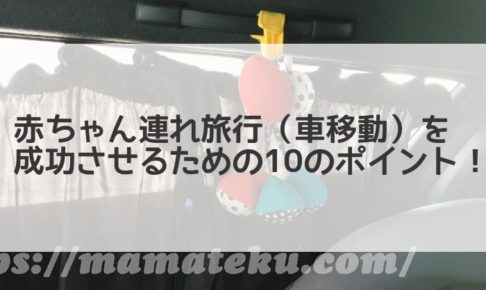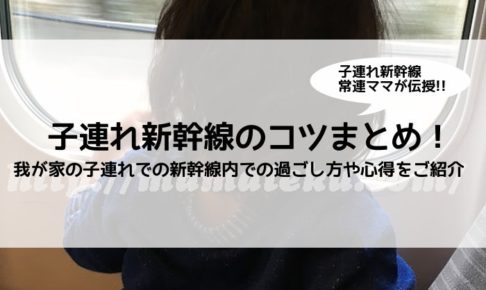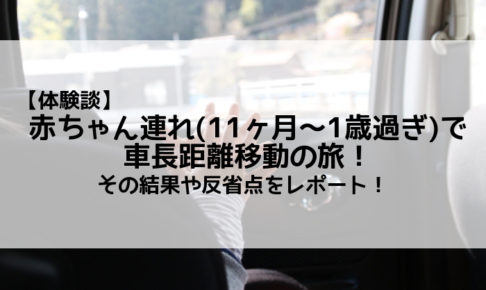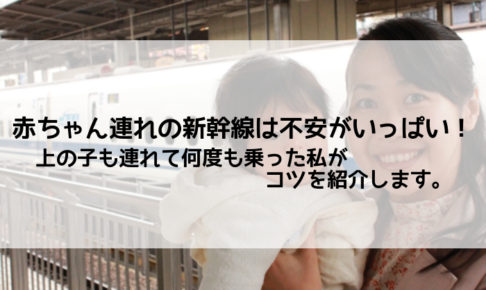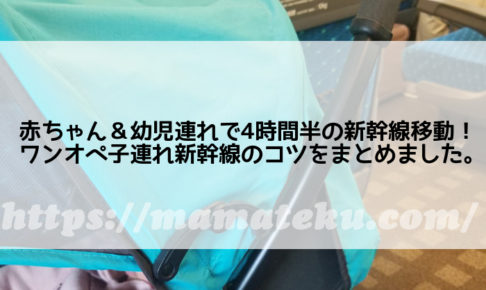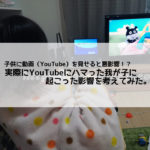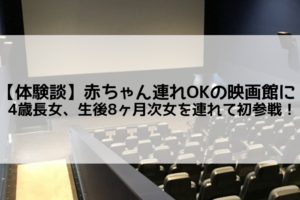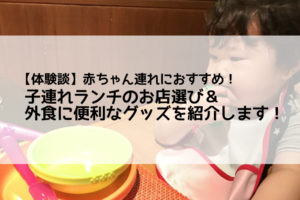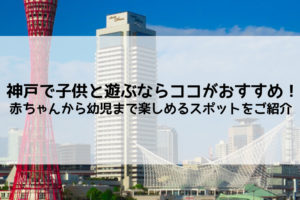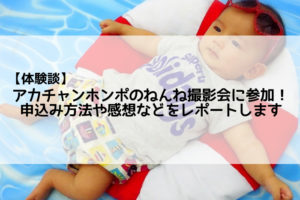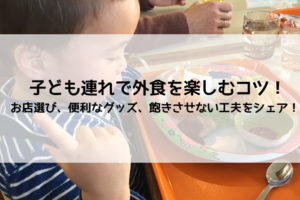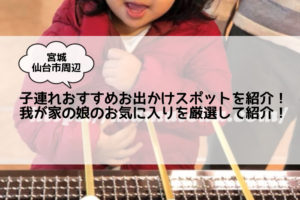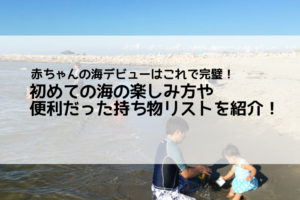あっこちゃん
最新記事 by あっこちゃん (全て見る)
- 子供のお絵かきデビュー!なるべく安全に、汚さないために工夫していることをシェア! - 2019年3月6日
- 手づかみ食べのストレスを軽減できるメニューはこれ!ママも赤ちゃんも楽しくなるレシピを紹介! - 2019年2月17日
- 世代を超えて親子でハマった!50周年を迎えたリカちゃん人形の世界が凄い! - 2019年2月1日
ママテク(@mamateku)ライターのあっこちゃんです。
新幹線に乗ると、帰省するのか帰省先から戻るのか、ママが1人で子供を連れて乗っている姿を見かけます。
私自身も片道4時間半かけて新幹線に乗って帰るので、子連れのママを見ると同志のような思いになり、勝手に親近感を抱いています。
長時間の新幹線移動は毎回しっかりとした準備と大きな覚悟が必要です。
我が家は昨年下の子が生まれたため、2人を率いての移動となり、これまで以上にしっかりとプランニングすることが大切だと感じています。
それにしても、1人の時でも大変だと感じていたのに、2人になると1人だけだったときは楽だったと感じるから不思議ですね。
今回、4歳の長女と4カ月の次女を連れての新幹線移動の体験から、準備のポイントをまとめてみました。
我が家は上と下が4歳差なので、年子を連れてなどもっと大変な方がいらっしゃるとも思いますが、

パッと読むための目次
子連れ新幹線の必勝法:とにかく寝てもらうようにすること!
新幹線に限らずですが、長時間の移動の必勝法は「一秒でも長く子供を寝かす」ことです。
自由に動き回ることができない空間に、じっとしていられない子供をとどめておくのは至難の業。
眠らせてしまえばこっちのものです。
新幹線で子供に寝てもらう方法
新幹線の車内で寝てもらうためには、昼寝しやすい時間に乗車することが大切です。
【スポンサードサーチ】
ただ2人連れとなると昼寝のタイミングは必ずしも同じでないので、一緒に寝かすのは簡単ではありません。
我が家の場合は今回、退屈するとうるさくなる長女(4歳)のお昼寝のタイミングで乗車しました。
子供って「寝てくれ」とか、眠くて機嫌が悪いときに「おとなしくしてくれ」と思うと、逆にぐずったり寝てくれなかったりしませんか?
「寝なかったら仕方がない」とゆったり構えておくことも大切。
泣いても親が慌てず振舞うと子供は安心して寝てくれることが多いです。

自由席の入り口から近い場所を確保
新幹線の料金は、小学生半額(子供料金)、未就学児無料です。
ただし、未就学児が無料になるのは、乗車券と自由席特急券のみ。
指定席に乗る場合には、小学生と同じで、乗車券と指令席特急券の半額分の料金が必要になります。
また、大人1人で子連れ乗車した場合、未就学児が無料になるのは2人まで。
乳幼児が3人になると自由席であっても、子供料金=大人の半額の料金を支払うルールになっています。
我が家の場合は、乳幼児が2人のため、自由席なら子供たちの料金が無料になるので、自由席を利用しました。

自由席のどの席を確保するようにしているかというと、デッキからなるべく近い席です。
子供がじっとしていられない場合は、デッキに出るママも多いです。
今回の帰省でも、デッキには赤ちゃんを抱っこしているママが入れ替わり立ち代わりで何人もいました。
ただ、子供を2人連れている場合、片方が寝てしまうとどうするべきか悩ましいですよね。
我が家は上の子が4歳で、
- 勝手に動かない
- 知らない人についていかない
と言えば理解はできるので、上の子を座席に寝かしたまま下の子をデッキであやして過ごした時間もありました。
デッキから座席の距離が遠いと往復するのは大変ですし、上の子を一人にするのが心配。
そのため、デッキから上の子の寝ている姿が見えるところに席を確保しました。
今回は幸運にも、通路を挟んだ隣の席に、同じように4歳と0歳の子連れのママがいたので、お互い声を掛け合って下の子とデッキに出たり、上の子の様子を見たりするようにしました。
特に心配なのは、新幹線が駅に到着し、乗客の入れ替えがあるタイミングです。
ドアが開いている時間は、上の子がどこかに行かないように必ず座席に戻り、隣にいるようにしています。
乗り降りがある時には、車内が賑やかになるので、ぐずる下の子を連れていても比較的席に居やすいです。
オムツ交換は、奇数号車の東京寄りの洋式トイレで
自由席を選ぶ時に、トイレがあるデッキの近くを選ぶことも大切です。
洋式トイレにはオムツ交換台がついています。
のぞみで東京方面に行く時は、1号車の後側・2 号車の前側・3号車の後側を選ぶようにしています。

ちなみに3号車の後ろには喫煙ルームが付いているので、2号車の後側と3号車の前側は避けています。
自由席がすいている時間もチェック
我が家は新幹線の始発駅ではない場所で暮らしていて、実家の最寄も始発駅ではないので、乗車の際、時間によっては行きも帰りも自由席が空いていないことがあります。
子供たちの昼寝のタイミングも大切ですが、それ以前に席を確保できないと困ってしまうので、自由席がすいている時間も考慮して移動するようにしています。
午前中の早い時間は、日帰りで出かける人が多く混雑し、夕方は帰宅する人たちがたくさん乗車しています。
その時間を避けたお昼前後が一番混みにくいので、お昼ちょっと前に乗車してお弁当を食べさせ、昼寝させることを目指しています。
また、連休中の自由席はどの時間を狙っても座れないことが多いので、帰省は連休にぶつからない時期を選ぶようにしています。
家族に荷物を持って先に入場してもらう
子供2人連れの帰省は、大荷物になります。

帰省先で使うものは事前に宅配便で送りますが、車内で必要なものだけでも結構な量になります。
さらに下の子を抱っこして、上の子の手を引いてベビーカーを押してとなるとなかなか大変です。
今回の帰省では、行きは夫に荷物をホームまで運んでもらい、新幹線を待つための列に並んでおいてもらうことで自由席の良い位置を確保することができました。
新幹線移動の持ち物~長女(4歳)の持ち物編~
お菓子・お弁当・飲み物
子供が「寝る」以外に子供がおとなしく座っていられる時間は「食べているとき」です。
そのため、食べ物と飲み物は子連れ新幹線の生命線とも言えます。

我が家では普段、お菓子は少しずつ食べさせていることもあり、長女はお菓子をたくさん持っているだけでわくわくしてお利口にしようとしてくれますし、食べている時間は静かです。
新幹線でお弁当を食べるのも、子供にとっては特別な時間。
ちなみに余談ですが、私は駅弁でテンションが上がりますが、残念ながら娘には不評でした。
今回、車内販売を利用したら長女が喜ぶかなと思い車内でお弁当を買ったのですが、高価な駅弁が1種類しか残っていなかった上、あんまり食べてくれずがっかりしました。
逆にテンションが上がってよく食べたのが、普段あまり行く機会のない駅にあるコンビニのおにぎり。
子供の口に合うもので、非日常を感じられるものが喜ばれるのかもしれません。
車内では飲食の回数が多くなるので、ウェットティッシュもあると便利です。
お絵かき帳・色鉛筆

長女はお絵かきが好きなので、好きなキャラクターの塗り絵やお絵かき帳はマストです。
あまり重くないもので、長く集中して遊べるおもちゃを用意していくのは大切です。
スマホでdキッズ
我が家では、飽きてしまったときの最後の手段にスマホを与えることにしています。
スマホでは「ドコモのdキッズ」という知育サービスを利用しています。

dキッズの魅力は、数のおけいこやクイズなどをゲーム感覚で楽しくできるアプリが使い放題なところです。
娘は、少し前まではアンパンマンと間違い探しをしたり、じゃんけんができるアプリが大好きでしたが、最近ではプリキュアと一緒に数を数え、クイズ感覚で足し算にもチャレンジしています。
その他にも、はなかっぱ・はらぺこあおむし・ハローキティ・ドラえもんなどの人気キャラクターと一緒に、国語算数英語などが学べるアプリが30種類以上あります。
知育なので、親としては「スマホに頼っている」という後ろめたさが軽減されるのも嬉しいところです。
さらにスマホをいったん渡してしまうと、子供たちはなかなかおしまいにできないものですが、dキッズには「タイマー機能」が付いているので、時間を過ぎると自然に終了できます。
我が家では、30分だけと決めてスマホを渡し、30分になると親に渡すことを促す画面が出るので、それ以上できないことになっていると説明して納得させています。
「ドコモのdキッズ」の利用料は、月額372円(税抜)で、ドコモだけでなく、auやソフトバンクの対応機種で利用できます。
我が家はタブレットを使っていないのですが、以前ドコモショップで聞いたら、タブレットで学習させているご家庭も多いそうです。
酔い止め
うちの子は2歳をすぎたくらいから、ちょっと調子が悪いときに遠出をすると、必ずと言っていいほど嘔吐します。
4歳になって、吐くことが少なくなってきたので油断していたら、はじめての子供2人連れの新幹線内で乗車3時間を過ぎた頃に嘔吐しました。
本人も酔ったという自覚はなく、嘔吐する前に「なんか臭い」と繰り返し、機嫌が悪くなり困っていたら、座席で戻してしまいました。
反射的に手で受け止めたので大惨事にはなりませんでしたが、その後車掌さんに汚してしまったことを伝えると、おしぼりをくれたのに加え、座面を取りはずして交換してくれました。
さらに
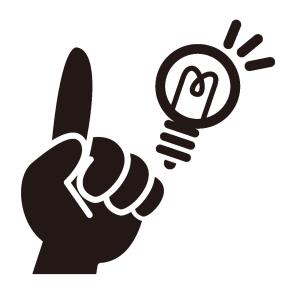
対応が手慣れている様子でとても有難かったです。
嘔吐後、片付けなどをしていたらあっという間にあと30分で到着というところまで来たので、結局酔い止めは頂きませんでしたが、次に乗車する時からは、子供用の酔い止めを飲ませるようにしています。

酔い止めは5歳から使用できるものが多いので、我が家のように5歳未満の場合は3歳から飲ませられるタイプを探すことが大切です。
酔い止めを飲むと眠くもなるので、吐かずに寝てくれて非常に強い味方だと感じています。
着替え
そして嘔吐した際には、念のためにと用意していた着替えに救われました。
4歳になって、赤ちゃんのころのように服を汚すことはとても少なくなりましたが、長時間の移動では何が起こるか分からないもの。
4歳でも着替えと下着は持っておいた方が安心です。
ちなみに長女の着替え・おもちゃ・お菓子は、長女のリュックに入れて自分で持たせるようにしています。
新幹線移動の持ち物~次女(生後4ヶ月)の持ち物編~

ミルク小缶
4時間半新幹線に乗ると、1回か2回はミルクタイムがあります。
次女とのお出かけで、最初のころは小分けされたキューブタイプやスティックの粉ミルクを使っていたのですが、最近では割安感を重視し、ミルクの小缶を持ち歩いています。
帰省する際、実家でも当然ミルクは必要なので、小缶を持ち歩けば滞在中にも使えて便利です。
ちょっと重くてかさばりますが、スティック1本分13g当たりの金額を比較してみると、スティックは51円、小缶は41円になります(和光堂レーベンスミルクはいはい/希望小売価格・税抜で比較)
実家に7日間滞在し、1日5回飲むとその差は350円…。
普段ベビー用品の安売り情報を気にしている身からすると、小さくない金額です。
ミルトン容器ごと哺乳瓶
我が家では、ミルトンを使って哺乳瓶を消毒しているのですが、帰省先にはミルトンの容器がありません。
また、哺乳瓶も持ち帰る必要があります。
そこで考えたのが、「ミルトンそのまま持ち出し作戦」です。

今回、ミルトン容器に普段使っている3本の哺乳瓶を入れて持ち帰りました。
家を出る直前にミルクをあげると哺乳瓶を1本使うことになります。
その哺乳瓶を消毒するのに1時間かかるので、消毒を待ってから家を出ると、あっという間に次のミルクタイムになってしまいます。
そこで、使い終わった哺乳瓶を洗って消毒液に入れたまま持ち出し、入れてから1時間が経過したところで、車内で水を捨て、消毒済みの哺乳瓶が手元に3本ある状態にしました。
新幹線が何らかの事情で止まってしまうと、車内での授乳回数も増えます。
消毒した哺乳瓶が足りないという状態を防ぐためにも、ミルトンそのまま持ち出し作戦は有効です。
ちなみに今回の帰省の際には、前の車両の点検と車両交換のため、70分到着が遅れました。
もともと4時間30分の移動が、5時間40分に…。
消毒していた哺乳瓶を3本持っていたので慌てずにすみました。
水筒(お湯)
調乳用のお湯も、車内にはないので忘れてはならないアイテムです。
次女の調乳用に新調したサーモスの水筒は保温力が抜群で使いやすいです。
授乳ケープ
次女は混合で育てているので、母乳タイムも必要です。
授乳は、窓のブラインドを下ろして、窓側の席で授乳ケープをしてしました。
授乳ケープがあればどこでも授乳できますし、おっぱいを咥えると寝てくれることもあるので、移動中にも重宝しました。
おむつ・おしりふき・レジ袋
オムツは5枚程度、おしりふきは普段のお出かけセットに加えて多めに持って乗車しました。
おしりふきは長女が戻した時にも使えましたし、お尻をふくだけでなく何かを汚して困ったときに活躍するので、多めに持っておいた方が良いです。
オムツを捨てるために普段からレジ袋もオムツポーチに入れていますが、多めにあると汚れた着替えを入れたり、ごみをまとめたり何かと役立ちます。
レジ袋は5枚以上、カバンに入れておくようにしています。
バスタオル
バスタオルは眠った時にかけてあげたり、シートの上に寝かせて遊ぶときなど、何かと使えます。
薄手のタイプをベビーカーの下のかごに入れておくと、出番は多いです。
着替え
吐き戻したり、うんちが付いてしまったときに着替えるので、着替えは下着を含めて最低2組は入れるようにしています。
慣れない環境のせいか、普段はそんなに着替えないのに、出先では何度も汚したりもするので、やはり着替えは大切です。
クレベリン
新幹線に長時間乗る中で、

そこで、クレベリンのペンタイプをカバンにつけていくことに。

クレベリンは、二酸化塩素の力でウィルスや菌を除去するとされる商品。
今回使ったペンタイプだけでなく部屋の中に置いておく形やスプレータイプもあります。
塩素というと臭いがきついイメージがありましたが、クレベリンの臭いは感じられませんでした。
クレベリンのおかげかは分かりませんが、今回往復新幹線で行き来して、体調を崩すことはありませんでした。
ベビーカー
我が家のベビーカーはそんなに大きなタイプではないので、二人掛けの座席の間にそのまま入れられます。

大きなタイプだと席の間に入ったとしても前の席の人が椅子を倒したときに引っかかってしまったりするので注意が必要ですが、そのまま入れられると子供を寝かすこともできるので便利です。
母子手帳・保険証・医療証
万が一に備えて忘れないようにしたいのが、母子手帳・保険証・医療証です。
長女の初めてのインフルエンザは帰省先ででしたし、子供はどこで何があるか分からないので、常にカバンに入れておくべきだと感じています。
まとめ
今回は、4歳と4カ月というタイミングでの帰省でしたが、来年の同じ時期に帰省するとなると、次女はもう歩き出していると思われます。
そして2年後は、イヤイヤ期に突入。
先のことを考えると、ワンオペ帰省の難易度は今よりも高くなっていくかもしれません。。
子供の成長に合わせて準備や持ち物を見直していく必要がありそうです。
ただ、とにかく寝かせて、退屈させない方法を探るという方向性は変わらないと思うので、子供たちのリズムと新幹線の自由席のタイミングを上手く見計らって、少しでも楽に帰れるように今後も知恵を絞っていこうと思います。
新幹線で帰省をする方、大きな声を出したり走りだそうとする子供をなだめたり、ずっとデッキに立ちっぱなしになったりと途中で心が折れそうになるときもありますが、頑張って目的地を目指しましょう。