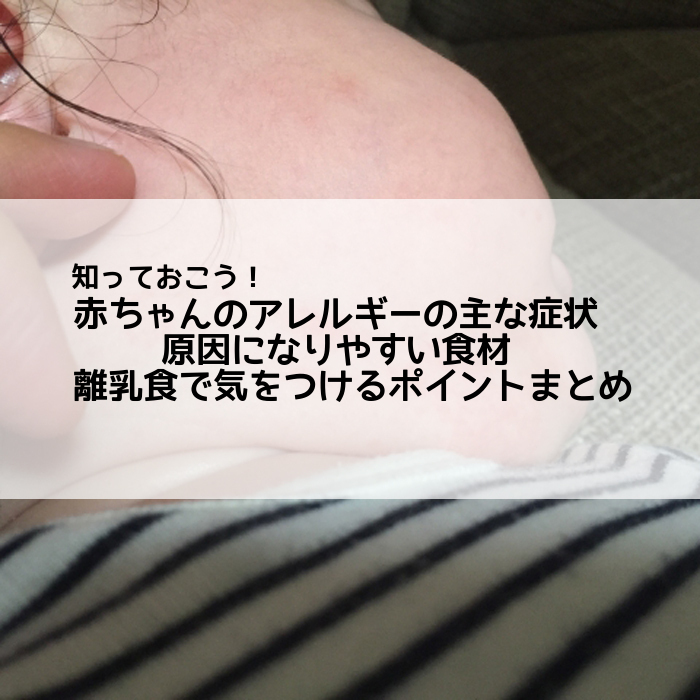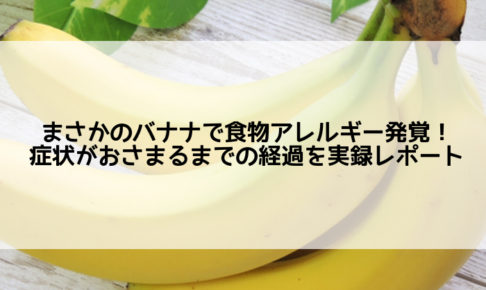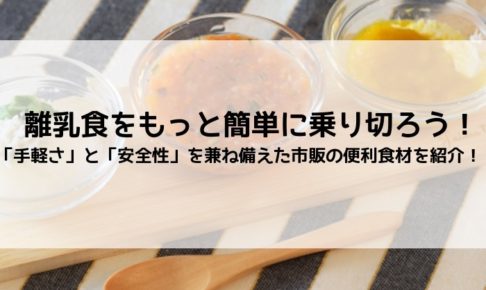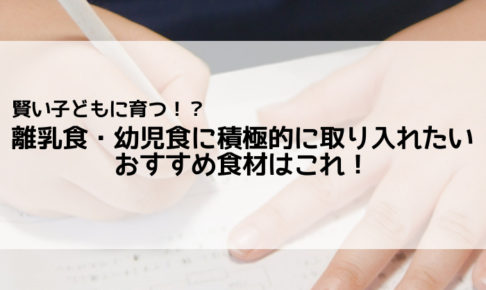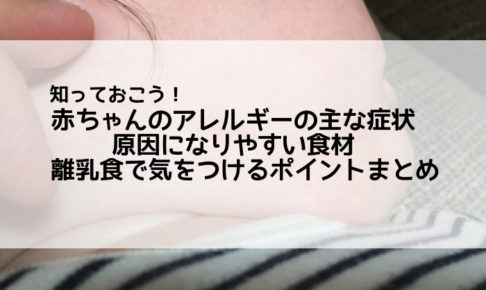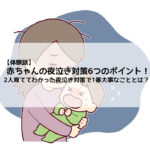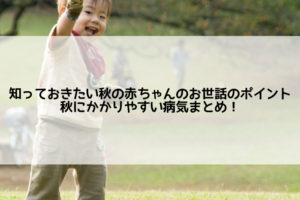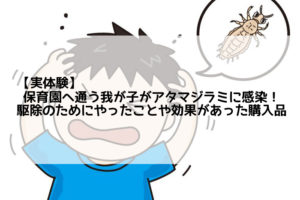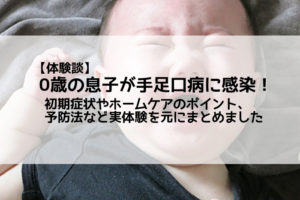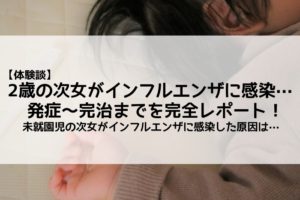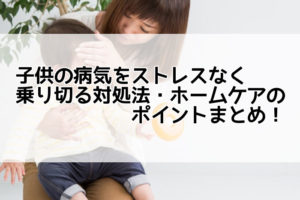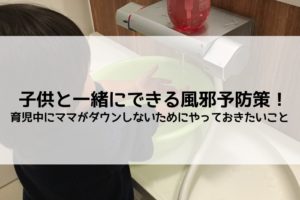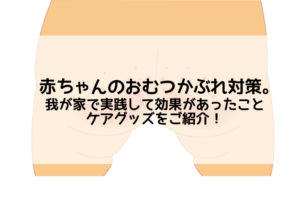美奈ママ
最新記事 by 美奈ママ (全て見る)
- 赤ちゃんの歯磨きのやり方まとめ!ガーゼ磨きの方法、歯磨きを楽しい時間にするためのコツも紹介します - 2017年9月27日
- 【体験談】コープデリは本当に子育てママにとって便利?私が入会して感じたメリット、デメリットをまとめてみました。 - 2017年9月25日
- 赤ちゃんに起こりやすい不慮の事故まとめ!対処法・対策を知って、事故を未然に防ごう! - 2017年9月22日
ママテク(@mamateku)ライターの美奈ママです。
赤ちゃん時にかかりやすい病気の1つ、食物アレルギーとアトピー性皮膚炎。
赤ちゃんに急にぽつぽつと赤い湿疹が出たり、下痢になったりせき込んだりするとママは心配になりますよね。もしかするとアレルギーが原因かもしれません。
赤ちゃんは体も小さいため、受けることができない検査もあり、アレルギーが原因なのか他の原因からくるものなのか、判断が難しいこともあります。
そこで今回は、食物アレルギーについてご紹介します。
急にアレルギー症状が出たら不安になると思いますが、症状や原因、対処法を知ることで、症状が軽くなる可能性も高いです。
成長と共に症状が改善されることも多いので、一人で悩まずお医者さんに相談しながら乗り越えましょう。
パッと読むための目次
アレルギーってなに?
私たち人は、体に侵入してきた異物やバイ菌を見つけて攻撃・排除する防御機能が備わっています。これを「免疫」といいます。
免疫は、外から侵入した異物を見つけて記憶し異物と戦うための「抗体」をつくります。
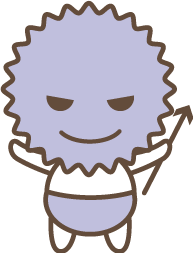
ところが、人間にとって大きな害ではないものにも「抗体」が作られてしまうことがあります。
抗体は、異物が侵入してきたとき、かゆみや鼻水、下痢、呼吸困難などの症状を引き起こします。
【スポンサードサーチ】
この抗体によって、アトピー性皮膚炎や食物アレルギーといった、アレルギー反応が出てしまいます。
赤ちゃんにはなぜアレルギーが多いの?
赤ちゃんに多いアレルギーは、食物アレルギーとアトピー性皮膚炎です。
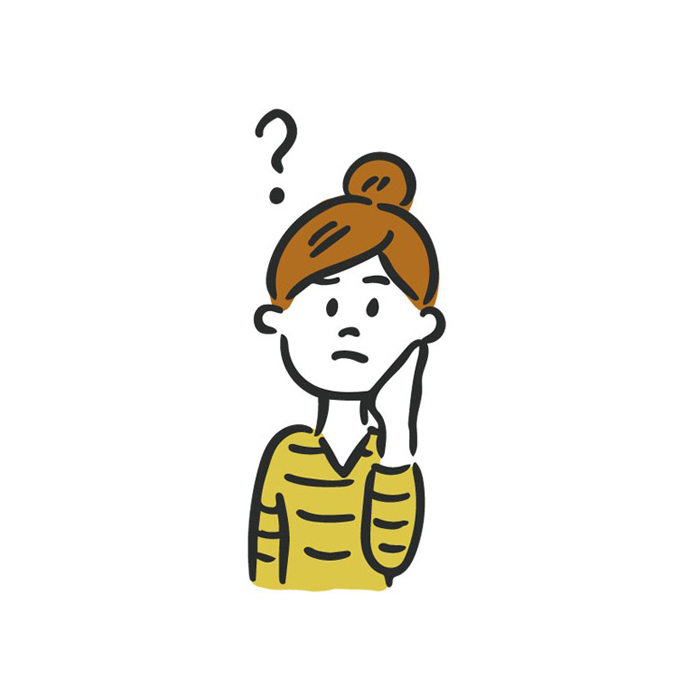
と思われるかもしれません。
赤ちゃんは食物を消化する機能が未熟なためといわれています。また、赤ちゃんの皮膚はとってもデリケート。有害なものから体を守る機能も低いことが関係しています。

成長するにつれて消化機能が発達したり、皮膚が丈夫になったりすることで、アレルギーが改善されることもよくあります。
ただ、近年は赤ちゃんのアレルギー発症が増える傾向にあります。実際に私の周りにもアレルギーを持っている赤ちゃんや子どもがたくさんいます。
アレルギーの症状とは?
アレルギー症状が出る原因となるものをアレルゲンといいます。
アレルゲンは多くの種類がありますが、代表的なものとして、卵や牛乳、小麦粉などのタンパク質、花粉、カビ、ハウスダスト、ダニ、ペットの毛などがあります。
アレルゲンに反応してしまうと以下の症状が現れます。
- アトピー性皮膚炎
- 気管支喘息
- 食物アレルギー
- 鼻炎、花粉症、結膜炎
など
アレルギーは遺伝するの?
親がアレルギーを持っている場合、子どももアレルギーになる可能性は高いといわれています。
ただ、それだけが原因ではなく赤ちゃん本人のもともとの免疫機能や発育状況、周囲の環境などの要素なども複合的に合わさって、アレルギー症状が出ます。
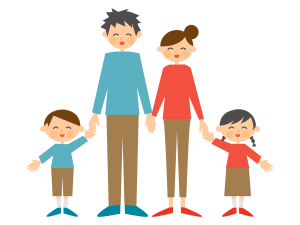
私はそばアレルギーを持っていますが、上の子もやはりそばアレルギーだと判明しました。

自分がアレルギー持ちなので遺伝するのかなと思っていましたが、やはり、遺伝要因も大きいのかもしれませんね。
それでは、赤ちゃんに特に発症が多いといわれる、食物アレルギーについて更に詳しく見ていきましょう。
乳幼児期に特に多いアレルゲンは?
初めて離乳食を食べさせるときは
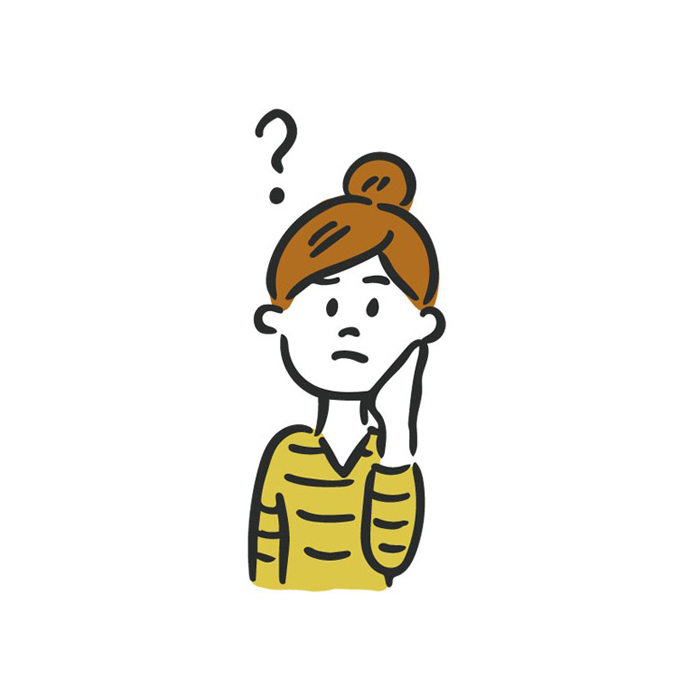
実際食物アレルギーは、10人に1人の赤ちゃんが持っているといわれています。特に生後1歳までがもっとも多く発症します。
私自身もアレルギー持ちなので、子どもに新しい食材を試すときは、心配でたまりませんでした。
赤ちゃんの食物アレルギーの原因となるもので多いのが卵で、次に牛乳、小麦です。9割をこの3大アレルゲンで占めています。
1歳を過ぎると、魚や魚卵も加わります。詳しく見ていきましょう
卵

一番アレルギーを起こしやすい食品です。
「卵白」がアレルゲンとなることが多いので、卵黄より卵白に気をつけてください。
牛乳

牛乳以外にも、チーズ、ヨーグルトなども可能性があります。
牛乳はよく食材に含まれていることがあるので、しっかりとアレルギー表示を確認しましょう。
小麦

パンやお菓子に使われる普通小麦や強力小麦の他にも、パスタに使用されるデュラム小麦もアレルゲンになります。
食物アレルギーの主な症状とは?
赤ちゃんは消化機能が未熟なので、タンパク質をうまく消化できません。消化できないまま吸収されてしまい、タンパク質がアレルゲンになってしまうことがあるのです。
アレルゲンが全身に運ばれるので、体にさまざまな症状を引き起こします。症状は以下のとおりです。
- 皮膚が赤くなる、湿疹、じんましん、かゆみ
- 呼吸が困難、息が苦しい、咳がでる、のどが詰まった感じがする
- 口の中がかゆい、舌に違和感を感じる、腫れる
- 鼻水が出る、鼻づまり、くしゃみ
- 目が腫れる、充血する
- お腹が痛い、下痢
- 嘔吐
など
症状は皮膚症状がほとんどで、9割近い人に見られます。
私の子どもは、そばをほんの数センチ食べさせただけでしたが、口の中がしびれるような感じで、よだれが出てきました。急に口を開いて閉じなくなったので、びっくりしました。
たった数センチでも症状が出るので、本当に怖いですよね。
これらの症状が出た時は、くわしく記録しておきましょう。
- 離乳食で何を食べたのか、食べた量、料理法など
- 発症した時間
- 症状
- 症状がどのくらい続いたのか
- 同じ食べ物で繰り返されるか
症状が起きているときの写真もあれば、医師に症状を伝えやすいと思いますので、出来れば撮影しておきましょう。
症状が出たらびっくりすると思いますが、症状が一時的で元気そうにしているのであれば、自宅で様子を見るようにしましょう。後日病院を受診すれば大丈夫です。
また、複数の場所で同時に症状がでることを「アナフィラキシー」といいます。
さらに、ぐったりしている、呼吸が苦しそう、血液低下、意識がもうろう…などの症状があると「アナフィラキシーショック」と呼ばれるショック状態に陥っている可能性があり、危険ですのでアナフィラキシーショックが出た場合には、すぐに受診しましょう。
母乳やミルクでも症状がでる?
食物アレルギーは直接赤ちゃんが口にしたものだけとは限りません。ママが食べたものをとおして、赤ちゃんの身体に入ってアレルギー反応が出ている可能性もあります。
母乳やミルクでアレルギー症状が出た場合には、ママの食べたもの(母乳の場合)、飲んでからどの位の時間で症状が現れたのかなどを記録して病院に行きましょう。

また、ミルクでアレルギーが出た場合は、ミルクの使用をやめてアレルギー用のミルクを使用することになります。こちらは必ず医師に相談して使用するようにしましょう。
離乳食のすすめ方で注意すること
(1)加熱しよう
赤ちゃんに初めての食材を食べさせるときは、加熱すると「低アレルゲン化」しますので、必ず加熱してあげるようにしましょう。火を通すか、レンジでチンするといいですね。
ただし、魚介類や豆類など、火を通してもあまり変わらない食材もあります。

また新しいものを食べさせるときは、1日に1品ずつにして、食べた後の様子を注意深く観察しましょう。いろいろと混ぜてしまうと、アレルギー症状が出た原因を特定しにくくなります。
「うどんに溶いた卵を混ぜるとバランスがいい!」と思っても、まずは1品ずつ。
初めてのものを食べるときは万が一の場合、すぐに病院へ行けるように平日の午前中にしましょう。
(2)離乳食開始を遅らせるといい?
赤ちゃんのうちは消化機能が未熟なので、「だったら離乳食の開始を遅らせばいいのかな?」と思いますよね。
でも、赤ちゃんの成長に必要な栄養やエネルギーは増えていきますので、離乳食開始は遅らせないで、5から6ヶ月になったらスタートさせましょう。

また、自分で「卵は危険だからあげないでおこう!」と判断しないようにしましょう。自己判断で食べさせないでおくと、それにより成長を妨げる可能性があります。
元気な体をつくるために、アレルギーを怖がりすぎず、まんべんなく食材を与えてあげるようにしましょうね。
(3)3大アレルゲンの食べさせ方
卵
離乳食を開始するときは、卵は特に気を付けたいですね。
私も上の子の離乳食開始のときは、本当に一口目は慎重に怖々とあげたのを覚えています。離乳食開始時期は、いろいろと気を使いますよね。

市販のベビーフードやおやつには、卵が使われている場合があります。「ボーロを食べたら、急にぶつぶつが出てきた!」というママもいます。
離乳食で卵が安全とわかるまでは、卵が使われているベビーフードは食べさせないようにしましょう。
7から8ヶ月になったら、よく加熱したゆで卵の卵黄だけを与えます。卵白にはアレルギーの原因となるたんぱく質が含まれているので、まずは卵黄から開始しましょう。
量は1g程から開始して、少しずつ増やしていくといいですね。
全卵を与えるのは、卵黄が食べられるとわかってから、1か月たった後にしましょう。こちらもしっかりと火をとおして、与えたあとは赤ちゃんの様子を見守ってあげてください。
卵は栄養価が高くて、調理も簡単で幅広いので、ママも食べさせやすい食材ですよね。危険だからあげないでおこうと思わずに、アレルギー反応が出なければ、離乳食メニューに是非取り入れたいですね。
小麦
6から7ヶ月で開始しましょう。
パンには牛乳や卵も含まれている可能性が高いので、うどんやそうめんからチャレンジしてみましょう。
しっかりとやわらかくなるまで煮込んでから、2センチほどからためしてみましょう。

牛乳
ミルクを問題なく飲んできた赤ちゃんなら、アレルギーの心配はありません。
母乳だけで育ってきた子どもなら、5から6ヶ月頃に、粉ミルク少量でチャレンジしてみましょう。

また、牛乳だけでなく、チーズ・ヨーグルトなどの乳製品に対してもアレルギー症状が出る場合がありますので、使用する場合は注意しましょう。
そばやピーナッツといった重症化しやすい食品は、開始時期を1歳すぎてからにしましょう。
私の子どもは私がそばアレルギーということもあり、アレルギーの可能性が高いことが予想されたので、そばは3歳前にあげました。「やっぱり出た!」という思いでしたね。
またピーナッツは、まちがって気管支に入ることで肺炎の原因になります。アレルギーの心配もありますので、3歳ごろまでは与えないようにしましょう。
いつも食べているのに突然アレルギーが出た
以前は食べても問題なかったものでも、アレルギー症状が出る場合がありますので、注意しましょう。

体調が悪くてアレルギーが出る
体の免疫や抵抗力が落ちているときは、アレルギーを発症しやすくなります。
調理の仕方によって出る
特に卵はしっかりと火を通すようにしましょう。
うどんなどに卵を流し入れる場合は、しっかりと火が通っているか確認してから出してあげてください。
実は軽いアレルギー反応が起こっていた
アレルギー症状が軽かったため、アレルギーと気づかないで過ごしている場合もあります。
あせもやニキビなどの湿疹と思って、離乳食に出し続けている場合もありますので、特定の食材を食べた時に湿疹がよく出る場合は、アレルギーを疑ってみることが大事といえます。
アレルギーの診断はどうやってするの?
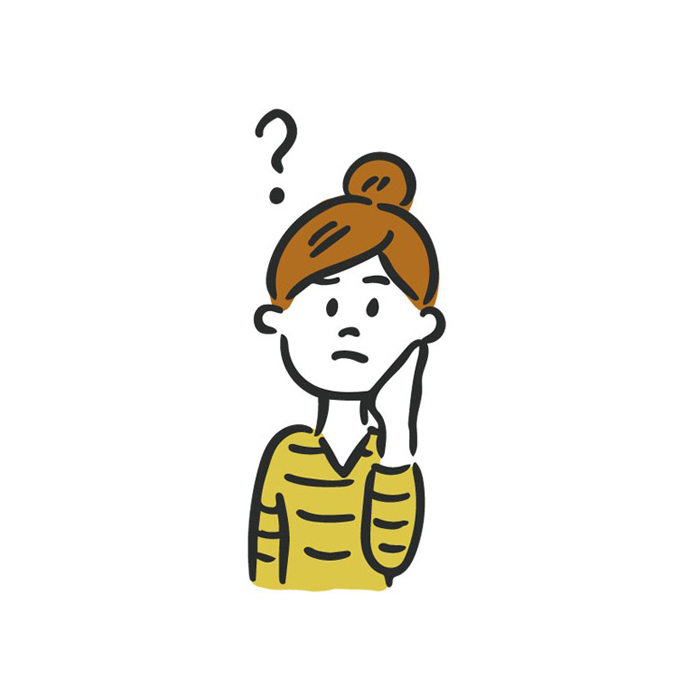
検査は、以下の通りです。

血液検査
抗体がどれくらいあるか調べます。数値が高い程アレルギーの可能性が高いです。
私の子どもはこの血液検査をして、そばアレルギーだと確定しました。
数値はそれ程高くなかったのですが、「数値が高くなくても、そばは少量で重症化する恐れがある」と言われました。
皮膚プリックテスト
皮膚に食品から出たエキスをたらして、皮膚の症状の変化を見るテストです。
除去テスト
疑わしいアレルゲンを食べないことで、症状が改善するかを調べるテストです。
負荷テスト
疑わしいアレルゲンを少しずつ食べさせることで変化を見るテストです。アレルゲンの影響により、どのくらいの症状が現れるかを正確に知ることができます。
アナフィラキシーが生じる場合があるので、医師の監督下で慎重にすすめることが大事です。
食物アレルギーと診断されたら
食物アレルギーと診断されたら、指示された食品を除去することになります。
医師に相談しながら除去することが大切で、自分の判断で勝手に除去しないようにしましょう。
アレルギーが怖くて、同じものばかり食べてしまうのもNGです。
また、除去する場合は、栄養を別の食品でどうやって補うかも一緒に相談しつつすすめることになります。

乳幼児期に発症した食物アレルギーは、成長するにつれて治ることが多いです。定期的に受診し、除去をしなくていいかどうかの食物負荷試験をおこないます。
これでOKがでれば除去は終了となりますが、試験でアレルギーが継続して出るようであれば、引き続き除去しながら食事をすすめていくことになります。
あらかじめアレルギー検査をしたい
離乳食をはじめる前に
- どの食品でアレルギーが出るかわからない
- アレルギーが出たら怖い
などの理由で、あらかじめアレルギー検査をしたい方もいるかもしれません。
どうしてもという場合は、生後6か月前後からすることができますが、以下の理由から事前の検査をすすめない場合もあります。
- 赤ちゃんの血管が細く、うまく針が刺さらず時間がかかるため、赤ちゃんにとって負担になる
- アレルギー検査で陽性でも、必ずしも症状が出るわけではなく、食べても大丈夫な場合もある
- 消化器官が未発達という原因で陽性になったとしても、いずれは治るものも多い
- 陰性の結果がでたけれど、実際食べたら症状が出た
アレルギー診断は、実際に症状が出て検査結果と合わせて行うことが大切です。
離乳食前に心配しすぎて、検査しなければと悩むのではなく、1日に耳かき一杯程度の少量ずつ正しく離乳食をはじめるようにしましょうね。
ただ、両親が重いアレルギーを持っている、母乳育児でアレルギー症状が出ていたなどの場合は事前検査しておいた方がいい場合もあるので、医師に相談してみてくださいね。
まとめ
いかがでしたか。乳児期に多い食物アレルギーについて、離乳食の進め方と合わせてご紹介しました。
食物アレルギーは、成長とともに治ることが多い病気です。
あまり心配しすぎずに、まずは初めての食材は、1日1品少量から始めてみましょう。お子さんの様子を注意深く観察して、アレルギー反応が出たら医師に相談してみてください。
私も、自分がアレルギー持ちだったので、離乳食をはじめるのが怖くて、ドキドキしました。
でも、離乳食を遅らせたり、排除しすぎたりすると、体の成長に必要な栄養やエネルギーが不足してしまいます。不安になりすぎずに正しく離乳食をすすめて行きましょうね。