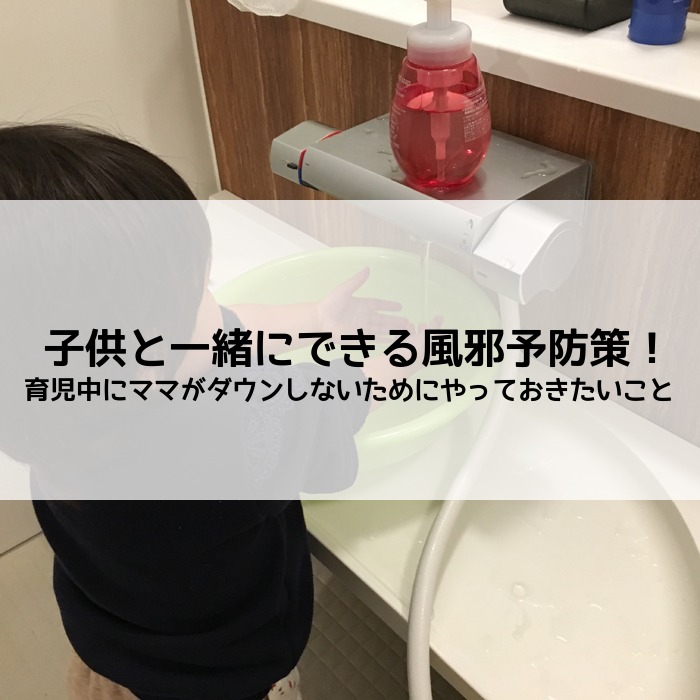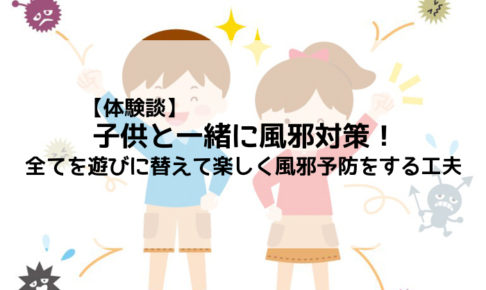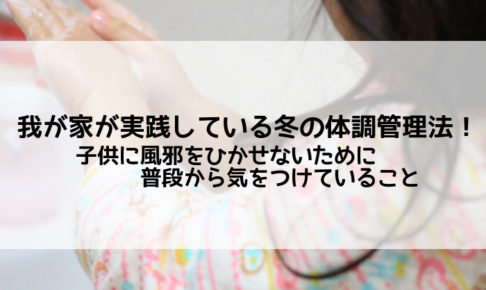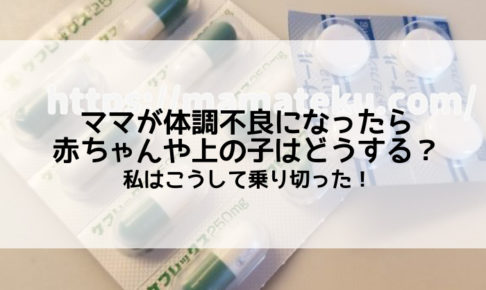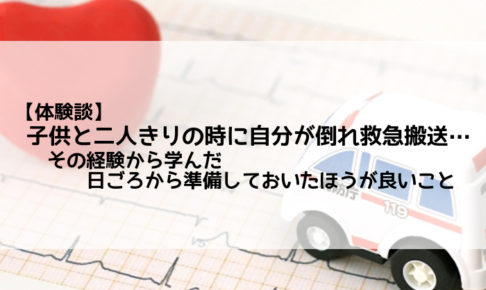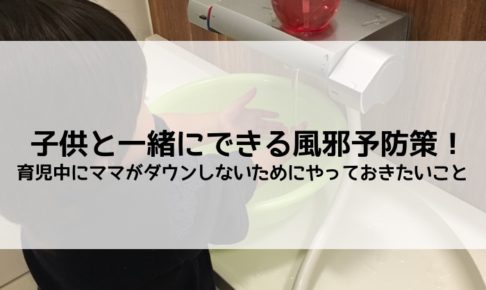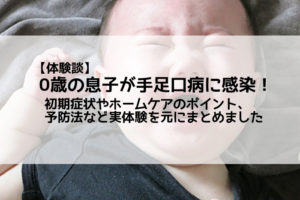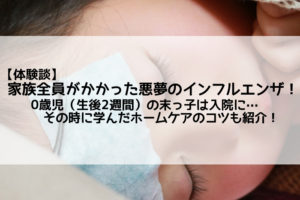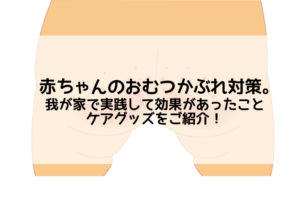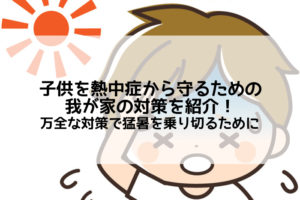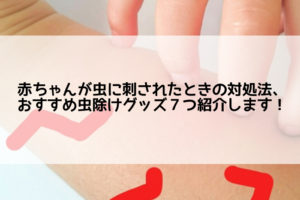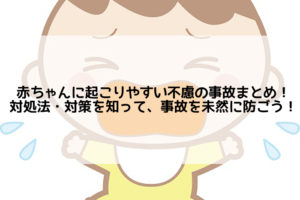Meow-Meow
最新記事 by Meow-Meow (全て見る)
- 妊娠が分かったらやるべきこと。受診の目安や手続きの流れ、周りへ報告するときに気をつけることなどまとめました - 2019年4月26日
- 【妊娠超初期~臨月まで】つわり、便秘、眠気…妊娠中の「つらい」を乗りきる方法まとめ - 2019年3月11日
- サイズアウトした子ども服・ベビー服はどうする?「捨てない」わが家の活用法6つ - 2019年2月27日
ママテク(@mamateku)ライターのMeow-Meowです。
寒い季節になると、子どもはどこからか風邪をもらってきます。
鼻水をたらすだけならまだしも、本人が高熱を出したり、ママやパパにも移り一家全員でダウンしてしまうことも。
わが家では寒くなったとたんに、筆者やパパが風邪で2~3日寝込むということが続きました。
幸いにもわが子本人はいたって元気なのですが、あるとき運悪くパパの仕事の激務とタイミングが重なってしまい、筆者は39℃の高熱のなかでわが子の世話をひとりでこなさなければならない状況に陥りました。
これは地獄を見るかのようなつらさでした。
そこで二度とこのような事態になるのを防ぐべく、風邪予防策を考案して実践することにしたので、みなさんにも共有したいと思います。
パッと読むための目次
【体験談】地獄の「39℃の高熱でワンオペ育児」
「ママがダウンするとどうなるか」という一例として、まず、そのときのエピソードをお話ししたいと思います。
風邪気味だけど、パパを会社へ送り出し…
わが子が生後10か月のときでした。
前日から「なんだかのどが痛いなあ」と思いながら、その日の朝、体温を測ると37℃と少し高め。
朝食も食べられたし、この程度の微熱なら大丈夫だと思い、パパをいつものように見送りました。
このとき、パパはいつになく仕事が忙しい時期で、クリエイター的な職種なので普段は時間の調節は比較的自由がきくのですが、このときばかりは帰宅が深夜に及ぶ日が続いていました。
【スポンサードサーチ】
『今週が山場だ』と言っていたので、パパの仕事をよく知っている筆者としては簡単には「休んで」とは言えませんでした。
すると、お昼前あたりから、全身がだるく熱っぽくなってきました。
体温を測ると、38.5℃。今朝からずいぶん上がっています。

「お腹すいた」とぐずるわが子を見ながら、筆者は絶望的な思いでした。
寝かしつけは放棄
生後10か月というと、
- 朝昼晩3回の寝かしつけ
- ミルクと離乳食の用意
- まだつかまり立ちしかできず長くひとり遊びもできない
という時期です。
お昼ごはんには早い時間でしたが、冷凍してあった離乳食を温めて食べさせてからミルクをあげ、自分も休みたかったので、11時頃、早々にわが子を2階の寝室へ連れていきました。
布団で横になりながら目をつむっていると、わが子は上に乗ってきたり、叩いてきたりします。
困ったことにまだまだ寝る気配はありません。
相手をすることもできず、自分も休まらないため、わが子に悪いと思いながらも寝かしつけを放棄して部屋を出ることにしました。
ベビーモニター任せ
わが家は寝室にベビーモニターを設置しています。
このとき筆者は1階に布団を敷いて横になりながら、モニターでわが子の様子を見ていました。
たくさんおもちゃを置いてきたので、わが子は布団でごろごろしながらひとりで遊んでいるようでした。

このころは、眠くなった頃合いで「おやすみ」と言って部屋を出れば、ひとりで寝てくれる日もあった時期だったので、泣いてしまうこともありましたが、そのうち寝るだろうなと思っていました。
しかしこの日はなかなか寝る気配はなく、30分が経過した時点で筆者のほうが先に寝てしまいました。
6時間も放置…わが子は?
次に起きたとき、モニターを見るとわが子は寝ていました。
泣けばモニターから声が聞こえるはずなので、遊びながら眠りについてくれたようでした。

2時間近く経っていましたが、わが子がいつ眠ったのかはわかりません。
筆者は全身に汗をかいていて、足元もふわふわとしていました。
体温を測ると、なんと39℃!
ふらふらしながら着替えを取りに2階に行って、わが子がすやすや寝ていることを自分の目でも確かめ、水分補給と市販の薬を飲み、再び布団に横になりました。
次に目覚めたのは、わが子の声でした。
また2時間ほど経っていましたが、わが子はいつの間にか起きて、またひとりで声を出しながら遊んでいるようでした。
迎えに行くべきだと思うのですが、39℃から熱が下がらない身体は石のように重くて動けず、横になったままうとうとしては目覚めてをくり返していました。
とうとうわが子が泣き出したのは、寝室に置いてきてから6時間も経ったころでした。
たまらず、パパにSOS!
お昼過ぎに起きたときにパパにはメールを入れておいたのですが、まだ読んでいないようでした。
職種上、スマホを携帯できないときも多いのです。
緊急の場合は会社に電話することになっています。
わが子を1階に連れてきたのはいいけど、相手なんてできません。
高熱のため、頭痛と全身の関節痛がひどく、息も苦しい…。
お風呂に入れることも、ご飯を食べさせる気力もありません。
温めた蒸しパンとミルクを用意してあげましたが、少し食べてからわが子はぐずりっぱなしです。
座り込んだまま、涙を浮かべてこちらを見ていますが、どうしようもありません。

このままではパパの深夜帰宅まで持ちこたえられないと思い、携帯に電話をかけてみました。
すると

パパが帰ってきたのはそれから2時間後。
わが子は泣き続け、筆者は意識もうろうとしていました。
わが子のためにも、自分がダウンすることは避けなければならないなと実感しました。
育児中は風邪を引きやすいのはなぜ?
筆者は大人になってから、ほとんど風邪というものを引いたことがありませんでした。
しかし産後は寒くなると、大げさではなく、隔週で風邪を引いていました。
ちょうど同じときにママになった友人も、これと似たようなことを言っていたことから、育児中はどうしても風邪を引きやすいのではないかと筆者は思います。
筆者の場合は、これには2つの原因があると考えられます。
- 妊娠・出産を経て体力が落ちたこと
- 子どものたくさん集まる場所に出かけるようになったこと
それまで「除菌」「アルコール消毒」などにはあまり神経質ではなかった筆者ですが、これは本格的に予防しなければ…と思い始めました。
一人暮らしの独身時代にたまに風邪を引くと、何もかも自分でやらなければならなくて

しかし、子育て中に風邪を引くと、それ以上の孤独を感じることに驚きました。
パパや実家に頼ることができればいいのですが、実家が遠くパパも仕事を休めないとなると、自分のこともままならないような状態で、わが子の世話までしなくてはなりません。
子どもの風邪予防はもちろんのことですが、ママ自身の体調管理も必要不可欠なのだと思い知らされました。
感染しやすいところは?
筆者はまず、「どこから風邪をもらってくるのか」という点に注目してみました。
小さな子どもがいるわけですから、人ごみや通勤電車に乗るわけでもなく、行く場所はそれほど多くありません。
具合が悪くなる前にどこへ行ったのかを思い出せれば、おのずと感染場所が見えてくるのではないかと考えたのです。
保育園、支援センターなど、子どもの集まる場所
思い返すと、“のどが痛くなる”という兆候が出る前には、ほとんど必ずといっていいほど児童館や支援センターに行っていました。
また、わが子は週1で一時保育に預けているため、わが子がウイルスをもらってきているのでは…?と疑いました。
ショッピングセンターなどの人ごみ
買い物やキッズスペースでわが子を遊ばせるため、ショッピングセンターに長時間いたときは帰り道でのどが痛くなり、やはり熱が出ました。

筆者は、水を飲むことも忘れて買い物やわが子の遊びに付き合っていたので、のどが乾燥でやられたところに風邪のウイルスのパンチをくらったのではないかと思っています。
このことから、
- 人がたくさん集まる場所
- 子どもがたくさんいる場所
- 暖房で乾燥している
このようなキーワードに当てはまる場所は注意したいものです。
風邪予防法1.うがい、手洗い
「うがい、手洗い」が風邪予防に効果的であることは知られています。

外出すると、ドアノブやおもちゃなど、いろいろなものに手が触れます。
風邪予防だけではなく、食中毒やほかの感染症予防にもなるため、外から帰ったらまず手洗いをするようにしています。
うがいは、口の中に侵入した細菌やウイルスを洗い流す効果があります。
風邪の多くは空気感染と言われていますので、手洗いとともにうがいをすることで予防効果は高まると思います。
子どもの手洗い、うがいをうまくさせる方法は?
わが子は1歳半過ぎですが、まだ洗面所まで手が届かないため、こんな風にお風呂場で洗わせています。
- シャワーではなく、蛇口の下に洗面器を置き、水を出す(そのまま水を出すとびしょびしょになるので)
- わが子の手に泡ハンドソープを出し、「あわあわ、ごしごし」と言いながら洗う
- 洗面器の中でじゃぶじゃぶ
- 最後に蛇口からの水できれいに流す
手で泡立てる必要のない、泡ハンドソープがおすすめです。
うがいは現在練習中です。
何でもマネをしたがる時期なので、筆者が「がらがらがら~」とお手本を見せるとマネをしています。
口の中をゆすぐだけでも効果があると思うので、そろそろうがいも実践させようかなと思っています。
風邪予防法2.帰ったら着替え
手洗い、うがいと同様の目的で、筆者は外から帰ったら着ていた服を脱ぎます。
毎回ではありませんが、とくに児童館や保育園など、たくさんの子どもが集まるような場所へ行ったあとは、そのときに着ていた服を着替えるようにしています。
ずぼらな筆者は、帰宅が夕方になれば、そのままお風呂に直行します。
そうすると、うがい・手洗い・着替えが一度に済んで一石三鳥なのです。
風邪予防法3.こまめに水分補給
理由はさまざまですが、風邪予防には「水分補給が大事」といわれています。

筆者も外出時には必ず水筒を持って行き、わが子にもストローマグを持たせて、意識的に水を飲むようにしています。
筆者が考える理由は3つあります。
- 冬はのどの渇きを感じにくいが、知らず知らずのうちに暖房や乾燥した空気で水分が失われていると感じるから
- 口の中やのどの粘膜が乾燥すると、免疫力が低下するため
- うがいの代わり
暖房の利いた部屋に長時間いると、のどが痛くなってくることがあります。
そんな状況では、ウイルスが身体に侵入することを許してしまい、風邪を引きやすくなります。
定期的に水分補給し、のどを潤すことが大事ではないかと思います。
また、胃へ入ったウイルスは胃酸であっけなく退治されてしまうそうなので、外出中はうがいの代わりにこまめに水を飲むというのも合理的でしょう。
特に支援センターやショッピングセンターなど、たくさん人がいる中に長時間いるときは、意識的に水分補給をするということを心掛けるといいと思います。
風邪予防法4.子どもの遊び場には長時間居ないようにする

暖かい季節は週2~3回、お弁当を持って児童館や子どもの広場(室内遊び場)などに行っていましたが、冬場は行く回数も時間も大幅に削減されました。
前述したように、このような場所が感染源になっている可能性が高いからです。
とはいえ「行かない」となると、ただでさえ遊ぶ場所が少ない季節に、さらに選択肢を減らしてしまうことになります。
そこで冬場にこういった施設へ遊びに行く場合には、次のことに気をつけるようにしています。
- 1時間程度で切り上げる
- お弁当を持って行かない
- 帰ったら、うがい、手洗い、着替えをする
風邪予防法5.果物でビタミン摂取
風邪予防にはビタミンを摂ることも効果的だといわれています。
わが子は果物が好きなので、冬場でも積極的に食べさせるようにしています。

たとえば、グレープフルーツは冷蔵庫に常備していて、食後にむいて家族で食べています。
みかんは箱で買い、毎日のように食べています。
真冬には店頭でもあまり見かけなくなりますが、秋の終わりごろまではキウイもまだまだ買えたのでよく食べていました。
ビタミン入りのジュースや野菜ジュースも良さそうですが、筆者は次の理由から健康のために飲むことはしていません。
- 糖分が高い
- 加熱処理しているので、ビタミンなどの栄養素がそのまま残っているとは限らない
したがって、「栄養を摂るため」「健康のため」にこういったジュースを飲ませるのではなく、わが家はおやつやごほうびとして子どもに飲ませています。
風邪予防法6.加湿する
わが家では、2台の加湿器を使っています。
昼間過ごすリビングと、夜寝るとき用に寝室にも置いてあります。

乾燥は大敵です。
その理由は、上にも書きましたが、
- のどが乾燥していると、免疫力が弱まること
- 空気が乾燥していると、風邪のウイルスが活動的になること
大手空調メーカーのDAIKIN公式サイトによると、快適な湿度は50%くらいだそう。
こちらに加湿と風邪予防について、かわいいイラストで分かりやすく説明されています。
どんな加湿器を使えばいい?
加湿器には大きく分けて3種類あります。
- 加熱式
- 超音波式
- 気化式
昔ながらの加湿器ですが、熱を使うため電気代がけっこうかかるところがネックです。
ただ、加熱殺菌されるので、衛生的には安心して使えるのかなと思います。
超音波式とは、熱を使わず超音波で水をミストに替えます。
2,000円前後~とお手軽な価格で購入でき、メンテナンスも楽ですが、ミストの粒が比較的大きいため、筆者は加湿器のまわりがびしょびしょになった経験があります。
また、ミストが部屋全体に行きわたりにくく、加湿器のまわりにあるカーテンにカビが発生したという話も聞きます。
筆者は気化式をおすすめします。
じゃばらになったフィルターが水を吸い上げ、そこに風をあてることで気化させるという仕組みです。
電気代も安く、ミストが出ないので加湿のしすぎにならず、加湿器から出る風で部屋全体をまんべんなく加湿することができます。
デメリットは、
- 加湿器本体が高価なこと(5,000円~2万円くらい)
- 風の音がうるさく感じる人もいるということ
- フィルターの掃除がめんどうなこと
おすすめの加湿器は?
筆者が使っているのは、こちらになります。
リビングは大容量、寝室は音が静かなものを選びました。
信頼できるメーカーであり、電器屋さんではどちらもロングセラーの売れ筋商品なので、フィルターやパッキンなど消耗品を買い替える際もなくなる心配がない、というのも選んだ理由のひとつでした。
まとめ
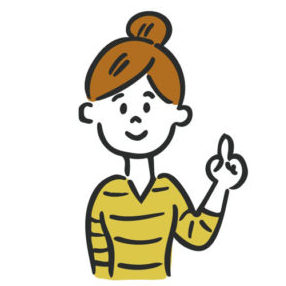
筆者も、妊娠中はお腹の中の赤ちゃんを守るために感染症には神経質になっていましたが、子どもが産まれてからは自分の身体にまで気が回りませんでした。
しかし、体力の落ちている産後こそ、育児中の身だからこそ、ママにもぜひ予防をしてほしいと思います。
子どもが児童館や保育園で風邪をもらってくるのは仕方のないことですが、それをほかの家族にうつさないようにする、自分自身が感染源にならないようにするという対策が大事なのかなと思います。