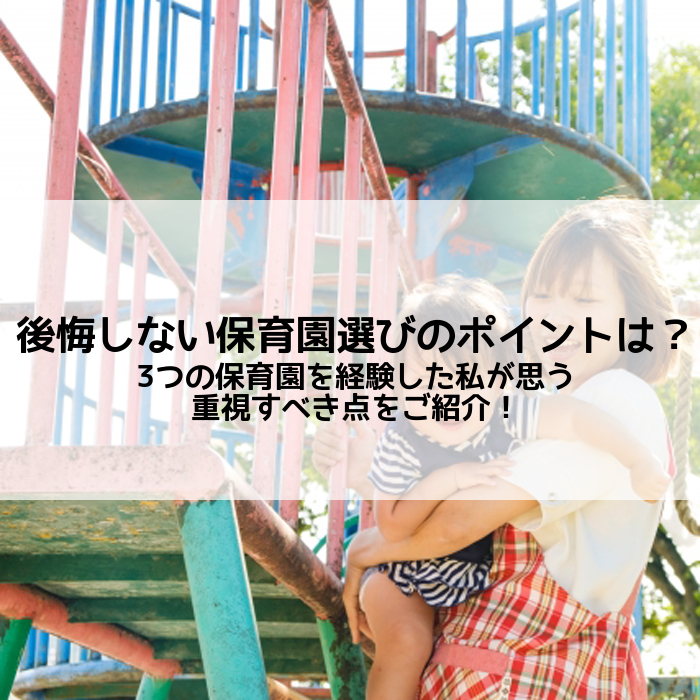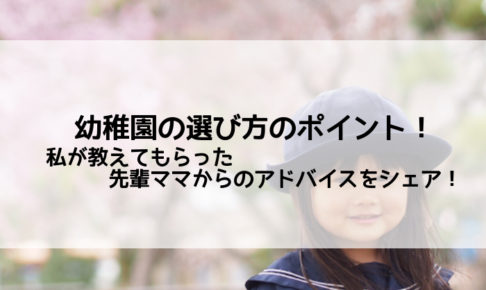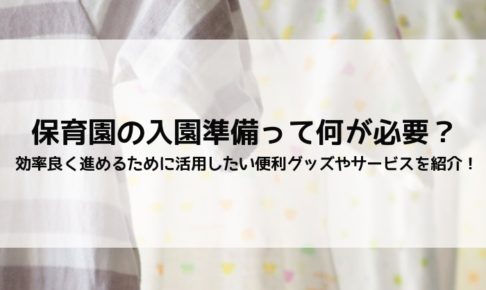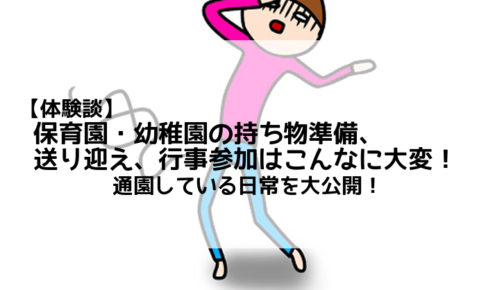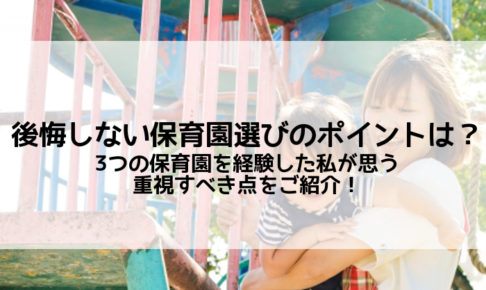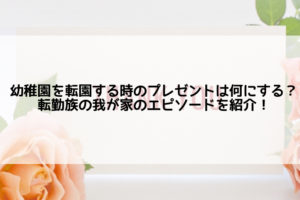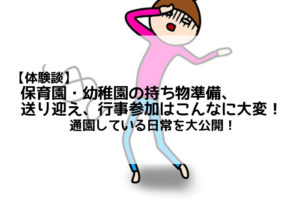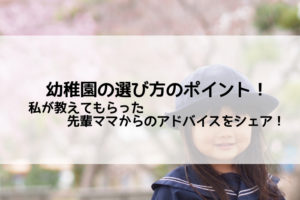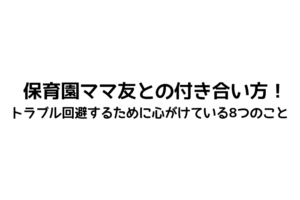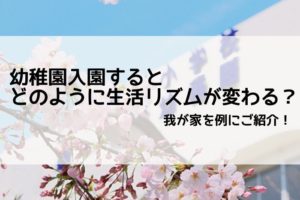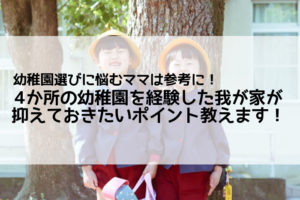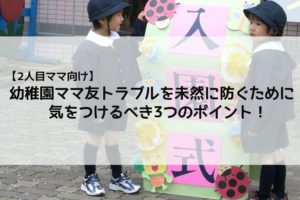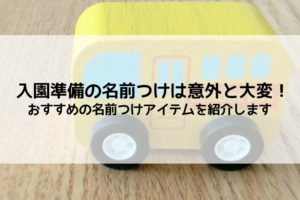ののかママ
最新記事 by ののかママ (全て見る)
- 保育園入園が決まったけど寂しい…。保育園に預けることへの葛藤、私はこう乗り越えました! - 2018年12月31日
- ひらがなの勉強はいつから?我が家の場合と実践している練習法をシェアします! - 2018年12月29日
- 我が家流・イクメンパパの育て方!育児に消極的だった夫を変えた4つのポイントをシェア! - 2018年12月26日
ママテク(@mamateku)ライターのののかママです。
夏が終わるとやってくるのが、保育園の申請の季節。
これから保育園にお子さんを預けようと思うお母さんたちも沢山いらっしゃると思います。
そして、日中、大事なお子さんが過ごす場所として、その保育園選びにはとても悩まれるのではないでしょうか。
私自身も、保育園で起こった悲しい事故や腹立たしい事件をニュースで聞くたびに、保育園選びの大切さを身を持って痛感しましたし、保育園選びだけは「決して間違えてはいけない…」と、大きなプレッシャーを背負って毎回保育園選びをしてきました。
実は我が家の場合、現在3歳の娘は親の仕事の都合で、3つ目の保育園に通っているのです。
毎回、新しい街では保育園の選び方にとても悩むのですが、幸いにも今まで行った保育園はどこもとても良い保育園で、今通っている保育園に関しては彼女の保育園生活史上、最高に娘に合っていると思える保育園です。
今回は、これから保育園選びを始めるご家庭に、私の経験上からの保育園選びのポイントと、反省点等をご紹介したいと思います。
パッと読むための目次
1つ目の保育園選びの流れは産休中からスタート
①ネットで収集からスタート
私が最初の保育園情報を集め始めたのは産前休暇を取り始めた頃でした。
産前休暇中はお腹も重く、あまりやることが無かったので、市役所のホームページから住んでいる町の保育園情報を収集しました。
この時、私が気を付けてみたのが、下記の事項でした。
【スポンサードサーチ】
- 受入年齢
- 受入人数
- 保育可能時間
- 保育園の特色・紹介ページ
当時、我が家は引っ越す予定もなく、出来れば就学前までは同じ保育園で過ごさせたいと考えていました。
そのため、何歳から何歳まで受け入れてくれるかはとても大切で、年少・年中・年長の時期の最大の保育可能時間が何時までなのかもとても気になるところでした。
と、いうのも、法律で時短を取らせるように定められているのは3歳までなんです。
それ以降の時短は会社の努力義務であるため、時短が取れなくなることも十分に考えられます。
育児短時間勤務法律
育児・介護休業法の第23条第1条 (勤務時間の短縮等の措置等)
事業主は、その雇用する労働者のうち、その三歳に満たない子を養育する労働者であって育児休業をしていないもの(一日の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるものを除く。)に関して、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の申出に基づき所定労働時間を短縮することにより当該労働者が就業しつつ当該子を養育することを容易にするための措置(以下「所定労働時間の短縮措置」という。)を講じなければならない。第24条(3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置)
事業主は、その雇用する労働者のうち、その3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関して、 育児休業の制度又は勤務時間の短縮等の措置に準じて、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
せっかく保育園に入れても、会社が3歳以降の時短勤務を許可してくれない場合、また改めて保育園を探すか、仕事を探すかしなければいけない可能性が高いので、「3歳になった時点で何時まで預けることが出来るのか」、は私の保育園選びにってとても重要なポイントでした。
また、役所のホームページだけではなく、保育園を運営する会社や保育園自体のホームページも閲覧し、その保育園の保育方針や行事などを調べました。
②実際に保育園に行ってみた
保育園の情報をネットで調べた後は、実際にその保育園に行ってみました。
産休中だったため時間はふんだんにあったので、散歩がてら色んな保育園を見に行きました。
とはいっても、この段階では保育園にアポイントをとり、正式に見学させてもらったりすることを目的としているのではなくて、保育園の外から子どもたちが日中どうやって過ごしているのかを遠くから見てみることが目的でした。
実際にに保育園に行ってみることで、良かったのは場所の把握ができたことです。
実際に家から保育園、保育園から駅までのルートを歩いてみることで、毎日通わせることが本当に出来るのかどうかを把握することができました。
また、大体8時とか9時の間に保育園に行ってみることで、日常の子どもたちの雰囲気が良く分かった事も実際に行ってみてのメリットでした。
何故その時間かというと、9時前位に保育園を遠くから眺めてみると大体一人や二人、お母さんと離れたくない…と泣いている子どもがいて、その泣いている子に対する保育士さんの対応や他の子どもたちの対応がとてもよく分かるからです。

「お母さんと離れたくない!」と泣いていた子が、お母さんの背中が見えなくなった途端けろっとして保育園の先生の手を取って中に入って行ったり、他のお友達と仲良く楽しそうに遊んでいる姿を見ると、単純にお母さんが良いというだけであって、保育園自体は楽しいんだなと思えましたし、実際に自分の子どもがどういう対応をしてもらえるのかもリアルに想像することができました。
また、私が住んでいた場所の近くの保育園は、どの保育園も大体9時とか10時位までは外遊びの時間であることが分かった為、子どもたちの日中の遊び方も見ることができました。
保育園の柵の外から見ていても、お腹が大きかったことで保育園の先生方や子どもたちに怪しまれることもなかったですし、遊び方を見て保育園の保育方針がどういうものなのかを把握することもできました。
③実際に見学に行ってみた
ネットで情報を収集し、アポイント無しで保育園の外から実際に保育園を見た後は、自分の子どもを行かせたいなと思う保育園に電話をして見学の予約を入れたり、夏祭りやバザーなどの予定があれば行きました。
個人的な感想ではありますが、実際に行ってみて私が感じたことをご紹介します(もちろん、其々の保育園や地域により異なる場合も多々あるかと思います)
(1)子どもから話し掛けてくる保育園は保護者の関与がとても多い
保護者が行事などにどんどん関わっている保育園は、子どもたち自身が先生以外の大人と係ることを特別なこととは思っていなくて、ある意味「大人慣れ」をしているように思います。
実際に保育園に行って子どもたちを見てみると、「何しに来たの?」「誰のお母さん?」と好奇心いっぱいの目で質問攻めにあった保育園がいくつかありましたが、話を聞くと行事などの主催は保護者である場合がとても多かったです。
(2)子どもの服の汚れで普段の遊び方が想像できる
保育園に見学に行くと、子どもたちの服の汚れを見て日常の遊び方が把握できました。
綺麗な洋服である場合は遊び方も大人しめなことが多く、顔も服も足も泥だらけの子どもたちが多い場合には遊び方もとてもアクティブなようです。
実際話を聞いてみると、子どもたちの服装の汚れが多ければ多いほど、普段ストックしておく着替えの量も多かったです。
(3)挨拶がきちんと返ってくる保育園にはどんなことも聞けた
保育園に行った際には、会う人全員に挨拶をしてみました。
保育士さんをはじめ、給食室の方、事務員さんに子どもたち。
おはようございます!とかこんにちは~!と声をかけて、しっかりと目を見て返してくれる保育園もあれば、挨拶する事に慣れていないのか返って来ない保育園もありました。
保育園見学に行って聞きたいことが沢山あったのですが、挨拶がきちんと返ってきた保育園は友好的でどんな小さなことにも親身になって答えてくれていたように思います。
反対に挨拶のない保育園は事務員さんも忙しそうだった印象があります。
もちろんただでさえ忙しい業務内に見学させて貰っているのですから仕方ない点もあるのでしょうけれど、結局我が家が選んだのは挨拶がきちんと返ってきた保育園でした。
実際に保育園の見学をしてみることというのは本当に大事で、見学に行ってみるとネット収集や遠くから見るだけでは分からないことがたくさんありました。
そして、我が家の2回目の保育園選びはそれをしなかった為に反省点もありました。
これから保育園を探されるご家庭は出来るだけ見学をしてみることをお奨めします。
また、見学ではなくても検討されている保育園の夏祭りやバザーなど、外部の人も行くことのできる行事があれば参加してみると入ってからの子どもの生活が想像できて保育園選びの参考になると思います。
初めての保育園選び まとめ
産休中にこのようにして保育園の情報を集め、産後直ぐにやってきた11月。4月入園の為の申込期限です。
その時点で我が家の保育園候補は3つにまで絞り込まれていました。
しかし、保育園の申請時に申請書に記載したのはその中の1つだけ。
その当時でまだ娘は生まれて数か月だったため、その保育園が駄目なら1年間復帰を待とうと思っていたのです。
我が家が1回目の保育園を決めるに当たり重視したポイントは下記の3つです。
- 保育園の距離 … 我が家から駅の途中にある保育園だったので一番近かった
- 保育園の保育方針 … 体をしっかりと作ると言う保育方針だった
- 保育園の先生たちの明るさ … いつみてもどの先生も笑顔だった
ダメ元での申請だったにも関わらず、1回目の保育園申請はあっさりと通り、娘は2年半その保育園で楽しい日々を過ごすことができました。
遠方への引っ越しの為、待機児童になった2回目の保育園選び
遠方からの保育園探しでネットの情報だけが頼りに…
2回目の保育園選びは夫の転勤が原因でしたが、遠方からの申請だったためなかなか決まらず、1か月半位、娘は待機児童になりました。
待機児童になった時にどう対処したのかは以下の記事でまとめています。
2回目の保育園申請は、遠方だったことや、実際に事前に新居地に行って保育園を一つ一つ見学する時間が無かったため、ネットでの情報だけが頼りでした。
2回目の保育園探しで重要視したことは『1つ目の保育園と出来るだけ似た保育方針である』こと、そして『家から歩いて通える』ことです。
ガラッと保育方針が変わってしまえば、娘自身が混乱することも多いと思い、なるべく似た環境に預けたかったので保育方針だけは譲れず、また新しい土地で運転をする勇気が無く、「歩いて通えること」は絶対にはずせない条件でした。
そのために新しく住む場所付近の保育園を探し、Googleのストリートビューで建物や周りの雰囲気を確認し、その保育園のホームページやブログなどからどのような保育園生活なのかを徹底的に調べました。
実際に保育園に行ってみたこともありましたが、運悪く保育園が休みの日曜等であることが多く、園庭や保育園の建物を外から見ることしか出来ず、それは少し後で後悔することになります。
そうやってネットで情報を収集し申請した保育園でしたが、第一希望で申請したところは出来たばかりで園舎も綺麗、駅から近いこともあって待機児童数が一番多い保育園でした。
しかし、私が在宅で子どもを見ながら仕事を続けていたこともあって奇跡的に入園許可が下り、娘もその保育園に通うことが出来るようになりました。
保育園見学しなかったことのデメリット
2回目の保育園も、娘は大好きでお友達も沢山出来てとても楽しんでいました。
しかし、実際に見学や話を聞きに行けなかったことでのデメリットも下記の通りありました。
(1)新しく買わなければいけないものが多すぎた
保育園で指定のもの(上履きやエプロン、布団など)が思った以上に有り、前の保育園で使ったものを使うことが出来ず、入園に伴っての出費がとても多かったです。
また、この時点で娘はオムツが外れていたにも関わらず「念の為持って来てください」と紙オムツやおしりふきを持って行かなければならず、結局ムダになってしまいました。
事前に見学に来れていれば分かったことなのに…と少し後悔しました。
(2)保育士さんと娘との相性
これは、どこの保育園に行っても子ども・先生・親各々の性格も有るので相性はあると思います。
また、慣れるまでの時間も必要であると思います。
しかし、普段の園生活では特に大きな問題はなかったものの、ところどころで娘と保育士さんたちとの相性があるなとは感じていました。
実際にどんな保育士さんたちが働いているのかを事前に把握できなかったので、慣れるまで少し時間が掛かりました。
(3)給食の質
2回目の保育園は給食を外部委託している保育園でした。
1度目の保育園が完全に園で手作りだったため、食べ慣れないものが多く、お昼ご飯をほとんど食べないこともあったようです。
食事やおやつは保育園生活の楽しみの一つですから、事前に知っておきたかったことでした。
(4)保育費以外の費用
新しい保育園では保育費以外の費用(布団乾燥費や父母の会会費等)も結構ありましたし、写真などの値段も前の保育園と異なっていたので最初は戸惑いました。
ネットなどの情報だけでは足りないことが思いのほかたくさんあることを実際に入ってみてから痛感しました。
また、2度目の保育園に関しては、行事などに親の協力を求められることはなくとても楽でしたが、その分先生たちの負担が大きいのか進級する際には娘の担任だった先生たちは全員辞めてしまい、他のクラスの先生たちも何人か辞めたそうで、出入りがとても激しいように思いました。
実際通わせてみても、先生たちの仲という部分では情報が共用されていなかったり、あまり親しそうな雰囲気はなかったり、新しい保育園だからかもしれませんが連携が上手く取れているようには決して思えませんでした。
新しい保育園は建物が綺麗・設備が整っている等というメリットがある半面で、先生たちのチームワークという点では、長年一緒に働いているような保育園よりかは物足りないのかなと思います。
2度目の保育園選びの反省点が活きた!3回目の保育園探し
2度目の保育園にやっと娘が慣れ始めた頃、我が家はまた夫の仕事の都合で保育園を探さなければならない状態となりました。
今回も保育園は遠方からの申請です。
私の会社は在宅での勤務が出来るので、フルタイム勤務であることは引っ越しても変わりません。
3度目の保育園探しは、2度目の経験がとても活きた結果になったと思います。
まず先手必勝と、夫に転勤の内示が出た時点で早々に保育園選びに動き始めました。
情報収集、そして今回は費用がかかってもやむを得ない…と、新しく住みたい街に仕事を休んで出かけ、市役所で話しを聞きに行き、保育園の見学もいくつか行きました。
疑問がある事はその都度電話をして保育園に問い合わせました。
住みたい地域のいくつかの町の保育園をいくつか見て回り、行かせたい保育園が決まるとその保育園のある街に家を探し、家の契約が決まった途端申し込みをしました。
今回の引っ越しは完全に保育園ありき、で決めています。
そして、今回一番気にしていたのはやはり保育方針でしたが、今回は保育設備にもこだわりを持っていました。
ここで言う設備というのは、綺麗な建物というわけではなくて、広い園庭や遊具類・園庭にある畑などです。

今回なぜ、保育園選びで設備を重要視したかというと、物心つかない0歳や2歳のころと比べ娘も3歳になり、出来ることも増え、好きなことや嫌いなことがはっきりしてきたためです。
前回・前々回と保育園の庭は割と狭かったので、いつもパワフルに体を動かしている我が家の娘には少し物足りない気がしました。
広い庭が有るような保育園は駅から離れていることが多いのですが、今回は駅から離れていても思う存分走り回れるような保育園を申請しました。
申請のときにはこの保育園に入れたいからこの町へ引っ越したと言う申請理由を付けました。
そして無事、入園許可が下りたのですが、子どもの足では毎日片道徒歩25分の距離は結構大変であるものの、娘の体は引き締まり保育園では思う存分遊んでいてとても楽しそうです。
行事への親の参加は多いのでその都度大変ですが、親も先生たちと接する事がとても多いので、先生たちの人となりも分かり、安心して預けることが出来ます。
保育園任せにせず親も保育活動にどんどん係っていくと言うスタイルは我が家に合っているようです。
まとめ
働くお母さんたちにとって、働いている間子どもを見ていてもらえる保育園はとても大事な場所で、その選定にはとても悩みますよね。
私の3回の保育園選びの経験から言えることは、
- 下調べと見学をしっかり行うこと
- 0歳や1歳の今だけを基準に選ぶのではなく、子どもや自分自身の性格や時短後の勤務状況を考慮しながら、半年後・1年後の成長を見据えて選定した方が良い
保育園選びはかなり大変な作業ではありますが、子どもにとって良い選択になるように頑張って下さい。