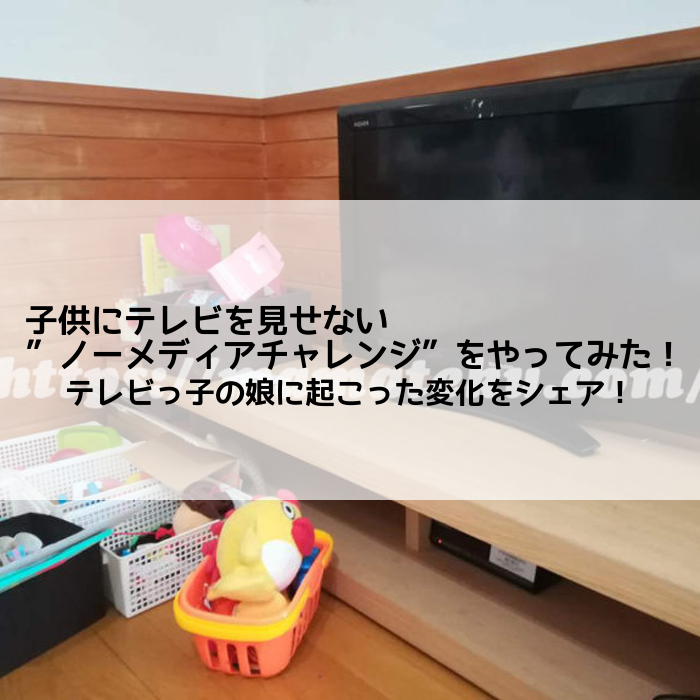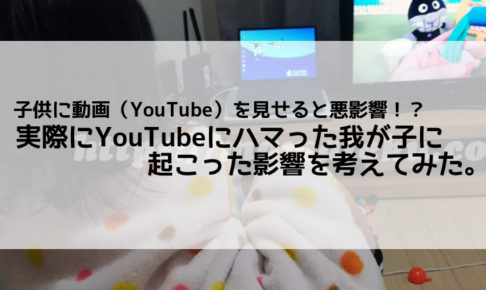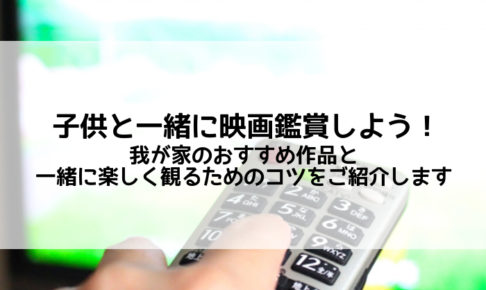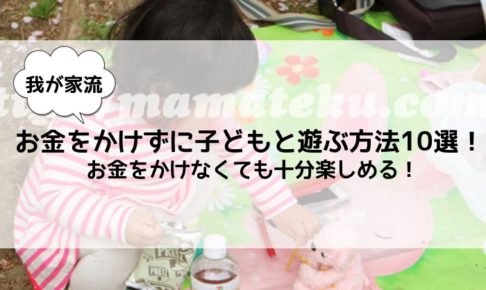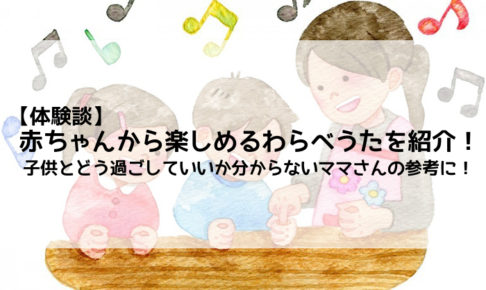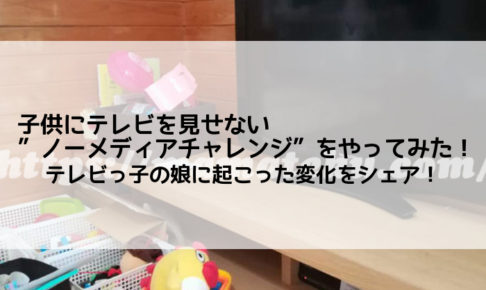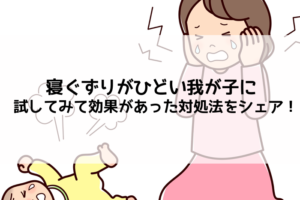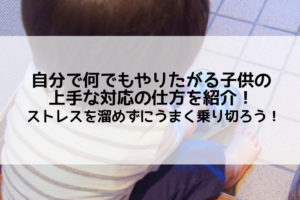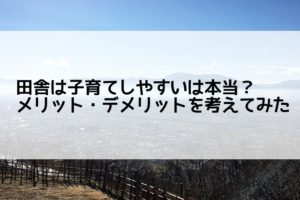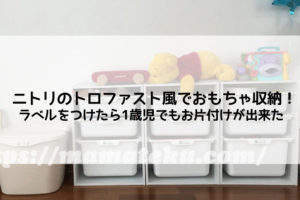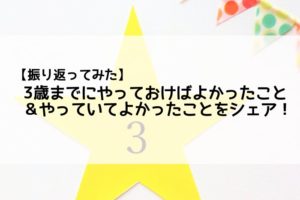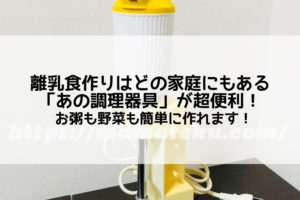せっきーママ
最新記事 by せっきーママ (全て見る)
- 【神奈川県・川崎市周辺】子連れおすすめお出かけスポットを紹介!元地元民ならではな穴場スポットも! - 2018年11月5日
- 子供にテレビを見せない”ノーメディアチャレンジ”をやってみた!テレビっ子の娘に起こった変化をシェア! - 2018年10月12日
- 3歳児のリアルなお手伝い事情をシェア!お手伝いの内容や大事にしているポイントなどを紹介! - 2018年9月8日
ママテク(@mamateku)ライターのせっきーママです。
あなたは子どもに一日どれくらいテレビやYouTubeなどのメディアを見せていますか?
我が家では多いときでは、一日5時間近く子どもにメディアを視聴させていたことがありました(過去記事でも書いています)
しかし、そのメディアの長時間の視聴が原因かどうかは定かではありませんが、保育園で娘が他者間とのコミュニケーションがうまく取れないということが最近発覚。
そこでその問題を改善するべく、テレビの視聴時間を制限することを思い立ちました。
テレビの視聴時間をなくす「ノーメディアチャレンジ」というものを家で実行し、実際に娘がどのように変わっていったかなどの体験談を皆さんとシェアしたいと思います。
パッと読むための目次
きっかけは保育園の先生からの一言
現在、娘は3歳で昼間は保育園に通っています。
年少のクラスにも慣れてきたころ、担任の先生からこんなことを言われました。
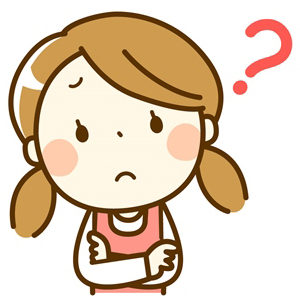
このときわたしはとてもショックを受けました。
家ではそんなことが全くなく、普通に会話もできるし受け答えもできていたからです。
他にも、先生から
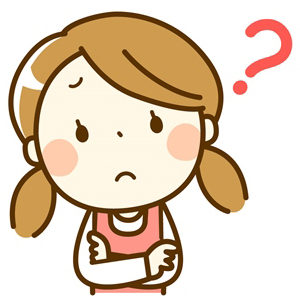
そこから、どうしてこんなにお家と保育園で差が出てきてしまったんだろう…と思い、日常生活を振り返ってみることにしました。
【スポンサードサーチ】
テレビなどのメディアの視聴時間が長いから?
以前、保育園に行く前に娘が『どうしてもドラえもんの映画が見たい』と言ってきたので、出かけるまで見せてから保育園に行きました。
そのことをクラスの担任の先生に話すと「いつもテレビや動画を結構見てるんですか?」と聞かれ、「休日の午前中とかはずっと見てますね…」と答えると

できればもっと〇〇ちゃんとやり取りをする時間を1日の中で増やしてみてください
と言われてしまいました。
教育現場に立つ保育士さんがこんな風に言うくらいなら、やはり子どもに対してメディアへの接し方は改めたほういいんだと思いつつも、自分も助かるからと、ついつい子どもをメディア漬けにしてしまっていたことに対して後悔が生まれました。
もちろん娘自身の生まれつきの特性もあり、他者とのコミュニケーションや受け答えがうまくいかない理由のすべてがテレビやメディアの視聴というわけではないと思います。
しかしこれが何かのきっかけにでもなればと思い、以前から長引きつつあったメディアの視聴時間をこの際減らしてみよう!と、この時ようやく決心しました。
『テレビに子育てをまかせていませんか?』という本との出会い

図書館でお目当ての本を探しているときに、何気なく他の棚に目をやると衝撃的なタイトルの本が目に入ってきました。
それが『テレビに子育てをまかせていませんか?』というタイトルの本。
「これ、わたしのことだ…」と思い、見た瞬間即行で手に取りました(笑)
この本では、テレビやビデオ、テレビゲームなどが子どもの身体面からメンタルまで及ぼす悪影響や弊害について書かれています。
ちなみにこの本が出版されたのが2004年なので、スマホやYoutubeなどのインターネットメディアは広く普及していない時代です。
テレビの部分をスマホであったりYoutubeなどの動画やDVDに置き換えると、今子育てしているすべての親が「自分のことだ…」と間違いなく思うはずです。

中でも目を引いた「ノーメディアチャレンジ」のコーナー
本の前半ではざっくりいうと、このようなことが書かれています。
- 最近の子どもは疲れやすく、弱い身体になってきている
- 感情のコントロールができなくなってきている
- 夜遅くまでメディア漬けのせいで睡眠不足になり、色んなところで影響が出ている
その中でも、『少年犯罪やいじめも、メディアが子どもたちの遊びの時間を奪ったから?』などという、少々行き過ぎじゃないかという内容も書かれていました。
よくある「今の子はダメだ」的な内容か…と半ば失望して本を読むのをやめようとしてペラペラとページをめくっていると、ノーメディアチャレンジという見慣れない文字が目に入ってきました。
ノーメディアチャレンジとは?

ノーメディアチャレンジは、一定の期間中テレビなどのメディアを一切遮断すること。
この本の中には、6日間のノーメディアチャレンジを実施した家族の体験談がいくつも書かれています。
この本の中でのノーメディアチャレンジのルールは以下の通りでした。
- この6日間は、テレビ、ビデオ、ゲーム、パソコンなどのメディアはすべてオフにして過ごします。家庭の外でもメディアでの遊びは禁止です。
- 親の生活に必要がある場合、ラジオはOKです。
- トランプ、ボードゲーム、かるたやすごろくなど、伝統的な遊びなら何をやってもOK。
- 読書はOK。ただし、マンガ本以外。
体験談の中では、6日間のうち一回も子どもにメディアを見せないことに成功した家族もいれば、子どもがグズってしまったため泣く泣くテレビをつけてしまい、結局1日も成功する日がなかった家族など様々で、読んでいてとても興味深い内容でした。
我が家でもノーメディアチャレンジ!
そこでうちでも試しにやってみようと思い、ノーメディアチャレンジを実施してみることにしました。
我が家でのルールは以下のように設定しました。
- 基本的に朝も夕方もテレビをつけない
- 映画は長時間の視聴につながるので見せない
- 見たいと言ってどうしてもきかなくなったら見せる(でもなるべく短時間)
- 自分が苦しくなったら即やめる
本に書かれていたものから比べるとだいぶゆる~い設定にしていますが、あまりガチガチに決めてしまうと自分も子どもも大変なので、とりあえずお試し!ということであえてルーズに設定しました(笑)
テレビを消して娘はこんなに変わった!
朝の保育園に行くまでの支度がスムーズになった
今までは何気なくつけていた朝のEテレをシャットダウン。
そうすることで、ごはんもぼーっとしながら食べていたのが、わたしと会話を交えながらあまりダラダラせず食べてくれるようになりました。
そしてトイレに行ったり着替えをするときも、以前はいくら呼び掛けてもテレビに集中して反応しないことが多くイライラしながら急かしていましたが、今ではびっくりするほど自分から「着替える!」ということが多くなりました。
お着替えのスピードも上がった気がします。
「ママと着替えるの競争しよう!」とわたしから誘うと、一生懸命着替えてくれます(笑)
子どもとの会話が増え、成長や変化に気づけた
以前はテレビを見ている子どもに「今日何して遊んだの~?」と問いかけても「………」と全くの反応ナシで何度も寂しい思いをしました。
しかしテレビを止めたことで子どもと関わる機会がかなり増えました。
当たり前と言えば当たり前なのですが…。
今日あった出来事などもポツポツと断片的にですが喋ってくれるようになり、保育園でどう過ごしているのかがよりわかるようになってきました。

子どもがおもちゃなどで自主的に遊ぶようになった

小さいころからテレビやYouTube漬けで育った娘は、一人で遊ぶことが苦手でした。
そんな娘ですが、テレビを消してよく使うおもちゃだけをリビングスペースに置いてみたところ、見事におもちゃで遊ぶようになってくれました。
もちろん親が相手をしてあげないといけないことがほとんどですが、今までおもちゃで遊べない子だと思っていたのに、テレビを消しただけで劇的に変わってくれてびっくり!
また、おもちゃで遊ぶだけでなくかくれんぼやお絵かきなど、今まではしてこなかった遊びのバリエーションも増えました。
今までできなかった遊びや動作がどんどんできるようになっていくのを日々目の当たりにして、子どもって毎日成長しているんだなと実感しました。
自然とお手伝いしてくれることが増えた
ちょうど保育園から帰ってくる頃は、Eテレで幼児向けの番組だったり、ケーブルテレビのキッズステーションでアンパンマンがやっている時間帯。
帰ってきてテレビの前に即行、そしてしばらくぼーっと見ているということが当たり前だった娘。
しかしテレビを消してからというもの、お菓子を一通り食べると台所で立っているわたしのもとに寄ってきて「お手伝いしたい~」と言うことが増えました。
「テレビを見たい!」というよりも他に何かしたいという気持ちになるんだなぁと思いました。
良い変化ばかりじゃない?ちょっと微妙な変化も…
「一緒に遊ぼ!」が増えて家事が進まない…
テレビを消したことで、「遊び相手」がいなくなってしまった娘は、常に「ママ!あそぼ!」と遊ぶに誘ってくれるようになりました…(^_^;)
子どもと全力で向き合える良い時間ではあるものの、それは家事を一切合切放っておけたらの話。
そんなわたしは夕食作りの時間帯に人形のおままごとに付き合わされています。
ママはリアルな食事作りもしたいんだけどなぁ…(笑)
食べることに興味がいってしまった

夕方はお菓子やらパンやら夕食の食材やら、とにかく何かしらを食べたがるようになってしまいました。
やはりテレビを見れないことでの一種の欲求不満なのかもしれません。
わたしが会社員として働いていた頃も、保育園から帰ってきて夕食を作るときは、テレビとお菓子をセットで渡してわたしは急いで夕食を作るということを1年近くやっていたので、テレビがなくなった今お菓子で欲を満たしているような感じもあります。
逆に食べ過ぎを注意すると今度は「抱っこして」と言ってくるので、ついつい食べ物を与えすぎてしまう自分がいます…。
代わりにスマホでYouTubeを見る時間が増えた

テレビを見せない代わりについついスマホでYouTubeを見せるようになってしまいました…。
娘には今、アナ雪ブームが到来しているのですが(今さら感)、ちょくちょくスマホで動画を見てテレビ変わりに楽しんでいるようです。
見せるときもなるべく子どもと一緒に見るようにして置き去りにしないようにはしていますが、やはり生活の中から完全にメディアを排除するのは難しいなと痛感しています。
それでもやっぱり自分の手が空くからと、ついつい約束した時間を過ぎても見せてしまうというダメ親っぷりを発揮しています…。
保育園で気がかりだった娘のコミュニケーション下手は…
もともと娘が保育園での会話のやり取りや受け答えが苦手ということを発端にして、このノーメディアチャレンジに取り組んでみましたが、その結果、娘が保育園でどう変わったのか。
……それはまだわからないというのが現状です。
状況が劇的に変わるということはまずないと思っていますが、出来るだけ子どもとのコミュニケーションの時間を作ることで少しずつ何かが変わっていくとは思います。
テレビを消して子どもと遊ぶ中で、かくれんぼなどのルールを教えたり、お店屋さんごっこを通してモノを買うやりとりを教えたりと、今まで教えてあげてこなかったことがたくさんあったなと思いました。
もし娘の苦手なことがあったとしても、それをそのままないがしろにするのではなく、きちんと向き合って解決する手立てを示していってやればいいのではないかとも思うようになりました。
ノーメディアチャレンジを実施した感想
テレビを消してみて気づいたこと

ある時、休日のお出かけ前の支度中に子どもがわたしに構ってほしくて「ねーぇー!あそぼー!」と何度も誘ってきてダダをこねているときがありました。
そこでわたしはすかさず「行くまでテレビ見てて!」とつい言ってしまいました。
そこでハッと気が付きました。
テレビや動画などのメディアは、”子ども”ではなく”親”がなくてはならないものだったということを。
忙しいとき、自分がラクをしたいとき、面倒くさいときなどなど…完全に親の都合で子どもにテレビなどを見せていたということを改めて痛感しました。
別に子どもはテレビなんか見なくても平気なんです。
他に遊んでくれる相手がいればテレビも見ずに余裕で一日中遊んでいれられるのです。
メディアなしでは子育てができない時代になっていると感じた
でも、子どもが一人っ子で兄弟がおらず、親が一人で子どもの相手をしている場合、メディアの手助けなしで子育てしていくことは不可能ですよね。
逆にどうやったらメディアなしで子供を育てていけるの!?と半ば反論めいた気持ちにさえなってしまいます。
わたしたちの世代ではスマホやYoutube、テレビなどのメディアは、育児の最強マストアイテムになっていることは間違いありません。
それでもノーメディアチャレンジは是非やってみてほしい
メディアなしでは子育てできないとは思うものの、それでもできるかぎり限り子どもへのメディア視聴を減らした方がいい、というのが今回の体験をしての感想です。
そして是非、気軽な気持ちでいいので家でノーメディアチャレンジをしてみてほしいと思います。
『テレビに子育てをまかせていませんか?』の中でも、テレビを6日間を見ないなんて絶対に無理だ!というお子さんの話が書かれていましたが、実際にやってみると意外となくても大丈夫だったという感想が多く散見されました。
そして、ノーメディアで過ごした期間は兄弟で色々と工夫しながら遊んだり、家族でボードゲームをしたり、いつもと違った時間を過ごせたといいます。
そしてわずか6日間という短い期間でも、子どもが状況に応じて適応していって成長する姿を目の当たりにしたという親の声も多かったです。
わたし自身も、テレビなどのメディアがなければ子どもはどうやって過ごすのか見当もつきませんでした。
しかし、意外とテレビなどのメディアがなくても、その状況に適応して過ごしていて、以前よりも子ども自身のできることが増えたり家族間での関わりが増えたりと、思った以上にプラスな面が多くて驚きました。
テレビを消すことが難しければ、見る時間をできる限り短くするところから始めて、消したあとは家事の手を一旦止めて少しだけでも子どもと一緒に遊んでみてください。
子どもがとても嬉しそうな顔をしてくれること、間違いありませんよ。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
娘の保育園でのことをきっかけに、テレビをなるべく見ないようにするノーメディアチャレンジを通して変化したことや気づいたことなどについて書いてきました。
あなたも気軽な気持ちで子どもが見ているテレビを少しでもいいので思い切って消してみてください。
そうすると思いもしなかった子どもや家族の変化がみられるかもしれませんよ。