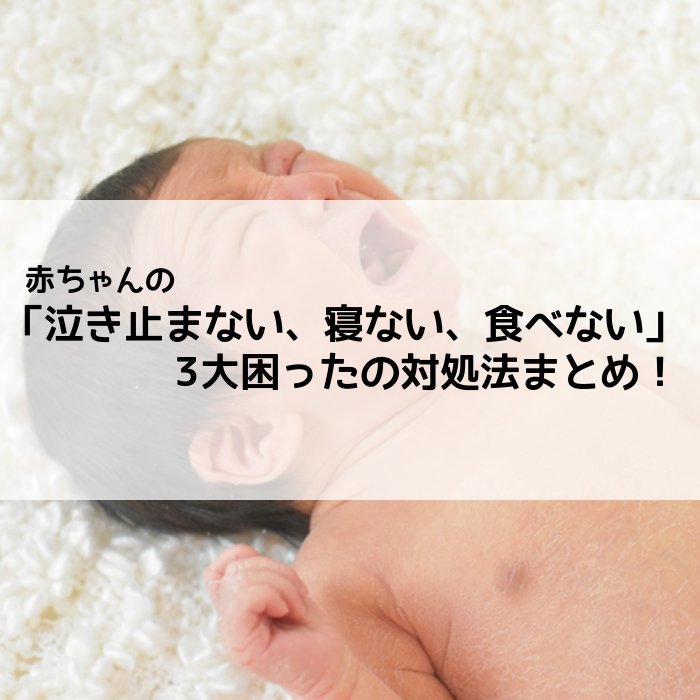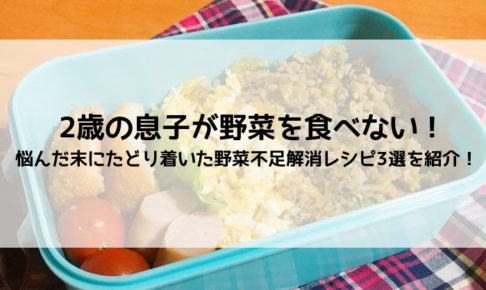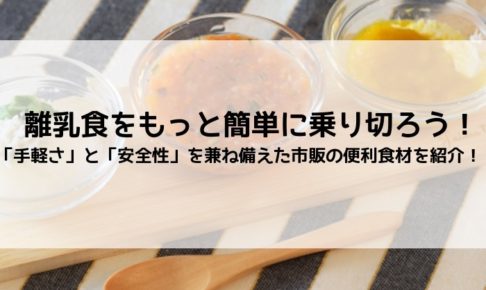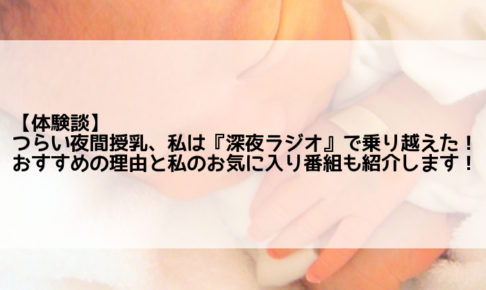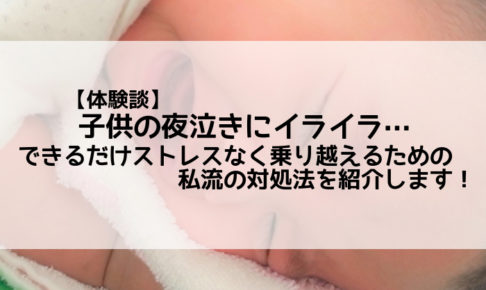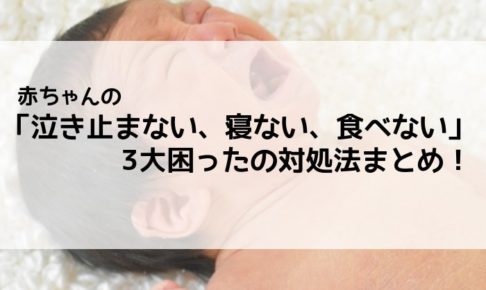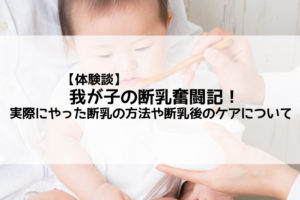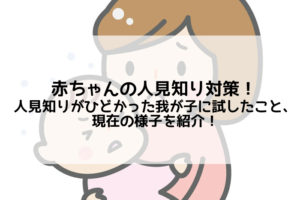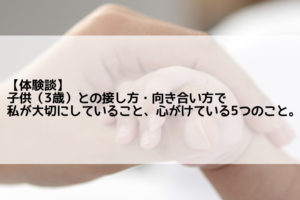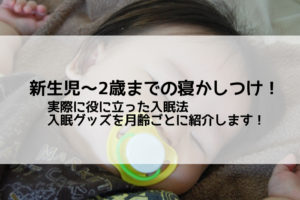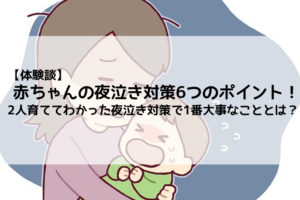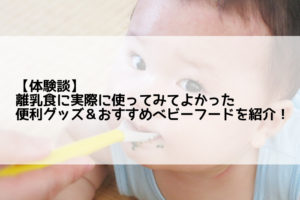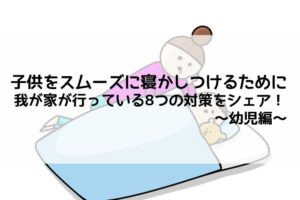Meow-Meow
最新記事 by Meow-Meow (全て見る)
- 妊娠が分かったらやるべきこと。受診の目安や手続きの流れ、周りへ報告するときに気をつけることなどまとめました - 2019年4月26日
- 【妊娠超初期~臨月まで】つわり、便秘、眠気…妊娠中の「つらい」を乗りきる方法まとめ - 2019年3月11日
- サイズアウトした子ども服・ベビー服はどうする?「捨てない」わが家の活用法6つ - 2019年2月27日
ママテク(@mamateku)ライターのMeow-Meowです。
何をやっても泣き止まない…いつまでも寝ない…離乳食を食べてくれない…そんなときってありますよね。
一人きりで赤ちゃんと向き合っているとき、パパを起こさないように真っ暗な部屋で寝かしつけをしているとき。
辛い時間はいつまで続くの?と思ってしまいます。
自我が芽生え始め、ひとり遊びができるようになれば、泣いているだけの時期は終わります。
子どもが巣立つまでの20年を考えれば、この数ヶ月~1年はとても短いですが、その真っ只中にいるときって永遠にも思える時間なんです。
この時期の育児がぐっと楽になるように、筆者が考え実践したアイデアをまとめてみました。毎日頑張っているママの育児が、少しでも楽になりますように。
パッと読むための目次
赤ちゃんが泣きやまない時の対処法
低月齢のうちはこれが一番だと思います。
ミルクもあげた、おむつも替えた、部屋の温度はちょうどいい。なのに抱っこしてもあやしても泣きやまないとなると、どうしていいか分からなくなりますよね。
そんなときは、このようにしてはいかがでしょうか。
赤ちゃんは泣くもの、と割り切ってアテレコしてみる
そうです。赤ちゃんは泣くことでしか伝えられないのです。赤ちゃんなりに何か不満があるのかもしれません。泣き声に合わせて、思いついたものを声に出してみましょう。

【スポンサードサーチ】
例えば、



パパやほかの家族がいるなら、一緒にやってみると楽しくなってきますよ。
そうやっているうちに、「あ、これかも」という泣きの原因が分かるかもしれません。
分からなくても大丈夫です。おむつやミルクが足りているなら「泣きたいだけ」なんだと思います。
赤ちゃんだって一人の人間ですから、そういう気分のときだってきっとあります。
赤ちゃんから離れる
泣き始めてからずっとそばについて抱っこしているなら、いったん離れてみるのも手かもしれません。
泣くと体温が上がりますし、赤ちゃんは暑がりなので、もしかしたらママと密着しているのが少し暑いと感じているときもあるのかも。

ベビーベッドやベビーサークルなど、安全なところに赤ちゃんを寝かせたら、部屋を出てドアを閉めましょう。
そして、甘いドリンクやノンカフェインコーヒーでも飲んで一息つきます。ぼーっと窓の外を眺めたり、テレビをつけてみたり、好きなアーティストの曲を一曲熱唱してみるなんてのもいいですね。
ただし、気を抜きすぎて一休みが長くなりすぎるのは禁物です。赤ちゃんの様子を見ながら実践してみてくださいね。
うちの子は、ママやパパの姿が見えると泣くけど、いなくなると泣き止んで寝ているか遊び始めることがよくあります。
赤ちゃんが泣きやまなくても、ママの気分転換になればまた新鮮な気持ちで赤ちゃんと向き合えるようになりますよ。
泣き顔の写真を撮る
産まれてから今まで何十枚何百枚と写真を撮っていることでしょう。でも、泣き顔の写真はあまりないのでは?
真っ赤な顔して、大きな口を開けて、のどちんこ丸見えで、短い手足をばたばたさせて、泣き顔ってとってもかわいいんですよ。

赤ちゃんが泣き始めるとあわてて抱っこして、なかなかちゃんと見られない人も多いかもしれませんが、泣き顔もじっくり見てあげてください。
スマホでパシャリと写真を撮ってあとで見返すと「こんな可愛い顔で泣いていたんだな」と思うことがあります。
赤ちゃんが寝ない時の対処法
一日に何度も寝かしつけをしなければならない低月齢の頃は、なかなか寝てくれないとイライラしてしまいますよね。
眠そうにしていたりぐずっているのに、いざ寝かしつけをしてもなかなか寝てくれなくて家事ができない。
ずっと抱っこでゆらゆらして、肩や背中が痛い。
筆者も子どもが五か月くらいまでは毎日そうでした。とくに夜の寝ぐずりがひどく、寝かしつけに2~3時間かかる日もありました。
ルールを破ろう!
育児書を読むと、「寝かしつけ」のルールってたくさんありますよね。
筆者もそれにならって、添い乳をするとクセになって卒乳が難しくなるとか、睡眠リズムを覚えさせるために毎日決まった時間に同じ入眠儀式をしなければならないとか、部屋は必ず暗くするなどの固定観念にばかりとらわれていました。

うちの子には抱き枕として産まれたばかりの頃に有名ブランドの『うさぎのぬいぐるみ』を与えたのですが、うちの子はゲームセンターのUFOキャッチャーで取った『ぶたのぬいぐるみ』の方を好んで遊んでいました。
寝るときは両方とも近くに置いていましたが、どちらも抱いて寝ることはなく、ママの枕の角をちゅぱちゅぱしながら寝るのが好きでした(おっぱいだと思ったのかな?)
「ぬいぐるみを抱いて寝ている赤ちゃん」という絵しか思い描いていなかったため、筆者はうちの子にとっては枕ちゅぱちゅぱが「入眠儀式」だと気付くまで時間がかかってしまいました。
その子にとって最適な入眠儀式や寝かしつけの方法は、赤ちゃんが教えてくれるときもあるのです。
パパや他の人に替わってみる

でも、上手い・下手ではないのです。

うちの子がずっと泣き続けて寝ないとき、さすがに疲れたのでパパに替わってもらったとたんに泣き止んで眠ってしまったことがありました。
「パパがいい」とか「ママじゃダメ」とかいうわけではないと思います。
赤ちゃんは惰性でいつまでも泣いているときがあります。抱っこする人が変わるとふと我に返って「あれ、なんで泣いてたんだっけ」と泣き止むのかも。
ひとりにしてみる
ママやパパがそばにいると嬉しくてつい遊んでしまい、寝られないのかもしれません。
もし赤ちゃんが泣いていないのなら、ママは寝かしつけをやめてそっと部屋を出てみましょう。
おもちゃなどに夢中になっている隙に、気付かれないようにそっーと、です。うつぶせ寝が心配な時期は背中まくらを利用するなどして、安全を確保してくださいね。

うちの子も、寝返りができる4~5か月頃になると布団の上でコロコロしてなかなか寝てくれませんでしたが、ある日「もうやーめた。勝手に寝てください」と部屋を出たら、数分後には寝ていました。
それ以来、ママやパパがいると遊んでしまうときは、部屋を真っ暗にしてひとりにさせたほうが寝てくれるようになりました。
あの寝かしつけの苦労は何だったのだろう…と思ってしまいます。
気分転換する
ギャン泣きして寝ない、ベッドに置くと泣く、というときは一人にさせておくのはちょっと不安ですね。
もしかして、まだ眠くないのかも。いやいや、昼寝もあまりしていないし…

そういうときは、興奮して寝付けないのかもしれません。
夕方5時以降まで寝ているなど昼寝をしすぎると夜眠れなくなりますが、筆者の経験では、昼寝をしなさすぎてもうまく夜眠れないことが分かりました。
夜泣きのメカニズムと同じように、昼間受けた刺激により興奮してしまっているのかなと思いました。
赤ちゃんがうまく眠りのスイッチに切り替えられないでいるときは、まず泣き止ませるなどして気分を変えてみましょう。
ちょっとベランダに出て夜風に当たる、歌を歌ったり音楽を聞かせる、おもちゃを握らせるなど。
うちの子は、いったん部屋を明るくして「こちょこちょ遊び」や「飛行機ブーン」をして笑わせると、その後はスムーズに眠るモードに切り替えられることができました。
あくびをしたり、目をこすり始めたら、再び部屋を暗くするとすんなり眠れましたよ。
寝かしつけをやめる

赤ちゃんだって、その日の体調や気分によって眠れるときと眠れないときがあるのだと思います。
そんなときは、「いつも通りに寝かせなければ!」という思いを捨てて、子どものリズムに合わせてみては?

赤ちゃんが一人遊びをしているなら、ママも横で本や雑誌を読む。
ママやパパと遊びたがっているなら、一緒に遊んであげる。
眠くなってくるまで付き合ってあげる!と構えていればいいのです。
「寝かしつけなければ…」「はやく寝てくれないかな」と焦ったりイライラしているのが赤ちゃんに伝わる、というのは本当だと筆者は感じます。
赤ちゃんだって人間ですから、毎日同じようにはいきません。臨機応変に対応できるように、余裕を持つといいと思います。
「眠い」サインを見極める
一番良いのは、赤ちゃんが眠くなるタイミングで寝かしつけをすることです。
赤ちゃんの活動時間は短いので、電池が切れそうになると、そのうち眠そうな仕草を見せるようになります。

その子によってさまざまですが、
- 目や耳をこする
- あくびをする
- 動きが鈍くなり、ぼーっとしている
- 二重になる、まぶたが閉じてくる
- 床やママの服に顔をスリスリする
- 1か所にじっとして、指しゃぶり(タグやヒモをしゃぶっていることも)
- 「あーあー」など同じトーンで声を出す
日ごろから表情や仕草を観察していると、赤ちゃんの「眠い」サインが分かるようになりますよ。
離乳食を食べてくれない時の対処法
5,6か月になると離乳食が始まりますが、はじめは食べムラがあると思います。
筆者も最初におかゆをあげたらすんなり食べてくれたので「よしよし!」と思っていましたが、人参・かぼちゃなどの野菜はにおいや見た目で最初の何回かは拒否。
魚は一口食べてマズイと学習したのかその後は口を開きませんでした。

やっと順調に食べるようになったと思ったら、おかゆを食べて反り返ってギャン泣き…「えっなんで?」と本当に不思議なのですが。離乳食の道は波乱万丈です。
もちろん、はじめからなんでもパクパク食べてくれる子もいると思いますが、もし離乳食でつまずいたら、次に書いたようなことを試してみてください。
いろいろなスプーンを試してみる
うちの子はお気に入りのスプーンがあり、はじめの頃はそれ以外では食べてくれませんでした。
ピジョンの離乳食セットについてきた、白くてスリムなスプーンです。

他にはピンクやグリーンの色がついた、シリコンのスプーンセットを買っていました。少し厚みがあって、丸くて、口の中を傷つけないように柔らかい素材です。
こちらは、まだ小さい赤ちゃんの口には少し大きすぎたのか、スプーンをひらすらカミカミするだけで食べてくれませんでした。
スプーンで遊んでしまう、食べにくそうにしている、食材が口からこぼれてしまう…などというときは、スプーンがその子に合っていないのかもしれません。
赤ちゃんに合うスプーン、食べさせやすいスプーンをいろいろ探してみるのもいいですよ。
食材をなめらかにする
赤ちゃんが初めての食材を嫌がる理由として、味より食感だという話もあります。
うちの子も七ヵ月になったときにトロトロだった食材から少し粒を残したものに変えてあげてみたら、見事にギャン泣き。
口の中に粒が残っているのが嫌なのか、吐き出す仕草を見せていました。

どうしても食感が残ってしまいがちなのは、魚・葉野菜・枝豆や豆腐です。
毎回入念に裏ごしをするのは大変。ブレンダーやミキサーで作って、冷凍しておきたいですよね。
そういうときは、赤ちゃんが大好きでなめらかな食材(おかゆ・バナナ・大根・ヨーグルトなど)と混ぜ合わせてあげたり、お湯でのばしてとろみをつけるといいと思います。
わが子は、魚+大根、豆類+バナナ+ヨーグルトのメニューが好きでしたよ。
大人と一緒の時間に食べる
一昔前はベビーフードなんてわざわざ作らず、大人が噛み砕いたものを口うつしで与えていた時代もありました。
さすがに口うつしは虫歯になる危険性があるので今はご法度ですが、大人と一緒に食卓を囲むという習慣は、赤ちゃんにとっても良いと感じます。
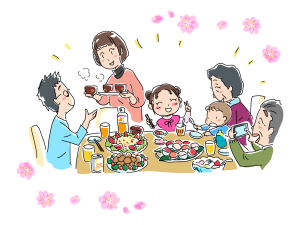
筆者もはじめの頃は、パパが出勤して家事もひととおり終わった10時ごろにあげていました。
朝は何かと忙しく、午後になると万一アレルギー症状が出たときに病院が閉まっている場合があるからです。
しかし二回食になるとき、ママとパパの食事のタイミングと同じ、朝と昼にあげるようにしました。すると、大人たちが食べているのを見てニコニコして、ご機嫌でパクパク食べるようになったのです。
自分たちの食事の用意だけでも大変ですが、慣れれば工夫しだいで同じタイミングでの食事のほうが楽だと感じるようになります。
たとえば、お味噌汁の豆腐やお刺身、トーストのパンなど大人の食事から少し取り分けて、レンジでチンしたり軽くすりつぶししたりして離乳食にする。冷凍ストックを解凍するだけ。などなど。
大人と同じタイミングでの食事だと、パパが離乳食をあげられますし、たくさんのメリットがあります。アレルギーが心配ならはじめての食材は朝にあげるといいでしょう。
離乳食をひと休みする
離乳食は、きちんと毎日決まった時間に同じ量をあげなければいけないと思っていませんか?
初めての子育てで、雑誌やインターネットなど育児書からの情報を頼りにしていた筆者もそう思っていました。
しかしある日、三人の子を持つママである友人とファミレスに行ったときのこと。
うちの子には、出かける前に時間を気にしつつ急いでドロドロのおかゆ、ベビーフードを食べさせてから行きました。
友人も同じくらいの月齢の子を連れていたのですが、彼女はランチセットについていたスープを薄めて子どもに飲ませ、ハンバーグの付けあわせの人参やじゃがいもをつぶして食べさせ、デザートのヨーグルトやフルーツもソースをよけてあげていました。


友人はこれまでそうやって上の二人を立派に育てているのです。目からうろこが落ちた気がしました。
それから、うちも気楽に行こうと思えました。
もし、離乳食をはじめたばかりであまり食べてくれないときは、まだ時期じゃないのかも。
順調にいっていたのに急に食べなくなったときは、離乳食にちょっと疲れたのかも。

そういうときは、ひと休みしてみてもいいと思います。
大人の食事を見て食べたそうにしていたら「今日はどうかな?」と少しあげてみたり、ご機嫌なときにベビーダノンなどのヨーグルトを食べさせてみたり。
その子なりのペースで進めてみてくださいね。
まとめ
子どもが成長するにつれ、一つ悩みが解決したかと思うと、また一つ別の試練が待ち受けています。そのときどきで違う大変さがあるのですね。
でも、ひとつひとつできることが増えると、今まで子育てをがんばってきたかいがあったなと思うのです。
何もかも育児書どおりに、きっちり管理するのではなく、日常のリズムは意識しながらもそれぞれの赤ちゃんのペースに合わせるのが一番ストレスなくできる方法だと筆者は感じます。
こんなに子どもと触れ合えるのも今のうちだけです。できるだけ楽に、楽しく子育てができたらいいですよね。