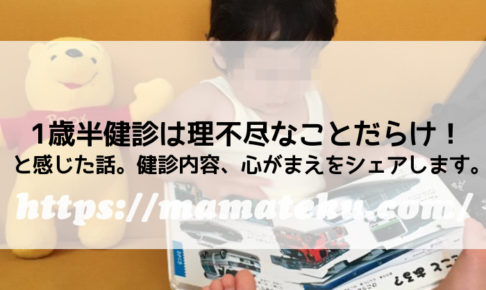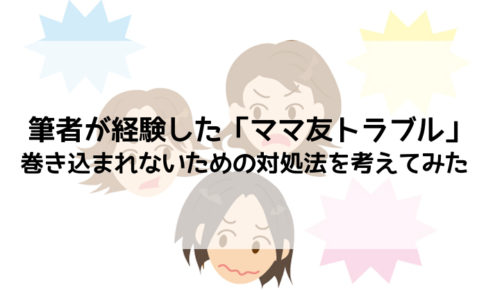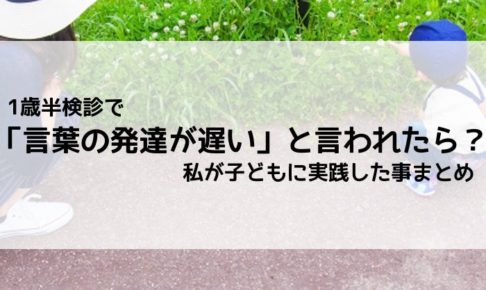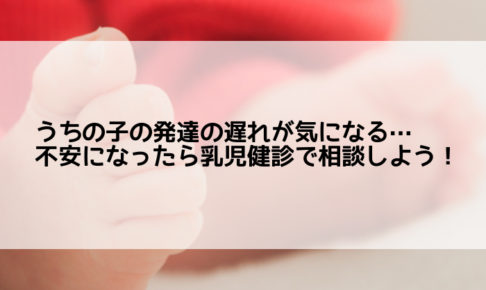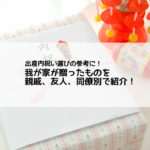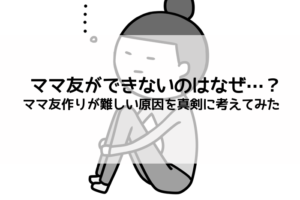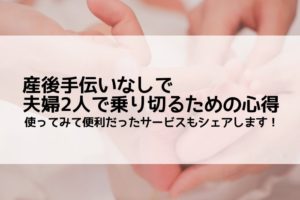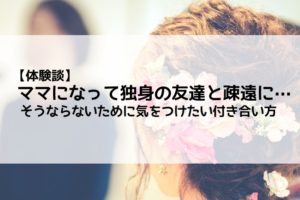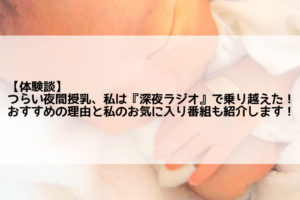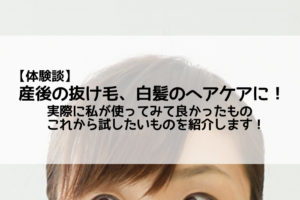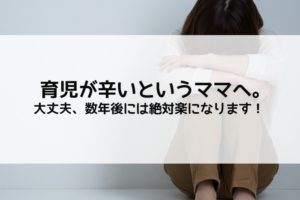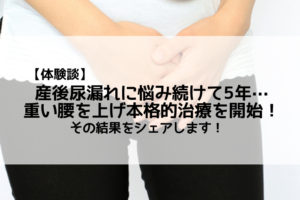Meow-Meow
最新記事 by Meow-Meow (全て見る)
- 妊娠が分かったらやるべきこと。受診の目安や手続きの流れ、周りへ報告するときに気をつけることなどまとめました - 2019年4月26日
- 【妊娠超初期~臨月まで】つわり、便秘、眠気…妊娠中の「つらい」を乗りきる方法まとめ - 2019年3月11日
- サイズアウトした子ども服・ベビー服はどうする?「捨てない」わが家の活用法6つ - 2019年2月27日
ママテク(@mamateku)ライターのMeow-Meowです。
“発達障害”という言葉が気になっている、というママさんも多いのではないでしょうか。
筆者の母は“発達障害”です。
そして、普段接しているママ友の中にも、同級生などの中にも「そうだ」と感じる人(実際にカミングアウトした友人も)が何人かいました。
これは偏見ではありません。いろんな場面で「母と同じだ」と感じるからです。
近年、“発達障害”という言葉をよく耳にするようになると同時に、その特徴も多くの人の知るところになりました。
したがって“空気が読めない人”“周囲から浮いている人”がいると、発達障害を疑うこともあると思います。
発達障害を見分けるのは難しく、ただの『性格』である場合もありますが、そうでない場合ももちろんあると思います。
潜在的なものも含めると、“発達障害”の人口は決して少なくなく、学校や公園などで、こういった“発達障害ママ”さんと出会う機会もきっとあると思います。
そうなったとき、おそらくその人に対してイライラしたり、不快に感じることが多々あると思います。
話が通じなかったり、突然傷つくことを言われたりするので、筆者も母と距離をとっていた時期もありました。
それは「日常的」であり、この先「治る」ことはありません。
【スポンサードサーチ】
周りの人が「そういう人なんだ」と理解し、うまく付き合うほかにないのです。
そんな母との日々をもとに、“発達障害ママ”との付き合い方、“発達障害ママ”の子育てについて触れてみたいと思います。
現在生きづらさを抱えている方が生きやすくなるように、何か感じてもらえたらと思います。
パッと読むための目次
母が“発達障害”だと分かったきっかけ
冒頭で述べたように母が“発達障害”であると、筆者が気付いたきっかけについて説明したいと思います。
周りと違う母
筆者は子どもの頃から、「うちのお母さんは、友達のお母さんとなんか違う」と感じていました。

子どもながらに「話が通じない、すぐ怒るし怒り出したら手がつけられない、大人なのに子どもみたいに失敗する」という風に母のことを見ていました。
そのときは“発達障害”なんて言葉は知る由もありませんので、母の『性格』だと思っていました。
ですが、高校生にもなるとあまりに友達のお母さんとギャップがありすぎるので、「何か精神的な病なのではないか」と心配になりました。
その後、“発達障害”という言葉がよく聞かれるようになり、その特徴も分かってくると、母がそれに該当するのではないかと漠然と思うようになりました。
でも、まさか親に向かって「病院に行け」とも言えません。
しかし、その思いは年々強くなっていくばかり。
そして、自分も結婚して子どもを持つと、“発達障害”の話題はより身近に感じられるようになりました。
育児関連の情報のなかに頻繁に出てきますし、ママ友の間でも「うちの子“発達障害”かな、大丈夫かな」という話が出るからです。
“発達障害”についての知識もだいぶ深めることができ、皮肉なことに今では「母は間違いなく発達障害だろう」と言えるくらいの確信を持てるようになったのです。
筆者が考える“発達障害”の特徴とは?
母は、簡潔に言えば「周りに注意を払うことが苦手で、ひとつのことに集中すると他のことを忘れてしまう(後でどうなるか考えられない)」のです。
これはADHDと呼ばれる、注意欠如・多動症の主な特徴のようです。
“発達障害”にはさまざまな症状があり、程度も日常生活にほとんど支障のない軽度~支援が必要な重度まであります。
筆者が分かっている“発達障害”についての情報は、あくまで母の場合なので、すべての方にあてはまるものではありません。
以下は、大人のADHDの特徴です。
- 不注意=ケアレスミスが多い、なくし物が多い、忘れっぽい。
- 多動性=時間があってもゆっくり休むことができず、落ち着かない。
- 衝動性=思ったことをすぐに口にしてしまう、衝動買いをしてしまう。
むやみに「あの人も?」「この人も?」と疑うのは賢明な行為ではありませんが、中には思い当たる人もいるでしょう。
『天然』や『おっちょこちょい』などの性格なのか、それとも“発達障害”かどうかの判断は難しいですが、ひとつの目安として筆者が言えることは、母を見ているとこういった特徴が『性格』だけとは思えないほど目立っていて(明らかにおかしい、普通とは違うということが側にいると分かる)、そのせいでずいぶん“生きづらく”なっているということです。
「社会人であれば当然できるはず」のことが「できない」ため、そのぶん大人の“発達障害”は顕著だと感じます。
一方子どもだと、
- 授業中に席に座っていられない
- 欲しいものを我慢できない
- 宿題をいつも忘れる
などが挙げられますが、こういった症状はどんな子供でも少しは見られることがあるため、“発達障害”かどうかの判断が難しいようですね。
母が“発達障害”ではないかと感じた出来事
- 買い物に行くと、50%くらいの確率で買った品物を忘れて帰ろうとする(タクシーやバスに忘れて、タクシー会社に電話したことも数えきれない)
- パンやお菓子を買うと、家に着くまで我慢できず食べてしまう。
- 極度の方向音痴。広くて複雑なデパートのトイレに入ると、出られないことも。
- 衝動買いが止められない(月に10万以上は無駄なものを買っている。娘である筆者が返品したり売ったりしている)
- なぜかクレジットカードを次々に作ってしまう。
- ときどき、かなりの偏食ぶりを発揮する(バナナしか食べない、麦ごはんしか食べないなど)父や私が栄養失調になりかけた過去も。
- 「長い文章」「長い話」が理解できない。いくつかのセンテンスが含まれていると、そのうちの一つのセンテンスについてしか頭に入らないので、何度も説明が必要。
ここまで読んでもらえれば、「普通の人と違う」ということが分かってもらえるのではないでしょうか。
母は、医師の診断を受けたわけではありません。本人も気付いていません。
あくまでセルフチェック(筆者が本人の代わりに)診断をしただけのこと。
しかし、父も、母をよく知る親戚も全員一致で“典型的な発達障害”と言います。
病院へ連れて行くことも一時期は考えましたが、いろいろ調べているうちにメリットがそんなに無いと分かりました。
発達障害は『治療』はできますが、あくまで『対処療法』であり、生活環境を改善させて暮らしやすくすることが目的だということなので、外での仕事もリタイヤして趣味に生きている母にはそれほど必要とは感じません。
医師の診断を受ければ『障害者手帳』が申請できますが、さまざまなサービスが受けられるようになる利点があると同時に、差別を受けるデメリットもあるという“もろ刃の剣”です。
それに、自分が“発達障害”だと知ることは、“障害者”だと認識するということ。
本人が受けるショックは少なくないはずです。
以上のことから、今のところは母本人に“発達障害”の可能性を告知するメリットが見つからないため、筆者の心にしまっています。
発達障害の母のことで困ったこと、周りへの影響
つらかった子ども時代
日常生活に支障はなかったのか?と聞かれると、「大いにあった」と答えざるを得ません。
本人は楽観的ですぐに忘れてしまうタイプなので、むしろ困っているのは周りの方だったりします。
まず、母は長い文章を理解できないため、学校からのプリントや連絡ノート、説明書の類、お知らせハガキなどは私が読んでひとつずつ説明してあげないといけませんでした。
子どものころから「長女だからしっかりしているね」と言われていましたが、私がしっかりせざるを得なかったのです。
母は他者とのかかわりが苦手だったため、育児の情報も得られず、保育園・幼稚園に入るにはだいぶ前から準備が必要だということが分かりませんでした。
その結果、母は自分でしつけや教育がうまくできないので保育園におまかせしたかったようですが、うまくいかず私は半年ほど保育園に通っただけでした(私は5歳までトイレトレーニングが未熟だった)
小学校で参観日がありますが、私は母に来てほしくありませんでした。
なぜかというと、下駄箱で靴を脱ぐのを忘れて土足で入ってくるうえ、「○○○○(私のフルネーム)の教室はどこですか?」と先生・保護者関係なく手当たり次第聞いてまわるので恥ずかしかったからです。
おそらく「○年○組」が覚えられなかったのでしょう。
買い物中にはぐれたり、学校からの帰りが少し遅いだけで110番をされたことも何度かありました。
そんな母と長年暮らしていた父は、大変な苦労だったと思います。
結婚前はもしかしたらただの『おっちょこちょい』『天然』だと思っていたのかもしれませんが、家族になるとそれでは済まされない現実に直面します。
そのせいか分かりませんが、私が幼い頃に父は数年間うつ病で引きこもっていた時期がありました。

そして、その後は単身赴任の仕事を見つけて、離れて暮らすようになりました。
このとき、私は父という味方を失って、母と二人きりの生活にずいぶん不安を覚えた記憶があります。
そんなわけで、筆者は「子ども時代を子どもらしく過ごす」ことができませんでした。
周りの友達みんなが何も考えずに遊んでいるように見え、友達のお母さんは優しくて知的で大人っぽく見えて、羨ましいと思っていました。
大人になってからの、母との関係
では、筆者が大人になり、母のもとを離れれば“発達障害”のことなど忘れられるかというと、そうではありませんでした。
大人になっても母に振り回されることがたびたびありました。
ほんの一部ですが、そのエピソードを紹介したいと思います。
エピソード①:チーズ
あるとき、母がブルーチーズを買ってきました。青かびの生えた、独特な臭いのする、あのチーズです。

私もチーズは好物だったので、少しつまんで食べてみました。すると、かなり塩分が高いもののよう。
「これ、けっこうしょっぱいね。フランスパンとか欲しくなるよね」と私は母に言いました。
普通であれば、「ああ、そうだね」「(逆に)いや、そうかな?」とか「明日買ってこようか」など、私の感想に対しての自分の意見が返ってくるものだと思っていたのですが、

私は美味しくないなどとは一言も言っていないし、フランスパンを要求しているわけではありませんでした。
このように、相手が言っていることを正しく理解してくれないことが多々ありました。
人の感情や雰囲気を読むよりも、相手の発した「言葉」を「文字」としてそのままの意味で受け取ってしまう節があるなと感じます。
普通の人であれば、前後の状況や相手の表情、ニュアンスから「言葉通りの意味ではない」と分かるはずのことが、分からないのです。
だから、私は「母とは話が通じない」とずっと思っていました。
エピソード②:彼氏
社会人になってから、付き合った彼が実家に来たときのことです。
予定していた訪問ではなく、私が実家にいる間にどうしても渡さなくてはならないものがあり、急に彼が来ることになりました。
母にはその旨を伝えて、「そうなの」と軽く納得したようだったのですが…。
彼と会えた嬉しさもあり、私は玄関先で長話になってしまいました。といっても、1時間も経っていません。
突然、鬼の形相で母が出てきて、

状況がのみ込めず、私も彼も唖然とするばかり。
このように、頭に血が上って、一気にいろんなことを爆発させることがたびたびありました。
きっかけは、いつもほんの些細なことなのです。
なのに、「自分は被害者だ。こんなに苦しんでいる」という思いに襲われるようです。
それに加えて、この出来事以来、母のなかで彼の印象は「悪いまま」になりました。

と。いや、あの状況ではごく普通の反応だったと思うのですが、母の思い込みには何を言っても通じません。
彼は二度と実家に連れてくることができず、別れてしまいました。
エピソード③:結婚式
きわめつけは、私の結婚式でのできごとです。
思ったことをすぐに口にしてしまう衝動性があると書きましたが、このときもそうでした。
母が結婚式での振る舞いかたを教えてほしいと言うので、私は事前にタイムテーブルを見せて事細かに説明して練習しました。
“発達障害”の母には、そうしてあげないといけないと分かっていたので、そこまでは良かったのですが…。
披露宴中は、両親は基本的に後方で座っているだけで良かったので、私はとくに何も言わなかったのですが、夫の母親が「夫の職場の人たちにお酌をして回っていた」そうなのです(私たち新郎新婦はまったく気づかなかった)

これは、マナー的にしてもしなくても良いことですし、まさか私も夫もするとは思っていなかったので予想できませんでした。
すると、最後のゲストのお見送りの直前。
母は私の目の前に来て、「どうして言ってくれなかったの!私が恥をかいたじゃない!」と泣き始めました。
向こうの両親があいさつ回りをしていたのに、私は教えられていないのでできなかった、という意味のことを言っているのだということはなんとか呑み込めたものの、これからゲストたちが出てきて一人一人にプチギフトを渡すという大事な『お見送り』が待っているタイミングでそんなことを言われ、私は衝撃のあまり頭が真っ白になりました。
式場の人のアナウンスで、母は去っていきましたが(お見送りには一人だけいなかった)、私は母の言動によって心がひどくかき乱され、ゲストひとりひとりの誰にどんな言葉をかけたのか、ちゃんと笑えていたのか、記憶がありません。
常識を持ち合わせていれば、娘の一生に一度の晴れ舞台を、最後の最後に台無しになんてしませんよね。
言いたいことがあるなら、結婚式が終わったあと(しかも当日ではなく後日あらためて)言えばいいこと。
でも、“発達障害”の母は一度自分が被害者だと感じてしまうと、こらえることはできません。
“発達障害”の人がうまく生きる方法
ここまで大変さばかりを書いてきました。“発達障害”の人は、さんざん周りに迷惑をかけて、不幸な人生を歩んでいるように見えるかもしれません。
しかし、紆余曲折はあったにせよ、母は自分では比較的ハッピーだと感じているようです。
なぜかというと、他人から悪意を向けられてもあまり気づかず、逆に人からの好意は素直に受け取るという性質が、本人の感じる幸福度に大きな影響をもたらしていると筆者は思います。
また、 “発達障害”だと自分で気づいていない(ただのおっちょこちょいな性格だと思っている)ための楽観さと、持ち前の明るく人懐こい人柄もあるのかなという気がします。
“発達障害”は、子どもの頃は「個性」「性格」だと思われることも多いです。
社会に出て、一人で生活するようになって、その“生きづらさ”に初めて気づいて受診すると“発達障害”だと診断されたというパターンも多く、「大人の発達障害」という言葉もあるほどです。
また、“発達障害”の方の中には、ある分野において特異な才能を持っている場合も多く、その特性を生かして仕事で成功している人は少なくないようです。
歴史上の人物ですが、レオナルド・ダ・ヴィンチやアインシュタインも自閉症などの“発達障害”だったといわれています。

母も例外ではなく、ほとんど描いたこともないのに絵を描かせると写真かと見間違うような鉛筆画が出来上がりますし、“形”や“色”などを認識する能力が人より鋭く、その特技を生かした趣味を今でも楽しんでいます。
このように、自分の特性を生かした「適職」に就けた場合、大人になってもとくに“生きづらさ”を感じず問題なく過ごせているケースもあります。
周りの人はどう接すればよいか
フォローする
“発達障害”は、周りの空気を読めず、「こんな時に、そんな話するの?」と驚くようなことをします。
たとえば母は、赤ちゃんが産まれた親戚の家に遊びに行ったとき、「最近虐待が増えているみたいね~かわいそうに。大丈夫よね?」と言い出しました。
産後のデリケートな時期で、かつ育児が大変なときにそんな話をするなんて、明らかに非常識です。
赤ちゃん誕生の祝福ムード一色だったその場は、母の一言で一瞬で凍りつき、ママやパパも明らかにイラッとしてました。
みんなの中にいても、一人だけ別のことを考え始め、それが口に出てしまうのです。
疑問に思ったり心配事があると、相手がどう思うか関係なく口に出してしまうのです。
そんなときは、「また、そんなこと言って~、ハイハイ」と冗談に変えるようなフォローをしてあげると、その場のみんなにも、言った本人にも笑顔が戻るのかなと感じます。
「空気を読んで!」とたしなめたり、指摘したりしたくなるとは思いますが、それは足がない魚に走れと言っているようなもので、いくら説明・注意しても理解するのは難しいからです。
聞き流す
筆者の母の例で示したように、“発達障害”は「言っていいこと」と「言ってはいけないこと」の区別があまりつきません。
たとえばママ友に「○○ちゃん、1歳すぎなのにまだパパもママも言わないの?どうして?」と言ったり、「帝王切開って麻酔だから楽なんだってね」と言ったりすることがあります(どちらも、“発達障害カミングアウト済み”の友人に、実際に私が言われたことです)
イラッとくるような言葉や、傷つくことを言われるときもありますが、本人は悪気があって言っているわけではありません。
純粋に“疑問に感じたこと”を聞いているだけだったりします。
あまり真剣に受け取らず、「うん、そうそう、そうなんだよ」とこれも受け流すことでイライラを回避することができます。
また、母は感情的になると、言っていることが今日と明日で違うなんてこともよくあるので、そんなときは右から左へと聞き流すことにしています。
本人は、だいたい落ち着くと自分の言ったことを忘れています。
同じ母親だということを忘れない
筆者自身も母親という立場になり、「自分の子ども時代」を思い返すと、当時の母は本当に一生懸命子育てをがんばっていたと思います。
物忘れをしたり、長い文章を理解できなかったり、周りの人とうまく付き合えなかったり…
それは普通のお母さんよりもっとずっと大変な子育てだったのだろうと想像できます(実際にかなり山あり谷ありな人生だったようです)
“発達障害”にとっては、周りに疎んじられて、ひとりぼっちになってしまうことが、一番辛いことです。
母も友人と呼べるような関係は一人もいません。
しかし、持ち前の明るさと人懐こさでカバーし、クラスのママたちとはなんとかやっていたようです。
“発達障害”の人は、とても素直で純粋な心を持っています。純粋すぎて、何でも口にしてしまいます。
しかし、基本的に性格が良いので、うまく付き合うことができれば、“良い友達”になれるのではと感じます。
筆者は、もし、周りから仲間はずれになっているママさんが“発達障害”だと感じたら、手を差し伸べてあげたいと思っています。

そして、これを読んでいる方にも、できる範囲で構わないので、そうしてもらいたいと願っています。
まとめ
“発達障害”は病気ではないと、筆者は思っています。
風邪を引きやすい、胃腸が弱いなどの体質と同じことで、特別視する必要はありませんが、配慮してあげるべき存在なのかなと感じます。
一般的に自閉症、アスペルガー症候群、学習障害、注意欠陥多動性障害などが“発達障害”と呼ばれていますが、一口に“発達障害”とはいっても、症状はさまざま。
見かけでは分かりづらく、『個性』や『性格』だと思い、家族や本人でさえ気づかないケースも多いようです。
しかし、共通しているのは、「周囲とマッチするのが難しく、社会で生きづらい」という点だと思います。
“発達障害”は子どもの病気というイメージがあるかもしれませんが、そうではありません。
“発達障害”という言葉さえ知らず、気づかないまま大人になった人もたくさんいます。大人になってから診断されるケースも多いそうです。
自分の身の周りに「“発達障害”かもしれない」と感じる方はいませんか?
“発達障害”は理解してもらえないと、「ただのトラブルメイカー」「空気の読めない人」と言う風にとらえられてしまいます。
そうすると、本人・子ども・周りの人たちすべてが“生きづらい”状況に陥ってしまいます。
もし身の回りで“発達障害”かもしれないという方がいれば、少しでもこの記事のことを思い出してもらえれば嬉しいです。
そして、本人や周りの人が生きやすい世の中になればいいなと思っています。