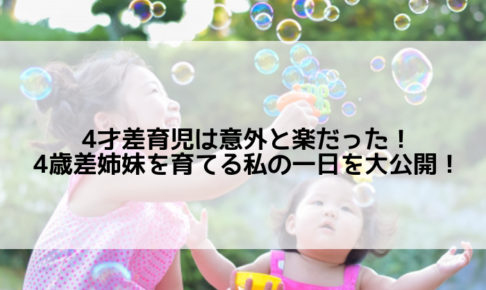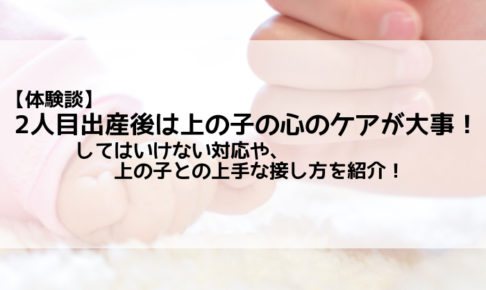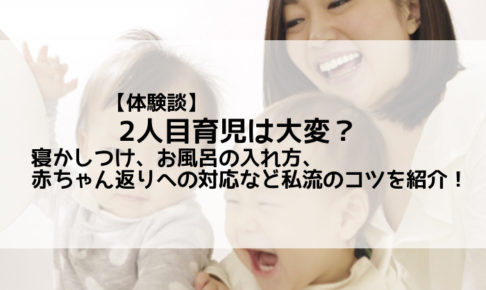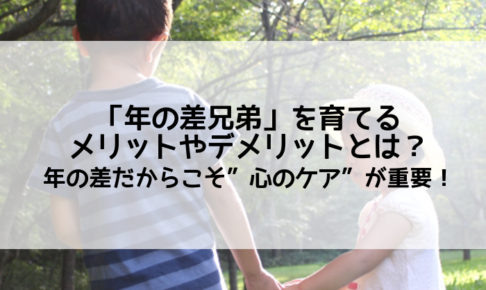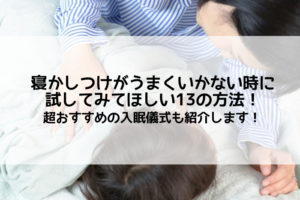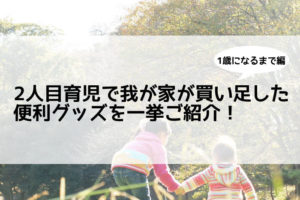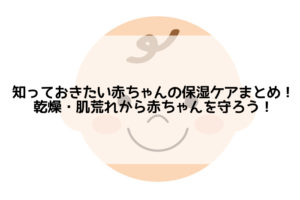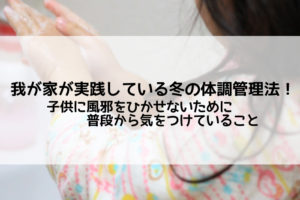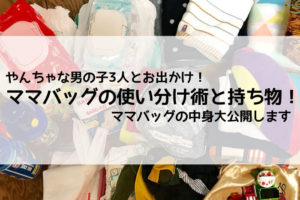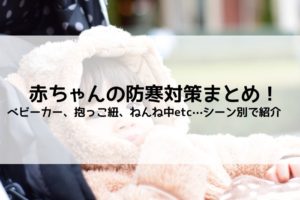ChiKa
最新記事 by ChiKa (全て見る)
- 育児が辛いというママへ。大丈夫、数年後には絶対楽になります! - 2019年4月12日
- 【2人目ママ向け】幼稚園ママ友トラブルを未然に防ぐために気をつけるべき3つのポイント! - 2019年3月20日
- 混合育児のコツ・スケジュールを大公開!混合育児成功のポイントをシェアします - 2019年2月25日
ママテク(@mamateku)ライターのChiKaです。
年齢がいくつになろうと、子供を授かって産むということは喜ばしいことですよね。
子供を育てるのはとても大変ですが、赤ちゃんが家にいるだけで家族みんなが笑顔になって幸せな気分になれるものです。
しかし、そんな気分なのはもしかしたら大人だけかもしれません。
というのは、赤ちゃんのお兄ちゃん・お姉ちゃんにあたる「上の子」的には手放しでは喜べない部分もあるのです。
赤ちゃんが産まれるまでは「いいお兄ちゃん(お姉ちゃん)になるんだ!」と張り切ってくれていたのに、いざ下の子が産まれてしまうと途端に複雑な気持ちになってしまうことがあるのです。

そしてそれは上の子が小さいほどその傾向が顕著です。
弟や妹の誕生が嬉しい気持ちと、自分自身がまだ両親に甘えたいという気持ちが自分でもコントロールで出来ずに悶々としてしまうのです。
しかし、逆に上の子と下の子の年齢が離れている場合は、一人っ子歴が長かったので「何だか、弟(妹)が出来たという実感がない…」という子もいれば、待望の弟や妹に「自分が親だ!」と言わんばかりに母性や父性を発揮する上の子もいます。
このように、年の差が空いていない兄弟に比べると心の準備が出来ている上の子が多いのが「年の差兄弟」の嬉しいところです。
親心としては、兄弟姉妹は仲良くしてほしいと思いますよね。
【スポンサードサーチ】
今回は、そんな上の子と下の子の年齢差に開きがある「年の差兄弟」にスポットを当てて、年の差がある子供を育てるメリットやデメリット、年の差育児で大切にしたいことなどをご紹介していきたいと思います!
パッと読むための目次
そもそも「年の差兄弟」とは何歳差くらい?
子供が2人以上いると、子供たちの間で必然的に発生する「兄弟姉妹」という関係。
私がよく見かける兄弟姉妹の年齢差は、2歳から3歳くらいの間隔であることが多いです。このくらいだと「年の差兄弟」とは言えないですよね。

上の子もまだまだママにベッタリしていたいというの子もいて、赤ちゃんが産まれても

- お兄ちゃん(お姉ちゃん)になった
- 赤ちゃんを大切にしたい!
もちろん、最初からパパやママと同様に深い愛情を赤ちゃんに対して持っている子もたくさんいます。
一般的には、5歳から6歳以上兄弟間の年齢が離れたら「年の差兄弟だね!」と言われることが多いようです。
5歳から6歳というと、上の子が小学生くらいになり、ある程度自分のことが自分で出来るようになって、自分の世界が広がりだした年齢ですよね。
これくらいの年齢になると単純に「赤ちゃん可愛い!」「自分もしっかりお手本にならないと!」と思える子が多くなるようです。
弟や妹が出来るのを心待ちにしていた子にとっては、親が思っている以上の喜びを感じていることでしょう。
また、個人の価値観によっては3歳差や4歳差で「我が家は上の子と下の子の年が離れている」と思う人もいるかもしれませんが、育てているうちに年の差を実感するのはやはり「上の子が小学生のときに下の子が産まれた」というくらいの年の差です。
上の子が未就学児であるかそうではないかということはかなり大きいところだと思います。
「年の差兄弟」のメリットは?
年の差兄弟の最大のメリットは、上の子のお世話からある程度手が離れているので、ママは余裕を持つことができますし、下の子にもしっかりと向き合える時間が増えるということです。
上の子と下の子で年齢差があまりないと、上の子のお世話と下の子のお世話が同時進行になるのでママはかなり大変な思いをします。

ちなみに私自身は兄と年子で、母は

上の子と下の子の年齢が近いと将来一気に育児が終わるということや、上の子と下の子の年齢による価値観も近いので一緒に遊んでくれるなどのメリットがありますが、子供が小さいうちは本当に大変です。
「子供同士で仲良く遊んでるな~」と思っていたのにいつの間にかケンカに発展していて、原因がよくわからないケンカの仲裁を何度もすることになるでしょう。
近い年齢の兄弟を育てるママは肉体的・精神的ともにとても大変なのです。
しかし、上の子がある程度大きいと、最低限の自分のことをすることができるので心にも体にもゆとりが出来ます。
上の子も

そして上の子は、自分が小さい頃にパパやママからしてもらったようなことを小さな弟や妹にしてあげようと自分なりの愛情を注いでくれることでしょう。

また、上の子が小学生高学年から中学生くらいだと赤ちゃんを抱っこすることもできるので、夕飯の支度で慌ただしいときに「ちょっとだけ構ってあげて!」とお願いできちゃうことも。
また、もし上の子が女の子だと「第2のママ」として振る舞ってくれるので、ママとしては大助かりです。
それ以上に、母性に溢れて自分の妹や弟を可愛がる姿はママからするとたまらなく愛しくて嬉しいものですよね。
ちなみに長女が通う幼稚園には、上の子(姉/大学生)と下の子(弟/幼稚園児)の年が16年離れているというお宅があります。
誰の目から見ても年の差兄弟で、お姉ちゃんは

- 弟が可愛くて仕方がない
- ママよりも自分になついてくれていて、とても愛しい
ですが、

16年離れているとは言っても、弟くんが産まれたときはまだ未成年なのでそう思うのも無理もありませんよね。
ですが、年が離れてると思うと大切にしなきゃという思いが強かったらしく、そんな考えはすぐになくなったそうです。
その子のママは、誰よりも信頼して下の子の面倒を任せられるし、上の子はお母さんに頼りにされているのを嬉しく思っているそうですよ。
「年の差兄弟」のデメリットは?
年の差兄弟は基本的にママの生活が比較的余裕が出来るというのがいいところです。しかし、デメリットも存在するのは確かです。
例えば、上の子の学校関係や習い事のイベントには必ず下の子を同行させないといけません。
パパが休みで家で下の子を見てくれたり、実家が近所でいつでも預かってくれる環境の人は当てはまりませんが、それ以外の人はどんな状態でも下の子を連れていかないといけません。

上の子の学校でインフルエンザやそのほかの感染症が流行っていたら、幼い下の子への感染が心配で連れていきたくないと思ってしまうものですが、そういうわけにもいきません。
逆に、下の子が体調を崩してしまったら上の子の用事にでかけることもできなくなり、我慢をさせてしまうことになります。
上の子も下の子も大切なママとしてはかなりのジレンマですよね…それが運動会や習い事の試合や発表会など上の子にとって重要なイベントなら尚更です。
ほかには、ママの育児関係にもちょっとだけ困ったところがあります。
上の子と年を空けて下の子を産むママは、育児にもすっかり慣れて余裕たっぷりでいられるのがいいところですよね。
下の子が熱を出したりしても、上の子のころの経験値があるので「こんなこともあったなぁ」「こういうときは○○すれば大丈夫」とドーンと受け止められます。
ですが、そんなママにも弱点があって、場合によっては「上の子の小さい頃の知識が下の子のときには通じなくなっている」なんてことがよくあるのです。

「年の差っていっても、そんな時代が変わるほど年数経ってないよ!」と思うかもしれませんが、育児関係の時代の流れはとても著しいです。
例えば我が家の場合、姉妹の年齢差は3歳差なのですが、上の子のときは「3種混合」だった予防接種が、下の子のときには「4種混合」になっていたことが衝撃的でした…。
便利なほうへと進化を遂げていたので「ラッキー」と思うことが出来ましたが、「勉強しなおさないとな」と思った1件でした。
「すでに1人育ててるし、わりと気楽」なのは間違いないのですが、知識面に関しては随時アップデートが必要になります。
意外と周りを見回してみると上の子の頃とは変わっていることがたくさんあるものです。
幼稚園や保育園も今では「認定こども園」になっているところが多数あるので「上の子がお世話になったところで!」とのんびり構えているといざというときに慌ててしまいます。
年の差が空く場合には「上の子のときの情報や知識」は使えないかもと思っておいたほうが良さそうです。
いつも育児に関するアンテナを張り続けて、上の子は上の子の、下の子は下の子の時代に合わせた子育てをしましょうね。
「年の差兄弟」でも「上の子のケア」は怠らないで!
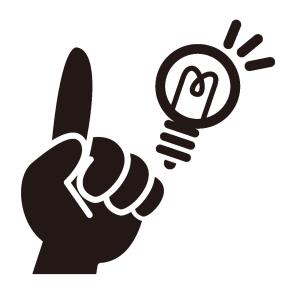
確かに上の子には手がかからなくなっているし、お手伝いをしてもらえることがあります。ですが、決して上の子から目を離していいわけではありません。

年の差がない兄弟姉妹だと、上の子が赤ちゃんの誕生によってパパやママを取られたと思い、自分の居場所がないように感じてしまうことがよくあります。
親は、そんな上の子の心の寂しさや不安を軽くするためにあれやこれやと手を尽くすのが今の常識ですが、年の差兄弟の場合はそれがおざなりになってしまうことがあります。
- もう充分愛情を注いだし、本人もわかっているはず
- 長い間一人っ子だったから、満足しているはず
確かにある程度手はかからなくなったかもしれませんが、上の子の育児が終わったわけではありません。
また、上の子には上の子の新しいステージや、それに応じた新たな悩みごとも発生します。
上の子が中学校などに上がり、新しい環境になるときは特に注意です。
小学生の入学時と違い、心が成長しているので複雑な感情を持っている子がたくさんいます。
さらには思春期に入るとこれまで経験のしたことのない悩みが出てくることになるでしょう。多感な時期なので、下の子以上に目が離せなくなります。
物理的にはラクになるかもしれませんが、精神的なところは誰よりも気にかけて一番近くにいてあげるようにしてあげましょうね。
下の子が小さいと手をとられがちですが、上の子ともしっかり向き合う時間を必ず取るようにしてあげてください。
年の差兄弟の上手な育て方
年の差がある兄弟姉妹を育てるのは、物理的にはかなり助かる部分があるのは間違いありません。
上の子が精神的にも成長しているのでママは助けられることがかなり多いでしょう。
しかし、それを当然と思って上の子の扱いに手を抜いたり「1人で出来るでしょ」なんて言ってすべてを委ねてはいけません。

そして上の子が自発的にお世話してくれるときや、どうしても手を離せないときにちょっとお願いするのはアリですが、それ以外のときに上の子がしっかりとしているのをいいことに、成長に大切な時間を奪って

そして下の子に対しても注意が必要です。
基本的には下の子が赤ちゃんのうちは上の子優先が好ましいのですが、下の子にある程度自我が芽生えたときにはスタイルを変えないといけません。

- お兄ちゃんはやりたいことやらせてもらってたけど、自分は出来なかった
- ママはお姉ちゃんの方が大切なんだ
年の差育児は楽な面ばかりクローズアップされがちですが、実際にはこのような精神的なフォローがとても大切になります。
年の差育児を成功させているママさんはみんな、「上の子育児と下の子育児を切り離して考える」ということをしています。
これは上の子と下の子の関与を一切無くすというものではなく、関与は程よく(人によってはガッツリ)ありつつも、成長のシーンに合わせてそこは子供個人の考えを大切にするというスタイルです。
例えば、下の子の七五三などのイベントに「家族のイベントだから」と上の子を強引に参加させるのではなく、上の子が「その日は前から友達と約束があるから」「習い事の練習がしたいから」と言ったらそれを優先させてあげるのもいいでしょう。

下の子の存在に左右されることなく、上の子の時間をある程度思うように使わせてあげるのはとてもいいことですよね。
また、下の子に対しては「上の子がこうだったから、アナタもそうしなさい」という押し付けも禁物です。
上の子の育児がそれでうまくいったからといって下の子をそのレールに乗せてしまうのは下の子がとてもかわいそうです。
前章でもお伝えしたとおり、上の子の時代とは育児のスタンダードが変わっていることもあるので、過去の経験をもとにして一辺倒に押し付けるのはよくありません。
育児には正解がなく、年の差がある兄弟姉妹が全員満足して同じ屋根のしたで暮らしていくのはとても難しいことかもしれません。
ですが、出来る限り子供たちが満足しながら成長していけるステキな生活を送るためには「上の子と下の子を切り離して考える」ということをして、それぞれを尊重してあげるようにするといいですよ。
まとめ
いかがだったでしょうか?
上の子とは年の差で産もうと考えている人や、実際に年の差で下の子を産んだけど、上の子や下の子とどう接していくべきかと考えていた人の参考になれたらいいなと思います。
いくら年の差があっても、上の子も下の子も可愛い我が子であることは変わりありません。誰も無理することなく、兄弟同士仲良く暮らしてほしいと思いますよね。
ですが、現実はどうしてもうまくいかないこともあり、結局は兄弟のどちらかがガマンをしなくてはならないこともあります。
兄弟がいれば年の差関係なくそういうことはあるでしょうけど、そんなときはフォローをしっかりとして「自分がないがしろにされた」「ママは、自分よりもアッチのほうが大切になんだ」と誤解されないようにしたいものですよね。
年の差兄弟は一見楽に思われがちですで、実際には上の子、下の子共に精神面でのフォローがとても重要です。
親が上の子と下の子を切り離して考えながら、上手に立ち回ることが大切なのです。